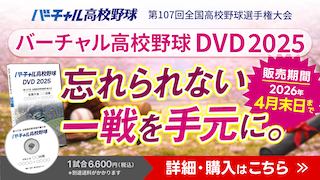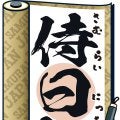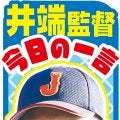鬼木達監督を迎えた鹿島アントラーズが好調だ。開幕戦こそ落としたが、その後は白星を重ねて首位に立っている。前節のヴィッセ…
鬼木達監督を迎えた鹿島アントラーズが好調だ。開幕戦こそ落としたが、その後は白星を重ねて首位に立っている。前節のヴィッセル神戸戦では、その強さの理由が垣間見えた。昨季王者との対戦で見えた「鬼木アントラーズ」の現在地をサッカージャーナリスト後藤健生が探る。
■「カウンタープレス全盛」の時代
高い位置からプレッシャーをかけて、相手陣内深くでボールを奪って一気にゴールに迫る……。世はまさに、「カウンタープレス全盛」の時代である。
Jリーグでもカウンタープレスを武器にヴィッセル神戸が2連覇を飾り、川崎フロンターレのパス・サッカーが一世を風靡したのが遠い昔のことのように感じられる。
その神戸に対抗するのが、どこのチームなのか、そして、どんなスタイルのチームが次の覇権を握るのか……。
パス・サッカーを駆使して川崎をJ1リーグの頂点に導き、リーグで4度の優勝をもたらした鬼木達監督が、今シーズンから鹿島アントラーズに移ってスタートダッシュに成功した。
「常勝軍団」復活のためのテーマとして、鬼木監督がまず掲げたのが球際の強さだった。
その意味で、J1リーグ第7節の神戸との一戦は、鹿島の現在地を占う試合であり、鬼木監督も「決勝戦のつもりで戦う」と公言していた。
その神戸戦も1-0の最小得点差ではありながら、鹿島は完勝した。
シュート数では鹿島の8本に対して神戸はわずかに3本。センターバックの植田直通と関川郁万、そしてGK早川友基が形成するゴール前の守りは大迫勇也、武藤嘉紀、エリキを擁する神戸の攻撃陣を完封。まさに“鉄壁”だった。
ハイプレスの掛け合いでも、最前線の鈴木優磨やレオ・セアラ、さらにサイドのチャヴリッチなども手を抜くことなくプレスをかけ続けた。
首位を走る鹿島の強さが、こうした守備力やプレー強度の高さにあることは間違いない。
だが、この神戸戦でもう一つ忘れてならないのは、ボールを奪った後の鹿島のプレー選択の幅だった。
■難しいのは「ボール奪取後」のプレー
ハイプレスをかけるのは、現代のサッカーのトレンドであり、世界中の多くのチームが実践している。
だが、一つ難しいのはハイプレスをかけてボールを奪った後のプレーである。
たとえば、昨シーズン、16シーズンぶりにJ1に復帰した東京ヴェルディは、「J1で戦えるだけの戦力があるのか?」という開幕前の疑問の声を見事に払拭して、6位という順位でフィニッシュしてみせた。
東京Vを率いる城福浩監督は選手たちにハードワークを要求し続けた。実際、ゲームでちょっとでもサボったりしたら、それが主力選手であっても次の試合から起用されないなど厳しい指導を行い、選手たちはJ1で戦えるだけの力と自信を付けていった。
ハイプレスで相手ボールを奪う。奪ったボールは技術力を生かしてパスをつないで前に運ぶ。自分たちのボールになれば、全員が攻撃の姿勢を見せる。そうした、当たり前のことを積み重ねることで、1年の間に選手たちは見違えるように成長した。
最初は強豪チームに対して挑んでは跳ね返されながら、少しずつ実力を付け、最後には真っ向勝負を挑めるだけのチームに成長した。
■「頑張る」以上のことができるように
その東京Vが、さらなる躍進も期待された今シーズンは第7節終了時点で12位と苦労している。
たしかに、選手たちは昨年の初めに比べれば大幅な成長を見せている。J1の高いプレー強度の中でもボールをつなぐだけの技術を身につけ、「ただ頑張る」以上のことができるようになっているのだ。
だが、その分、「ハードワークを惜しまない」という昨年に見せていた姿勢が薄れてしまう瞬間があるのだ。ボールを奪った後の選択を間違えて、それが苦戦に結びつく場面が何度もあった。
相手ボールに対して、複数人でプレッシャーをかけてボールを奪う。だが、全員が相手ボールを奪うためにオリジナル・ポジションから離れて追い回すのだから、ボールを奪った瞬間には選手の配置が崩れていて攻撃に転じられない場面も多い。
そこで、奪ったボールをどのようにつないで攻撃に転じるのかの選択が難しくなる。高い位置でボールを奪いさえすれば、それだけで自動的に攻撃の形ができるわけではないのだ。