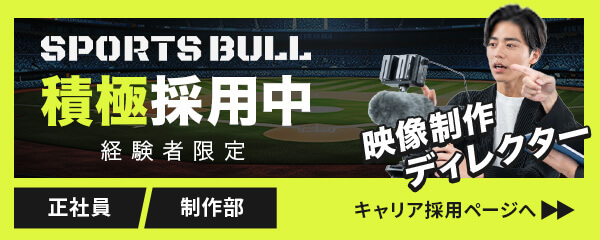蹴球放浪家・後藤健生は世界中で繰り広げるサッカー取材の道中で、多くの人と出会ってきた。そして、多くの珍獣とも出会ってきた。そのインパクトは世界大会の記憶とともに、蹴球放浪家の脳裏に深く刻まれている。■初めての中東で「ラクダだ!」 象や猫の…
蹴球放浪家・後藤健生は世界中で繰り広げるサッカー取材の道中で、多くの人と出会ってきた。そして、多くの珍獣とも出会ってきた。そのインパクトは世界大会の記憶とともに、蹴球放浪家の脳裏に深く刻まれている。
■初めての中東で「ラクダだ!」
象や猫のほかにも、世界中のあちこちでいろいろな動物を目にしました。
1993年のワールドカップ・アジア1次予選で、ハンス・オフト監督の日本代表はアラブ首長国連邦(UAE)やタイと同じグループFに入り、日本(神戸・東京)とUAE(ドバイ・アルアイン)のダブル・セントラル方式で戦いました。
そのため、僕は4月にUAEを訪れました。僕を含めて、多くの日本人サポーターや日本人ジャーナリストにとっては、これが初めての中東地域経験でした。まだ日本からの直行便はなく、僕はアエロフロート航空を利用してモスクワ経由でドバイまで往復しました。
当然、郊外に出ればたくさんのラクダがいます。いや、街中にもラクダはのそのそと歩いています。ラクダは荷物の運搬などに使えますし、ラクダ・レースも盛んです。
なにしろ初めての中東ですから、すべてが珍しく、お祈りの時間になるとあちこちのモスクから聞こえてくるアザーン(お祈りを促す呼びかけ)に耳を傾け、そしてラクダがいると「あ、ラクダだ!」と皆で指さしていたものです。
同じ1993年秋には最終予選がカタールのドーハで開かれ、その後もワールドカップ予選やアジアカップのために、中東には何十回も行くことになります。すぐに、中東の街並みも砂漠も見慣れたものになってしまい、ラクダが歩いていても誰も気にも留めなくなっていきました。
■アルゼンチンで「アルパカ」目撃
そのほかにも、各地で“珍獣”を見かけました。
1979年に初めて中国旅行に行ったときには、上海の動物園でジャイアント・パンダを見物しました。1972年9月に日本と中華人民共和国が国交正常化すると、10月には上野動物園にパンダのカンカンとランランがやって来て「パンダ・ブーム」が訪れます。パンダは日本中の注目を集め、大変に大事にされていました。
そのパンダを本場中国で見てみようというわけです。
ところが、上野のパンダと違って上海の動物園のパンダは小さな檻に入れられて、あまり手入れもされていないのか、白い部分が茶色く汚れていたのです。「ああ、さすが本場だ」と僕はかえって感心したものですが……。
1978年のアルゼンチン・ワールドカップを見に行くために、ペルーやボリビアを旅行しましたが、このときはアンデスの高原でリャマやアルパカを何頭も見かけました。どちらも、アンデス山脈にいるラクダ科の動物で、その体毛が高級な毛織物の原料となります。
今では、日本でもリャマやアルパカは有名になっていますが、約半世紀も昔のこと、当時は僕にとってはかなりの珍獣のように思われました。
■背後で「ドサッ」という音がして
南米大陸やメキシコでは、イグアナも見かけました。
1995年のUー17世界選手権(現Uー17ワールドカップ)はエクアドルで開かれました。小野伸二や高原直泰、稲本潤一がいた日本代表は、初めてアジア予選を突破して世界の舞台に登場したのです。前回の1993年大会には中田英寿や宮本恒靖(現JFA会長)のチームが出場していますが、この時は「開催国」としての出場でした。
日本の試合はすべて首都である高原都市キトで行われましたが(グループリーグ敗退)、決勝は最大都市グアヤキルが会場でした。太平洋に面した港町。赤道直下の熱帯です。
ある日、グアヤキルの公園のベンチに座ってのんびりしていたら、背後でドサッという音がしたので振り返ると、そこには大きなイグアナがいたのです。見上げると周囲の樹々の枝には数多くのイグアナがおり、そのうち1頭が枝から落ちてきたようでした。
メキシコにもイグアナはいますが、1986年ワールドカップの会場となった都市はすべて内陸の高原地帯にありましたから、イグアナはほとんど見かけませんでした。ただ、メキシコの熱帯ではイグアナを食用にするということを読んだので、メキシコ市内でもイグアナを食べられるレストランがないかと思って、泊まっていたホテルで調べてもらったのですが、残念ながらメキシコ市内では見つかりませんでした。
というわけで、今回登場した動物たちのうち、僕が食べたことがあるのは象とラクダだけのようです……。