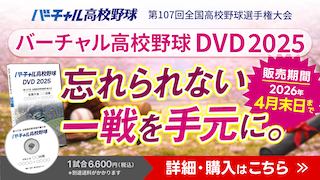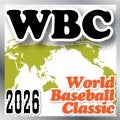連載第35回杉山茂樹の「看過できない」 鹿島アントラーズはちょっと変わったクラブだ。4-4-2を頑なに守ることが伝統のよ…
連載第35回
杉山茂樹の「看過できない」
鹿島アントラーズはちょっと変わったクラブだ。4-4-2を頑なに守ることが伝統のようになっている。川崎フロンターレでは4-3-3が多かった鬼木達新監督でさえも、4-4-2で戦っている。鈴木優磨を1トップ下と捉えれば4-2-3-1と言ってもいいはずなのに、表記は4-4-2だ。

横浜F・マリノスから鹿島アントラーズに移籍した小池龍太 photo by Fujita Masato
似たようなことが、かつてイングランドサッカーにも当てはまる時期があった。2000年代のある時まで、イングランドは4バックのほとんどが4-4-2だった。当時の欧州は、1990年代後半にフース・ヒディンク(PSV、オランダ代表などの監督を歴任)が発意した4-2-3-1が各地で流行していて、イングランドにもそれはじわりと伝播していた。マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルも、4-4-2というより4-2-3-1と言ったほうが正しいようなサッカーをしていた。
しかし、クラブもメディアも頑なだった。ある地元記者は苦笑いしながら「布陣は3列表記が基本。イングランドに4列表記は馴染まないんだ」と語っていたが、4-2-3-1は4-3-3という3列表記でも十分対応できる。4-4-2へのこだわりは欧州の他の国々より強かった。
4-4-2と4-2-3-1。違いは「サイドハーフかウイングか」「2トップが横に並ぶか、縦関係を築くか」の2点になる。
4-2-3-1を流行させたヒディンクに尋ねてみると「簡単に言えば4-3-3の両ウイングをMF的にした布陣だ」と教示された。また当時のオランダ代表監督で、現役時代はミランでプレッシングサッカーの中心選手として活躍したフランク・ライカールトは筆者に、「プレッシングを売りにしたミラン式の4-4-2とオランダ伝統の4-3-3を足して2で割った布陣だ」と筆者に述べている。
一方、4-4-2はイングランドのみならずイタリアでも流行していた。厳密に言えば1990年代中ごろまでということになるが、プレッシングサッカーを提唱したアリゴ・サッキ(ミラン、イタリア代表などの監督を歴任)は自らのアイデアを、4-4-2を用いて実践した。4-4-2は、プレッシングの定番的な布陣だった。
【サイドハーフの名手たち】
1990年イタリアW杯でイタリア代表のサイドハーフを務めたのはロベルト・ドナドニとジュゼッペ・ジャンニーニで、1994年アメリカW杯はドナドニとニコラ・ベルティだった。
また、マンチェスター・ユナイテッドの黄金期は、ライアン・ギグスとデビッド・ベッカムがサイドハーフを務めていた。2005-06シーズンにバルセロナとチャンピオンズリーグ決勝を争ったアーセナルは、アレクサンドル・フレブとロベール・ピレスがサイドハーフだった。ウインガーであるギグス以外はれっきとしたMFだ。文字どおりの「サイドハーフ」である。
4-4-2が流行すればサイドハーフ的な選手が育ち、4-3-3、4-2-3-1が流行すればウインガー的な選手が育つ。選手はポジションによって育てられる。
日本はどうなのか。鹿島に話を戻せば、その伝統的な4-4-2は4列表記に直せば4-2-2-2だった。ブラジルである時期まで幅をきかせていた布陣である。ジーコをはじめ、鹿島はこれまでブラジル人監督が頻繁に率いていたことと深い関係がある。
ただし、4-2-2-2はプレッシングサッカーに適した布陣ではなかった。1990年代、当時の加茂周日本代表監督はこの4-2-2-2を用いてプレッシングサッカーを実践しようとした。うまくいかないのは当然の帰結だった。
4-2-2-2は鹿島や加茂ジャパンに限った話ではなかった。ブラジル人指導者が当時のJリーグの各クラブには多くいた。4バックは4-2-2-2と同義語だった。
そこに守備的サッカーの波が押し寄せる。1998年に日本代表監督に就任したフィリップ・トルシエは5バックになりやすい3バック、3-4-1-2を採用する。その後に就任したジーコは4-2-2-2とトルシエ式3バックの二択だった。
その後にやってきたのがイビチャ・オシムだった。サイドハーフもウイングも不在のなかで、日本代表では初となる4-2-3-1を採用。3の両サイドを務めることができる人材が不足するなかで、その座に就いたのは遠藤保仁や中村俊輔だった。しかし、ゲームメーカータイプにサイドアタッカー役は難しかった。2007年アジアカップでは4-2-3-1の特長を出せずに終わり。4位に沈んだ。
【ウイングは続々と生まれているが......】
続く岡田武史監督は就任当初、サイドハーフやウイングを起用する意識がなかった。日本サッカー界がそうした選手を育ててこなかったので、当然といえば当然だが、代表監督として2期目を迎えた岡田監督自身もその責任を担っていた。ほどなくして4-2-3-1にトライし始めるが、欧州で見る4-2-3-1とはまるで異なっていた。サイドアタッカーが実質的にはサイドバック1枚の、4-2-2-2色の強い4-2-3-1だったからだ。
しかし、岡田監督は2010年南アフリカW杯では、文字どおりの4-2-3-1で戦うことができた。メインは4-3-3だったほどだ。左右のウイングの座に就いたのは大久保嘉人と松井大輔で、サイドアタッカーの適性がない選手をそこに起用せざるを得なかったオシム時代とは、ガラリと変わることができた。
これは日本サッカーの分岐点と言ってもいい変化だった。ブラジル式4-2-2-2はこれをもって終焉を迎えた。遅まきながら、日本でも4-2-3-1が普及し始めることになった。
アルベルト・ザッケローニもこれを採用、2014年ブラジルW杯に臨もうとしたが、布陣の特性にマッチした選手は急には育たない。初戦のコートジボワール戦の敗因は、左ウイングの香川真司が自らのポジションをカバーせず、真ん中でプレーしたがったことにあった。そこをコートジボワールに突かれた。喫した2失点はいずれも香川のポジション取りと関係する。
2018年ロシアW杯になって、ようやく日本は文字どおりの4-2-3-1を築くことができた。乾貴士、宇佐美貴史、原口元気、武藤嘉紀と、ウイング役が育ち、布陣の変化に追いつくことができた。ウイングはその後も日本に続々と誕生している。中盤に好素材が集中し"中盤王国"と言われた時代から、"ウイング王国"の時代を迎えることになった。
だが、サイドハーフは置いてきぼりになった。4-2-2-2ではない中盤フラット型の4-4-2が日本で流行らなかったことと、サイドハーフの人材不足は大きな関係がある。現在の森保ジャパンを見ても、三笘薫、久保建英、伊東純也、中村敬斗、堂安律とウインガーの駒は揃っている。だが、サイドハーフに相応しい選手はいない。つまり、中盤フラット型4-4-2では戦いにくい状況にある。
現在、3-4-2-1で戦っている森保ジャパン。4-3-3や4-2-3-1で戦う姿はイメージできるが、中盤フラット型4-4-2で戦う姿を想像するのは難しい。4-「4」-2の「4」の両サイドに適性がある選手はメンバーにいない。先述のピレス、ベッカム、ドナドニ的な選手だ。つまり、「中盤選手色50、ウインガー色50」。右サイドをセンスよく上手にカバーする選手である。
鹿島に再び話を戻せば、今季の4-4-2はいつになく整っているように見える。右のサイドハーフにきれいに収まる選手が現れたからだ。横浜F・マリノスから今季獲得した小池龍太である。その1列下で構えるもうひとりのサイドアタッカー、濃野公人とのコンビネーションで右サイドを的確にカバーしている。試合途中でふたりのポジションが入れ替わることもある。森保ジャパンからは絶対に拝めない上質なサイドの関係性だ。
多機能で頭脳的な小池。天然記念物に指定されそうな希少な選手を見るかのようである。
言い換えると、日本サッカーの盲点を小池に見ることができる。4-2-2-2から、中盤フラット型4-4-2を経ずに4-2-3-1、4-3-3へと移行した弊害だろう。小池のような選手をどれだけ育てることができるか。このあたりは指導者たちにも知恵を絞ってほしいものである。