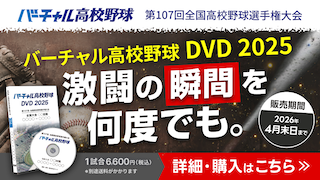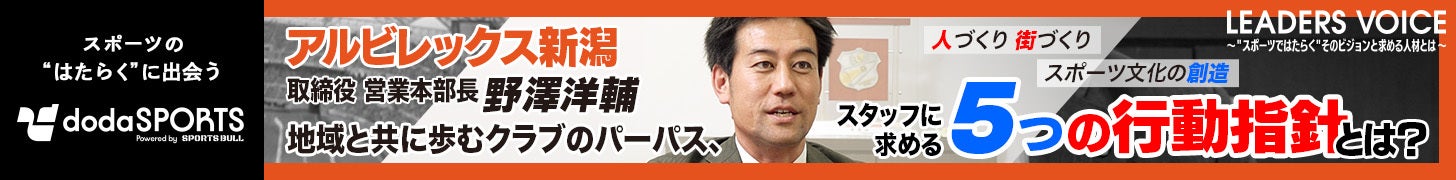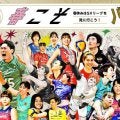蹴球放浪家・後藤健生は、世界中のサッカーを巡るために、駅や空港、スタジアムなど、各国の施設を利用する。その際に避けては…
蹴球放浪家・後藤健生は、世界中のサッカーを巡るために、駅や空港、スタジアムなど、各国の施設を利用する。その際に避けては通れないのが、手荷物検査だ。国や場所、実施する人によっても違う検査から、サッカーのリスク管理にもつながる、各国の「お国柄」を読み解く!
■安全の担保ために必要な「手続き」
空港で飛行機に搭乗する前には、必ず手荷物検査が行われます。検査を受ける身としては、きわめて不便で不快なことですが、航空機の安全を担保するために必要な手続きなので、僕たちはそれに従っているわけです。
ただ、空港によって、その手続きが少しずつ違うのはなんとかしてほしいものです。
荷物を検査台に預けて、パソコンなどを取り出して……と手順はだいたい同じなのですが、「上着を脱げ」と言われることもありますし、「ベルトまではずせ」と言われることもあります。「靴を脱げ」と言われることもありますよね。
「世界全体で」とまでは言いませんが、せめて日本国内では、その手順を統一してほしいものです。それが、お互いにストレスフリーをもたらすはずですから。
ところで、中国に行くと飛行機に乗るときだけでなく、しょっちゅう手荷物検査が行われます。高速鉄道はもちろん、市内で地下鉄に乗るときも改札のところで手荷物検査があって、荷物をX線装置に通さなければなりません(さすがにバスでは手荷物検査はありませんが)。
僕は、「そうだよなぁ」と思います。
■退屈そ~うな係員に「大いに疑問」
飛行機に乗るときに手荷物検査が行われるのは、爆発物などを持ち込ませないためです。飛行中に爆弾が爆発したらどうなるか……。誰にも分かります。
でも、飛行機だけでなく、たとえば新幹線で爆発事故(事件)があったら、どうなるのでしょうか。
250キロで走行中の新幹線の中で爆発があったら、間違いなく大惨事になります。新幹線は最大で16両編成で運行されています。各車両にたとえば50人が乗っていたとしても(かなり、空いています)、16両で800人という計算になります。
日航ジャンボ機墜落事故(1985年8月)では520名が犠牲となり、これが日本の民間航空史上最悪の事故とされていますが、新幹線で爆発が起こったら、これに匹敵する、いやそれを上回る被害が生じるわけです。
他の新幹線とすれ違う瞬間に事故が起これば、2編成の乗客に被害が及びますし、車両が市街地に飛び出したりすれば、さらに被害は大きくなります。
ですから、新幹線には飛行機と同様な手荷物検査が必要なのではないでしょうか。そして、できれば地下鉄でも検査は行うべきではないでしょうか。地下鉄サリン事件(1995年)も防げたかもしれません。
もっとも、中国の地下鉄駅にいる係員はまったくやる気がなさそうで、退屈そ~うに仕事をしていますから、あれで本当に犯罪を防げるのかどうか大いに疑問に感じますが……。
■当初は厳重も…次第に「手抜き」に
というわけで、世界を放浪していると、あちこちで荷物検査を受けることになります。
いちばん身近なのはスタジアムでしょう。
1982年のスペイン・ワールドカップは運営面で問題だらけの大会でしたが、手荷物検査もスタジアムによってバラバラ。いや、同じスタジアムでも行くたびに対応が違っていたりしました。
検査はセキュリティーのためでもあり、また治安対策でもありました。
スペインでは、独裁者だったフランシスコ・フランコ総統が1975年に死去。彼が後継者として育てたフアン・カルロスが国王に即位しましたが、フアン・カルロス国王は、意外にも急速に民主化を進めました。しかし、フランコという“重し”が取れたことで、カタルーニャやバスクの独立運動が盛んになり、バルセロナで行われた開幕戦の前には会場のカンプ・ノウ周辺で独立運動派がビラを撒いて、治安部隊と小競り合いを繰り返していました。
そんなわけで、開幕当初は手荷物検査はかなり厳重でした。しかし、その後、手荷物検査の係員たちの仕事ぶりは手抜きになっていき、最初はカメラまで持ち込み禁止だと言われて困惑していた人も多かったのですが、そのうちカメラなど見向きもしなくなり、その一方で突然、傘の持ち込みが禁止されてしまうなど、いい加減なものでした。