万年5位というレッテルは、もはや過去のものと言っていい。しかし、令和になってからの3シーズンはすべて4位に甘んじており…
万年5位というレッテルは、もはや過去のものと言っていい。しかし、令和になってからの3シーズンはすべて4位に甘んじており、秋季リーグの命題は2017年(平成29年)春以来遠ざかっている優勝だ。主務の高橋嶺一も真剣な表情で手応えを口にした。

「5位が指定席の時代もありましたが、常に優勝を争えるチームを目指したい。今年は4年生を中心に明るいのがチームカラー。ロボットのように動くのではなく、自分たちで考えて、一丸となって戦えている。秋こその思いです」
思えば、立教大にとって昭和の後半は”暗黒時代”だった。優勝は昭和41年春が最後。次に栄光をつかむのは実に23年後の平成元年秋まで待たなければならなかった。溝口智成監督は「うちは通算勝利数も優勝回数も5位。かつては優勝しなくて当たり前、という風潮のときもあった。そこから抜け出すのは至難だったが、近年は上位に食い込めている。新たな伝統を築いていければ」と前を向く。

立教大の根底には「自主自立」の精神が流れている。また、部員の多様性も他の5大学に比べると大きな特徴のひとつだろう。一般入試はもちろん、指定校推薦、アスリート入試、付属校からの進学など入部者の属性は様々。「それぞれに違うバックボーンがあり、野球の技術、勉強の仕方、ものの見方、考え方などお互いに刺激し合い、相乗効果はある」と溝口監督は言う。

そんな中、コロナの感染防止対策においても1カ月を掛け、マネジャー9人とオンラインで議論し、A4サイズ10枚に及ぶ「立教大学野球部新生活ルール」を作り上げている。高橋主務は「感染者を出さずにリーグ戦を迎えるために、みんなで協力し、知恵を絞って作ったもの。かなり大変でした」と充実感をにじませた。こんなところにも立教らしい自主自立の精神が表れているようにも感じられた。
何しろ、150人を超える部員ほぼ全員が「智徳寮」と隣接する2カ所の寮生活。クラスターの危険性を常にはらんでいたからだ。溝口監督は「どんなに対策しても感染者は出るときは出てしまう。そのときに、その部員が責められないぐらい徹底したルールを作り、守ることにした」と言い「本当によく我慢したと思う。その背景には全員に六大学の一員という強い思いがあったからでしょう」と感心する。

立教と聞いて浮かぶのは、まずは”ミスタープロ野球”長嶋茂雄さん。続いてタテジマのユニホームだろう。何しろ、日本最初のピンストライプ。溝口監督が「特別な思いがある」と話せば、宮慎太朗主将は「着るのはリーグ戦のとき、選手だけなので、みんな、あれを着たいと思っている。着ると気持ちがたかぶり、アドレナリンが出る」と言う。
もちろん、今回から入場OKとなった応援団の力も借りるつもりだ。
「昨秋4連敗後に勝ち点3を取れたのも応援の力があったからこそ」と宮主将。溝口監督は「敵ではあるが、向こうのチャンスメドレーが頭にこびりつき、時々口ずさんでしまうほど。野球と応援がセットになって神宮という舞台で独特の雰囲気を作り上げている」と話す。
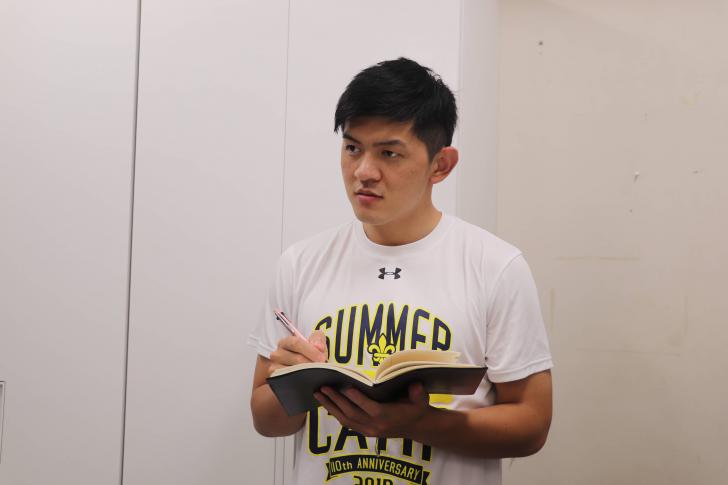
今回から取り入れられるギフティングサービス「Unlim(アンリム)」も発奮材料だろう。溝口監督は「興味深い企画です。例えば個人のバットは1本1万円。1球で折れることもある。施設のメンテナンスなど使いたい部分はたくさんあります」と話し、高橋主務は「そのためには立教野球が魅力的でないといけない。神宮で力を発揮したい」と意気込んだ。
今年のスローガンは「煌奮迅(こうふんじん)」だ。「煌」には光り輝くという意味があり、栄光をつかむためには奮い立って猛進する激しさが求められる。その一方で裏の合い言葉には「どんなときでも明るく、つらいときこそ明るく」という思いを込めて「祭」にした。祭を盛り上げるには当然、しっかりと準備をする必要がある。常勝軍団へ。タテジマの誇りを胸に「立教健児」は秋のリーグを戦っていく。
東京六大学秋季リーグ応援企画「声援がほしい。ROKUDAIGAKU MESSAGES」はこちら























































































