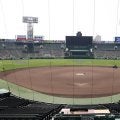「点取った後、切り替えて行こう!」 「さあ、良いバッター行くよ!」 「ここが勝負所、全員で行こう!」 試合中に聞こえるか…
「点取った後、切り替えて行こう!」
「さあ、良いバッター行くよ!」
「ここが勝負所、全員で行こう!」
試合中に聞こえるかけ声。ベンチから出ているものと思いきや、選手のものでも、監督のものでもない。この声の主は、ある審判員だ。4か月遅れで行われている東京六大学春季リーグ戦。「私自身は試合に集中しているので、注目していただいるなんて全く知りませんでした」と笑うのが、明大OBの審判員・山口智久さんである。
感染症対策が生んだ“副産物”だった。今回は観衆が上限3000人に制限されて歓声は少なく、東京六大学の華である応援団もいない。響いているのは蝉と選手と、審判の声。自然とグラウンドで発せられる音が耳に入る。結果、山口さんのとにかく明るい声かけが観客の興味を惹くことになった。
15日の早慶戦で9回2死から同点となり、球場全体のムードが上がる中、延長タイブレークのプレーがかかる際は「さあ、行くぞベンチー!!」と大声で盛り上げた。その掛け声に呼応したのは、選手よりも観客たち。感化されたように、ネット裏から自然と拍手が沸き起こる。「あの審判の声かけ、面白いね」との声も聞かれた。
なぜ、審判員として“声”で選手たちの背中を押すのか。山口さんは真意を明かす。
「審判員、特に学生野球の審判員というのはジャッジはもちろん大事ですが、選手を盛り立てるような声かけが大事だと思っています。学生野球には教育的立場もあるので、プレーがかかれば、厳しくすることもあれば、イニング間に関しては気を使って、選手を奮い立たせるような声をかける。49歳という厳しい年齢ではありますが、ゲームをコントロールする上で大事なのではないかと思って、ずっと続けています」
かける声にも、こだわりがある。単に大声でグラウンド上を盛り立てるだけでなく、前述のように試合展開に応じ、置かれた選手の心情に配慮。「ただ『頑張っていこう』だけでは、選手に気持ちは伝わらない。私もプレーヤーだったので、そこを意識しながら、選手の気持ちに沿った声かけをするように心がけています」と明かす。
審判も選手も同じ人間。「審判員が判定屋にならないように」というのがモットーにある。特に、意識するのは7、8、9回の3イニング。「野球において凄く大切なイニングなので、そこに向けていかに選手を集中させていくか。あとは序盤の1~3回も大事」。両校平等に盛り立てる振る舞いには、プレーヤーへの深いリスペクトが伝わる。こうして選手と一緒にゲームを作る“共同作業”で神宮を盛り上げている。

そもそもは「恩返し」で始めた審判員だった。
大宮南(埼玉)では外野手としてプレー。3年夏は県準優勝と甲子園まであと一歩に迫った。明大野球部では1年先輩の鳥越裕介(現ロッテコーチ)、1年後輩の野村克則(現楽天コーチ)らと練習に励み、出場こそなかったものの、4年生では三塁コーチャーとして神宮のグラウンドに立った。
転機は30歳の時だった。ホテル業に従事していたが、OBの善波達也氏(明大前監督)に「審判をやらないか」と誘われた。各校の野球部OBが務める東京六大学の審判員。前任の明大OBが勇退し、後任としてオファーが舞い込んだ。
「練習でも審判をやった経験はなくて。最初は母校に恩返しするつもりで、東京六大学の審判員だけ頑張ろうと思っていたのですが……」
気づけば、甲子園、都市対抗と高校から社会人まで幅を広げ、アマ球界の名物審判に。16年にはアマ野球審判員として初めて国際審判員のライセンスを取得し、昨年は侍ジャパンが優勝した「プレミア12」で国際大会の舞台に立った。
それほど、のめり込んだ審判員の魅力とは何なのか。
「1試合を終わった時の達成感。試合には上手くいかないことも必ずあって、次の試合に生かそうという向上心が生まれる。その達成感と向上心が審判員として感じる魅力でしょうか。あとは、選手と同じグラウンドでスタンドからの歓声を体験し、鳥肌が立つような緊張感も魅力かもしれません」
選手は打者ならホームラン、投手なら完封をすれば、分かりやすい成功だ。しかし、審判員には失敗はあっても、成功と定義されるものがない。
「確かに、私たちには成功というものがありません。だから、まず一番に考えるのは何もトラブルがなく、普通に試合を終えること。そこに僅差とか大差とかはあまり関係ない。試合中は苦しいことしかないですが、終わった後に清々しさを感じられることにやりがいを感じます」
グラウンドで起こるプレーは2度と同じものがない。だから、審判員は奥が深く、ゴールもない。
東京六大学の審判員を務め、およそ20年。マスク越しに見た選手で記憶に残った選手も多い。駆け出しの頃、02年春から4季連続優勝した早大は和田毅(現ソフトバンク)、青木宣親(現ヤクルト)、鳥谷敬(現ロッテ)らを擁した黄金期。「和田君の球速以上に感じる球の伸びとコントロール。球が体に隠れて見えづらく、ボールが突然ぱっと現れるような感じ。当時の早稲田は凄く強かったですね」と思い返した。
思い出深い試合もある。特に感動したのは早慶戦。審判は母校の試合は担当しない決まりがあり、早慶戦も裁くのは両校以外4校の審判となる。審判員にとっても特別な舞台だ。「初めて立った時は鳥肌が立ちました。特に早慶戦は応援団が内野と外野の2つに分かれているので、応援がやまびこみたいで、声が地面を震わせる感じ。甲子園、都市対抗の超満員も凄いですが、神宮は応援席との距離が近い分、格別です」と話す。

審判員をやっているから、得られる感動との出会い。それは大学野球以外にもある。
特に、印象に残っているのは1年前の夏の甲子園2回戦、球審を務めた明石商(兵庫)-花咲徳栄(埼玉)。ネット上で大きな話題を呼ぶ出来事の当事者となった。7回、明石商の投手の投げたスライダーがすっぽ抜け、右打席の花咲徳栄・菅原謙伸に当たった場面だ。
この時点で、山口さんは「あのボールはよけ切れない。ヒットバイピッチ(死球)にしようと判断した」。ただ、頭部死球だった場合、高校野球は臨時代走を指示する必要があるため、最初に「どこに当たったの?」と声をかけた。すると、菅原から返ってきたのは「自分のよけ方が悪くて、すみません」との声。驚いた山口さんは「どうして?」と聞いたら「よけ方が悪いので、ヒットバイピッチではありません」と言ってきたという。
まさかの返答。「正直、その瞬間、迷った」という。理由は「打者からの自己申告を受け入れていいかどうか」という葛藤があったからだ。
「普通は審判員の判断でヒットバイピッチか、もう一回打たせるのか、決めなければいけない。状況的に見て、自分から当たりに行っているわけではないので、本当はヒットバイピッチにしなければいけないと思うけど、間が空いてしまった。スタンドのお客さんもやりとりを見ているので、フェアプレーということもあり、自己申告を受け入れようと。最後は『あとで審判長に怒られてもいいや』と思い、打ち直しで立たせました」
すると、直後の初球を菅原が豪快に本塁打。試合には敗れたが、当時の自己申告を試合後の会見で話し、菅原の振る舞いが「フェアプレー弾」と報道されたが、球審を務めている山口さんの目線で当時のやりとりが明かされるのは初めてのこと。結果的にドラマを演出することになった。
「もちろん、ホームランを打つなんて私も思っていませんでした。ホームラン自体は結果論でしたが、自己申告のフェアプレーという判断でこのプレーを生かそうと思いました。あれが公式戦1号とのことだったので、本人も親御さんも嬉しい一本だったと思いますが、私としては花咲徳栄から(確認の)伝令が出ることもなく、逆に明石商の捕手も『申し訳ないです』と謝ってきたので、球審ながら良い光景だなと思って見ていました」
その後、何かの縁か、菅原は山口さんの母校である明大に進学し、再会した際には当時の話題になり「よく初球でホームランを打ったね」と初めて直接、労いの声をかけたという。こんな風に審判員ならではのドラマに遭遇することも魅力の一つかもしれない。
49歳となり、審判員としてはベテランの域。都市対抗決勝の球審を務めるなど、徐々に活躍のステージは広がっている。そして、国際審判員として1年延期になった東京五輪で審判員を務める可能性もあり、自身のキャリアについてもビジョンを描いている。
「今は審判員が高齢化している。若い人たちが審判員を目指すきっかけ作りをしていきたいし、国際大会を目指すサポートもしていきたい。そろそろ引退が見える年齢だけど、まずは私自身、来年に開催されれば東京五輪を目指したい気持ちがあるし、その経験を若い人たちに伝えて、山口のようになりたいと言ってもらえる審判でいたい。だからこそ、口だけでなく実際にやる姿をしっかりと見せないといけません」

そんな使命感を持ちながら迎えた2020年春の東京六大学リーグ戦は特別なものになった。
新型コロナウイルス感染拡大により、リーグ戦は8月に1試合総当たり制で実施。審判員も例年とは異なる試合をこなす。連日、30度を超える炎天下。選手は攻撃中に休める時間はあるが、審判は2時間以上、グラウンドに立ち続けることになる。
春、秋のシーズンなら5回終了後のグラウンド整備のタイミングに1度だけという水分補給も今回はイニングごとに行う。
「審判員はジャッジをするだけじゃなく、ゲームを運営するのも役割。試合進行していく上では難しい気候になる。例年は甲子園でジャッジをさせていただいていますが、甲子園球場より神宮球場の暑さの方が厳しい。甲子園はライトからレフトに吹く浜風を暑い中に少しは感じることができますが、風が全くなく、人工芝。選手はもちろん、審判員にとっても厳しい状況にあります」
体力を消耗する中でも続けているのが、選手への声かけ。「大きな声を出すのもしんどいですが、選手を奮い立たせながら、自分も気持ちが折れないように声を出しているつもりです」。今回は開催8日間で4試合のグラウンドに立ち、2試合で球審を務めて声を張り上げている。
東京六大学の審判員として、山口さんが持つ信念は2つある。
「野球は必ず勝敗がついてしまうものですが、試合が終わった後にお互いが全力を尽くして、良い試合ができたと思ってくれることが一つ。もう一つは見ているお客さんが終わった後に感動したり、また六大学に来たいと思ってくれたりするような試合運びをしたいということ。その中で、プロ野球より歴史のある東京六大学の魅力を絶やさないように、審判員も記録員も裏方がしている努力が少しでも伝わってくれれば幸いです」
100年近い歴史を持つ東京六大学を支える人は、いろんな場所にいる。選手と寄り添い、自らにできる方法で伝統を支え続けている山口さん。
その「声」を神宮で聞いてほしい。
<Full-Count 神原英彰>