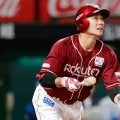連載「世界で“差を生む”サッカー育成論」:Jリーグで起きた2つのいざこざと暗黙の掟 スペインサッカーに精通し、数々のトッ…
連載「世界で“差を生む”サッカー育成論」:Jリーグで起きた2つのいざこざと暗黙の掟
スペインサッカーに精通し、数々のトップアスリートの生き様を描いてきたスポーツライターの小宮良之氏が、「育成論」をテーマにしたコラムを「THE ANSWER」に寄稿。世界で“差を生む”サッカー選手は、どんな指導環境や文化的背景から生まれてくるのか。今回は試合や練習中に、相手チーム選手や仲間同士で時折起こるいざこざについて。サッカーには闘争心が不可欠であると同時に、そうした怒りのパワーをピッチ外へと引きずらない重要性を説いている。
◇ ◇ ◇
Jリーグのピッチで起こったいざこざは、しばしばプレー内容以上に話題を集める。
2月、開幕戦のガンバ大阪対鹿島アントラーズの試合で、敵味方の交錯が物議を醸した。ボールをキープしたG大阪FWパトリックに対し、鹿島のFW鈴木優磨がタックル。両者はもつれ合い、鈴木が足をつかみ、パトリックが腕で振り払おうとした。実際のところ、パトリックの腕は当たっていないようにも映ったが……。結局、鈴木はお咎めなしで、パトリックはレッドカードを受けた。
判定を巡っては、外野のほうが騒いだ。
「なぜパトリックだけが裁かれる!?」
その不当さによって、今度は鈴木がバッシングを浴びる形になった。
5月、セレッソ大阪とG大阪による“大阪ダービー”では、G大阪の選手同士が派手な口論に及んでいる。
終盤、リードされた展開で、DF昌子源が左サイドのスローインで早く試合を再開しようとしたが、前線の動きに不満があったのか、大声で叱責するような口調と身振り手振りをすると、激高したFWレアンドロ・ペレイラが駆け寄り、お互いつかみ合いになりかけた。味方が仲裁に入って大ごとにはならなかったが……。
このシーンはメディアで大きく取り上げられ、「仲間割れ」と揶揄するように報じられた。SNSでは格好のネタになっている。「味方同士の喧嘩」というのは、たとえサッカーを知らなくても、一般化して語れるのだろう。道徳的に言って、人前で声を荒げて言い合う姿は模範的ではない。それに対し、人は何か意見をぶつけたくなる。
「争う姿を子供には見せたくない」
そんな意見もある。
サッカーの育成の観点から、どう向き合うべきか。
デポルティボの練習場で見た喧嘩腰の選手たち
「ピッチで起きたことはすべてピッチで収める」
それはスペインやイタリアだけでなく、南米各国などサッカーにおける一つの不文律と言える。
この不文律が生まれた理由は、ピッチ内での闘争が想像以上に激しく、お互いの憎悪を生みかねないところにあるだろう。プレー中は相手より有利に立つため、審判を欺くような行為も平然と行われる。最近はVARの導入によってめっきり減ったが、見えないところで相手を小突いたり、蹴ったり、削ったり、中には急所を握りつぶすような行為もかつてはあった。
サッカーはコンタクトプレーが基本にある。常に一触即発の状態。相手から際どいタックルを受けたら、報復したい、という悪意が生まれることもある。ピッチの中は戦争に近い。
もし、そのやりとりを試合後まで引きずったら……。暴力事件に発展してもおかしくないだろう。その連鎖を断ち切るため、「ピッチで起こったことはすべてピッチで収める」という暗黙の掟がある。サッカーというスポーツにおける自己防衛手段の一つで、オンとオフをはっきり分けているのだ。
ありあまる闘争心は、好ましくはないが、否定すべきでもない。お互いが協調して戦うことが本筋にはあるわけだが、切迫した心理はその境界線を時に越える。仲間に対し、叱咤に似た怒号にもつながる。
2000年代、小さな港町のクラブながら欧州中のビッグクラブを次々に倒していたデポルティボ・ラ・コルーニャの練習を筆者は取材しているが、思わず目を疑った。紅白戦で選手は喧嘩腰で、つかみ合いにまで発展した。驚くべきことに、監督以下スタッフが「殴り合いは禁止」としながら、そのギリギリのテンションを求めていた。
練習が終わった直後、デポルの選手たちは熱が冷めない様子だった。しかしロッカールームから出てくると、喧嘩同然だった選手が笑い合っていた。ピッチで起こったことをピッチで収めていたのである。
彼らは掟を守っていた。それだけの修羅場を乗り越えているからこそ、ジャイアントキリングもやってのけられたのだろう。
これは文化の違いも大きい。
日本人は意外にも感情的になりやすく、言い方は難しいが、本気で腹を立ててしまう。「プレーの中での単なる摩擦」と考えず、わだかまりがどこかに残る。オンとオフを使い分けられる、合理的な考えの持ち主は少ない。
判定に抗議したパトリックも守った不文律
「ピッチで起きたことはすべてピッチで収める」
その不文律は「恨みを残さない」という点で、とても理にかなっている。
冒頭、レッドカードを受けたパトリックが、ピッチを去る際にはお辞儀をしている。判定には不当を訴え、猛抗議した。納得はしていなかったはずだが、下された決断に対しては不文律を守っていた。
鈴木も判定に傲然と胸を張った。「汚い」「卑怯」と誹謗中傷を受けようとも、彼はルールの中、チームが勝つためだけの行動をしたに過ぎない。ピッチの中、勝つためになりふり構わないプレーをし、生き方を貫いている。
また、G大阪の昌子とペレイラも試合後には和解したという。クラブも特別なペナルティは科していない。それは、あるべき姿と言える。
ピッチの中での出来事は、できるだけ引きずるべきではない。
子供たちも目を背けず、ピッチで起こる出来事をすべて見つめるべきだろう。その上で自らが考え、己の中で正しい答えを出す。戦場は曖昧な塩梅の世界で、誰も答えは提示してくれないのだ。
不文律は、一つのヒントになる。(小宮 良之 / Yoshiyuki Komiya)
小宮 良之
1972年生まれ。大学卒業後にスペインのバルセロナに渡り、スポーツライターに。トリノ五輪、ドイツW杯を現地取材後、2006年から日本に拠点を移す。アスリートと心を通わすインタビューに定評があり、『導かれし者』(角川文庫)、『アンチ・ドロップアウト』(集英社)など多くの著書がある。2018年に『ラストシュート 絆を忘れない』(角川文庫)で小説家としてもデビュー。少年少女の熱い生き方を描き、重松清氏の賞賛を受けた。2020年12月には『氷上のフェニックス』(角川文庫)を上梓。