「電子版スポーツノートの可能性」後編、木村友輔氏を起業後に襲った病 スポーツの現場では近年、テクノロジーの発展とともに様…
「電子版スポーツノートの可能性」後編、木村友輔氏を起業後に襲った病
スポーツの現場では近年、テクノロジーの発展とともに様々なツールやサービスが開発され、日々のトレーニングをサポートしている。その一つとして注目されているのが、電子版スポーツノート「Aruga」(アルガ)だ。25歳の創業者・木村友輔氏は、筑波大学在学中に起業したキャリアの持ち主。子供の頃からサッカーに打ち込んできた木村氏は、なぜ電子版スポーツノートを開発することになったのか。後編では起業後に発症したうつ病の経験や、アルガのサービスの根底にある想いを語った。(取材・文=原山裕平)
◇ ◇ ◇
アイデアの着想は、筑波大のサッカー部時代にあった。
選手が個人の目標や振り返りを書き込む「サッカーノート」というものがある。今では競技を問わず、多くのスポーツチームで活用されているものだが、基本的には紙に手書きで、コーチ側も手書きでフィードバックすることがほとんどだ。
「筑波大も160人の部員がいて、監督は1人。160人分をフィードバックする作業はとても大変なこと。でもこれをIT化すれば、単純に指導者も楽になりますし、選手側もスマホに打ち込むスタイルなら、継続的に取り組めるようになるのではと思い、電子版スポーツノートを考えました」
これまで運用してきた「シェアトレ」は、発展性に限界を感じていた部分もあったため、新たなサービスを考える必要があった。そのなかで木村氏はこの「電子版スポーツノート」の開発に向けて、プロジェクトをスタートさせた。
ところが、ここで思いもよらないアクシデントが起きてしまう。
「会社のメンバーも増やし、資金も調達してやっていこうというタイミングで、うつ病になって働けなくなってしまったんです」
医者からは「働いてはダメだ」と言われた。夜は眠れないし、手も震える。動悸も激しくなった。木村氏は半年以上休養し、30人に増えた会社も解散。木村氏の下に残ったのは、「シェアトレ」時代からの共同創業者とインターン生2人の3人のみだった。
しかし、このうつ病の発症が、電子版スポーツノート「Aruga」(アルガ)開発を大きく前進させることになる。
「僕が休養している間に、残ったメンバーが、今のサービスの原型となるチャットボットを作ってくれたんです。うつになりかけた時、カウンセリングの人に相談に乗ってもらっていたんですが、そのサポートは週に1回くらいだったんです。つまり、“点”のサポートしか受けられず、継続的ではなかったんですね。でも、その“点”に加えて、毎日『体調どうですか?』と聞いてくれるような存在があれば、“線”のサポートになるんです。しかもチャットボットなら、手軽に毎日見ることができる。彼らがそういうものを開発してくれたんですが、これをスポーツビジネスに使えるんじゃないかと。ある人が誰かを継続して見てあげたいという想いを叶えるためのツールとして作ったものを、スポーツに応用させたのがアルガなんです」
アルガの根源にある「個人を見る」という発想
アルガとは、具体的にどういったサービスなのか。一言で言えば、「LINE」を介して指導者と選手をつなぐ「選手一人ひとりを育成するマネジメントツール」である。
選手側はチャットボットの質問や提案に応える形で、目標や日々の課題、練習の振り返りや、体調などを入力していく。指導者側は選手が入力したものを一覧で見ることができるため、それぞれの意識や状態を把握することができる。またそれに対してフィードバックを書き込むこともでき、選手側は指導者のアドバイスを適宜受けることができる。
選手が書き込んだものはデータとして残るため、学年が上がって他のコーチに引き継ぐ際にも、指導者側は初めて見る選手の特徴や情報をあらかじめ知ることができる。日常的に使う「LINE」を活用するため、手軽に簡単に、即効性のある振り返りができるのも、アルガの便利なポイントだ。
「最近はコロナ禍なので、ミーティングも頻繁にできなかったりしますが、このアルガがあれば、選手が練習でどんなことを考えているかが分かりますし、コミュニケーションを取りやすい環境が生まれると思います」
アルガの根源にあるのは、指導現場に重要な「個人を見る」という発想だ。
「寄り添いがベースですね。寄り添ってあげたいけど、これまでの手書きのノートではそこまで個人個人を見てあげることができない。でも、アルガではそれが可能になります。それぞれが何を考えて、日々の練習を行っているのか。指導者の目を拡張するためのツールになると思います。選手としても、『あのプレー良かったぞ』と、一言言ってもらえるだけで、だいぶ意識が違ってくるはずです。選手と指導者の隙間を埋めるツールでありたいと考えています」
また子供たちが常日頃から目的意識を持ち、どのように課題を乗り越えていくかを考えることにつながるツールでもある。これは、選手としてだけではなく、将来にも役立つものだと、木村氏は主張する。
「単純に自分で目標を立てて、振り返る力は社会に出てからも生きてくるものです。スポーツで上達したいと思った時に、できなかったところを改善していく。そこは普遍的というか、生きるうえで一段大事な力だと個人的には思っているので。そういったところを学びにできるツールでもありたいです。『スポーツを通じて、生き抜く力を育む』をスローガンに、僕らは頑張っていますから」
育成現場だけでなく磐田などプロチームも採用
昨年10月にローンチされたアルガは、すでに多くのチームで活用されている。実際にユーザーからは、どのような反応があるのだろうか。
「指導者の方は、選手の考えていることがより分かるようになったという反応が多いですね。この選手の課題はここだと思っていたら、本人の振り返りは全然違っていたということもあって、そこですり合わせができるようになったという意見もあります。あとは、自分が言っていることがしっかりと伝わっているかどうかが、振り返りを見れば分かるという声もありますね」
面白かったのは1、2年生のみにアルガを使わせ、引退間近の3年生には適用しなかったチームのケースだ。
「3年生は与えられたメニューをやるだけなのに対し、1、2年生は毎回練習に対して目標を持ってくるので、前向きな姿勢の子供が多かったそうです。一回一回の練習で、伸びが全然違うと。こういう意見を聞くと、自分が主体的に目標を持つことがすごく大事なんだなと、改めて実感しました。僕らとしても、目標を立ててやることで、少しずつでも前に進む嬉しさを感じてもらえるように設計していきたいと考えていますし、実際にこのサービスで変わってくる子供が増えているのは嬉しいことですね」
育成現場だけではなく、アルガはプロのチームにも採用されているそうだ。
「(2021年度では)ジュビロ磐田の強化部が使ってくれていて、J3のY.S.C.C.横浜ではチーム全員が利用してくれています。大学だと、立教大学の女子ラクロス部がアルガを導入して、2年連続で日本一になりました。それまでは紙に書いたものを、写真で撮ってLINEでコーチに送るというやり方をしていたそうですが、その形を簡単にできるということで、好評をいただいています。スポーツノートを活用しているチームは多いと思いますが、選手とのやり取りを手軽にできるこのサービスが、多くのチームに届いてくれたらうれしいですね」
すでに実用的なサービスとして運用されているアルガだが、今後はより使いやすく、機能性の高いものへと進化させていく考えがあるという。
「今、着手しているのは動画の送信をできるようにすることです。振り返りをした後に、『ここに課題があるのなら、この動画を見たらいいよ』というように、視覚的にもアドバイスを送ることができます。あとは、指導者側に選手一人ひとりの状態がカルテのよう一目で分かるようなデザインにもしたいと考えています」
社名に込めた「あるがままに」の想い
「アルガ」という名称には、育成現場で指導を行う木村氏の子供たちに対する思いが込められている。
「小学生を指導すると、やっぱり個性が全然違うんですよね。その子たちが伸びたい方向があって、それを邪魔しないようにサポートするのが、指導者の役目だと思うんです。そのサポートの裏方にはアルガのサービスがある。アルガを使っている選手たちが自分なりに考えて行動し、自分なりの方向に成長していけるように。つまり、それぞれの子供たちが『あるがまま』であってほしいという想いから、『アルガ』と名付けました」
プロを目指したプレーヤーであったはずの木村氏は、今ではすっかり「育成」にやりがいを見出している。
「今までフェイントができなかった子が、フェイントで何人も抜いていってしまう。そんな瞬間を目の当たりにできたら、本当に感動します。単純に子供が成長していくのを見るのが嬉しいんですよ。子育てに似ているんですかね(笑)」
一方で、育成に携わる人間として、大きな使命も感じている。
「アイデンティティが確立される時期に、自身の強みだったり、どこに喜びを感じられるかとか、そういうことに自覚的になれる子が増えていくことが、これからの時代には必要だと思っています。多様性のある社会の中で、自分が興味のあることを自分で知っている人の方が、幸福を得やすいと思います。それこそ、あるがままに生きられるように、自分で自分を知るというのが当たり前になるように。それを手助けできるようなサービスを作っていきたいです」
そこには、自身に対する戒めも込められているのかもしれない。
「僕自身、自分の幸福が分からないまま、他人の期待や要求に突っ走って、うつになってしまったところもあります。そこを反面教師にしてほしいですし、ああいう苦しみを持たないでほしいなと思います」(原山 裕平 / Yuhei Harayama)








































































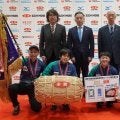



![アルカラス、難敵ポールを退け3年連続の8強進出!史上最年少の生涯グランドスラムに邁進[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012516260245513700.jpg)



