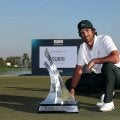王者の源流~大阪桐蔭「衝撃の甲子園デビュー」の軌跡第3回 今でこそ全国各地から逸材が集まる大阪桐蔭だが、創部当初は大阪…
王者の源流~大阪桐蔭「衝撃の甲子園デビュー」の軌跡
第3回
今でこそ全国各地から逸材が集まる大阪桐蔭だが、創部当初は大阪府大東市に自宅がある井上大や萩原誠をはじめ、通いの部員が多かった。
この世代で1年から寮だったのは、エースの和田友貴彦、キャッチャーの白石幸二、セカンドの澤村通、ショートの元谷哲也......。だが、自身も寮に住んでいた野球部部長の森岡正晃は、日本一を目指す以上はチームの足並みを揃えなければならないとばかりに、2年の夏が終わると通いの選手たちも「1年間、みんなで学ばんか?」と声をかけた。
人数に制限があり、全部員というわけにはいかなかったが、おもにベンチ入りしているメンバーが次々と入寮した。
この環境で自然発生的に生まれたのが、選手間でのミーティングだった。元谷が当時を振り返る。
「1つ上、2つ上の先輩は、選手同士でのミーティングはやっていませんでした。僕らの代になってから『やろう』となって。玉山(雅一)を中心に寮の食堂で集まって、『グラウンドでは歩かない』とか『もっと元気を出そう』とか、そういった単純なところからチームみんなで取り組んでいきました」
玉山が中心──これも当時の大阪桐蔭で自然と成り立っていた関係だった。強烈な個性を持った選手が集まったこの世代においても、入学当初から玉山が音頭を取れば、仲間はみな賛同したという。今でも玉山と親交が深い白石が言う。
「タマ(玉山)は、萩原とか1年から試合に出ていたヤツらを特別扱いせず、言うべき時はしっかりと自分の意見を言っていた。誰に対しても厳しく、優しかった。同級生なんですけど、感覚としては"頼れる先輩"みたいでしたね」
新チームになると当然のように玉山が主将になるのだが、任命したのは監督の長澤和雄だった。
「個性が強いのが集まっていましたから。そんななかで『アイツが言うなら......』っていう存在が、玉山しかいなかったんです。指導者や選手、みんなが納得するキャプテンが玉山でした」
玉山は小学生、中学生の時も所属チームで主将を務めた生粋のリーダーである。個性派を束ねる立場として、玉山が心がけたのは選手たちにのびのびと野球をしてもらうことだった。玉山が言う。
「今の桐蔭もそういう部分があると思うんですけど、当時から選手を締めつけずに尊重するという考えはありました。当時は無名校でしたけど、甲子園に出るという目標はみんな一緒でした。ただ、僕らの代はかなり個性が強かった。だから、自由にさせるなかでも締めるところは締めないと、チームがバラバラになる可能性がありました。それをミーティングだったり、僕が個人で話し合ったりして、なんとかまとめていった感じですね」
そんな主将が牽引するチームは、創部4年目にして初めての甲子園となるセンバツ出場を実現させた。そして初戦の仙台育英(宮城)戦では、主砲・萩原がホームランを放ち、エースの和田はノーヒット・ノーランという衝撃の甲子園デビューを飾った。
箕島(和歌山)との2回戦でも勢いは止まらず、2点を追う8回に玉山の同点二塁打など、一挙4点を奪い逆転勝ち。チームのムードは最高潮に達した。
「もう優勝しかないやろ!」
メンバーのほとんどがそう信じて疑わなかった。準々決勝の相手が「優勝候補筆頭」の天理を撃破した松商学園(長野)でも、自信が揺らぐことはなかった。
「長野の高校? 余裕やろう!」
ところが、そんな慢心をあざ笑うかのように、松商学園のエース・上田佳範の術中にはまり、大阪桐蔭打線は沈黙する。ストレートとカーブ、そしてナックルを駆使した投球に翻弄され、安打はわずか5本。0−3の完敗だった。

松商学園のエース・上田佳範から三振を奪われ天を仰ぐ大阪桐蔭・玉山雅一
全国制覇を疑わず、楽勝だと思っていた相手に足元をすくわれた。そのダメージは大きかった。玉山がセンバツ後のチーム状況を明かす。
「センバツは僕も含め、みんな目立ちたい一心でやっていたと思うんですよ。そこで負けると思っていなかった相手に負けて、だんだんと歯車が噛み合わなくなってしまって......センバツが終わってからは練習試合でも勝てなくなり、チーム力が落ちていることは明白でした。みんな余裕がなくなってもうて」
低迷するチームのなかでとくに重症だったのが、ふたりの「1番」だった。
ひとりは、大阪桐蔭の「1番打者」としてチームの得点源となっていた澤村である。新チーム始動から秋の近畿大会まで、練習試合を含め5割近い打率を誇っていた不動のリードオフマンが不振に陥った原因は、じつはバットだった。
「この年(1991年)の春から、消音バットが導入されるようになって、今まで使っていたものが使えなくなったんです。それに新しいバットも消音になったばかりで、種類が少なくて......。『どれも合わん。バランス悪いわぁ』って思いながら、結局、甲子園でも打てなくてね」
打者にとって"体の一部"ともいえる相棒を失った代償は大きく、センバツでは初戦の内野安打1本のみに終わった。だが、それ以上に澤村にとっての悔恨は、松商学園戦での不甲斐ない結果だった。
「『オレら優勝やん!』って思っていたところで松商にやられて。しかも自分、最後のバッターやったんです。打たれへんで負けたんが悔しくて、歯がゆくて......」
試合後、寮に戻った澤村は自室で泣いた。野球人生で初めての屈辱だった。
<全国制覇 絶対にする!>
失意をかき消すかのように力強く紙に書き、寮の部屋に貼った。
だが、そんな思いとは裏腹に、調子は一向に上がらない。オープンスタンスから大きく足を上げ、鋭くバットを振り抜く本来の打撃フォームがどこかぎこちない。澤村が目の色を変えてバットを振り込む姿を見続けてきた元谷が証言する。
「『(澤村)通が打てんかっても、オレが打つから任せとけ』とか言ってましたけど、センバツが終わってからの澤村はおかしかった。あいつは器用でバットコントロールもいいし、力もあるから無心でバットを振ればええのに......。あの時期は気負いすぎていたんでしょうね」
大スランプの澤村とは対極に、センバツで絶好調だったがゆえに気負いすぎてしまったのが「背番号1」の和田だった。
仙台育英戦でのノーヒット・ノーランが象徴するように、センバツでは3試合20イニングを投げ、防御率0.45。ストレートの球速も145キロに迫るほどだったこともあり、「欲が出た」と、和田は自らを客観視して分析する。
「センバツが始まった頃は、ある意味、無欲だったんです。それが"ノーヒット・ノーラン男"とか言われるようになったもんで、調子に乗ってしまったんでしょうね。『もっといい球を投げたい』と思うようになってから、だんだん調子が悪くなってしまって」
とくに、和田が追い求めたのがスピードだった。「もっと速い球を投げたい」と、それまでのスリークォーターからオーバースローに近い位置まで腕を上げたことで、投球に狂いが生じるようになってしまった。
完封はおろか、最少失点で抑えることが当然だった背番号「1」が、簡単に失点を許す。センバツで獅子奮迅の活躍を見せたエースは、いつしか自分を見失っていた。
「『どこから投げればいいんだろう?』って思う時期もありました」
澤村と和田の不振が際立っていたが、チームも浮上のきっかけをつかめずにいた。ミーティングで「1番の澤村が出て、2番の元谷が送って、3番の井上、4番の萩原で還すといういつもの得点パターンをもう一度しっかりやろう」と話し合っても、改善どころか試合をするたびに危機感が募る。
センバツ後に行なわれた春季大会準々決勝の上宮戦もそのひとつだ。主将の中村豊、エースの薮田安彦を筆頭に、久保孝之、市原圭、下級生にも筒井壮、西浦克拓、黒田博樹とのちに7人もプロ入りする「タレント軍団」に1−2と惜敗した。
ただ、チームの副キャプテンでもあった井上は、この負けを前向きにとらえていた。
「正直『上宮、強いな、これじゃあ夏は勝てないだろうな』って思ったんです。そういう意味で、ここで負けたことは大きかったと思います」
だからといって、この敗戦によって急にチームがまとまり出したわけではない。勝てないことでフラストレーションがたまり、選手同士の小競り合いも目立つようになっていった。
そんな揉め事の際は、いつもは寡黙な萩原が止めに入ることで収束したという。玉山同様、選手たちから一目置かれていた萩原が同時を述懐する。
「チームの状態は最悪でしたね。『締めないといけない』ってミーティングをやったりしましたけど......練習試合で公立校にもボコボコにやられるくらいでしたから。正直、僕も調子はよくなかったし、そういうものがチームに伝染していったんとちゃうかなって」
そんなチームが目覚めるきっかけとなったのは、勝利ではなく敗戦だった。
夏の大阪大会直前に組まれた東邦高校(愛知)への遠征でのことだ。センバツにも出場した強豪との2連戦で、大阪桐蔭は和田、背尾伊洋の二枚看板を先発させるも、2試合とも圧倒された。試合を観戦していた父兄や高校野球ファンからヤジが飛ぶ。
「おまえら、そんなんで甲子園に行けるとでも思ってんのか!」
選手たちも「やかましいわ、コラっ!」とやり返したが、それほどチーム状態はどん底だった。ただ、この敗戦でチームが変わったことは事実だった。玉山が言う。
「1勝1敗だったらあかんかったしれない。連敗したからよかったんです。いよいよ『これはやばいぞ』となって、初心に戻れたというかね。『一戦必勝で戦っていこう』って」
東邦への遠征からまもなくして行なわれたミーティング。選手たちはようやく覚悟を決めた。
「負けるんやったら1回戦で負けよう。そのほうが夏休み長いし。勝つんやったら優勝しよう。甲子園に行こう!」
言うなれば開き直りだった。そして迎えた大阪大会、またしても予期せぬ事態が待ち構えていた。
つづく
(文中敬称略)