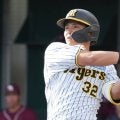近年、移籍マーケットがオープンするたびに、数々の日本人選手がヨーロッパのクラブに移籍することが風物詩と化している。そし…
近年、移籍マーケットがオープンするたびに、数々の日本人選手がヨーロッパのクラブに移籍することが風物詩と化している。そしてこの冬も、その例に漏れることなく、5人の日本人選手が新たにヨーロッパに旅立った。
川崎フロンターレの守田英正がサンタ・クララ(ポルトガル)に、柏レイソルの中村航輔がポルティモネンセ(ポルトガル)に、湘南ベルマーレの齊藤未月がルビン・カザン(ロシア)に、同じく湘南の鈴木冬一がローザンヌ(スイス)に、そして横浜FCの斉藤光毅はロンメル(ベルギー2部)に、それぞれ新天地を求めている(1月26日時点)。

斉藤光毅は19歳でヨーロッパに飛び立った
そのなかで、サンタ・クララの守田はさっそく1月25日に行なわれたリオ・アヴェ戦でデビューを飾ると、試合終了間際に決勝ゴールを決めて勝利に貢献。4−4−2の右ボランチでインパクトのあるパフォーマンスを見せ、新天地で上々の滑り出しを見せた。
そもそも冬の移籍マーケットは、夏と比較すると市場規模は小さい。しかもこのコロナ禍において、新たに5人もの選手をヨーロッパに送り込んだ事実は、あいかわらず移籍マーケットにおける日本人選手の信用度が低くないことの証と言える。守田のデビュー戦での活躍ぶりも、おそらくその裏付けとなってくれるはずだ。
ところで、今回ヨーロッパのクラブに移籍を果たした5人を見てみると、完全移籍かレンタル移籍かは別として、主に2つの傾向に大別されることがわかる。
ひとつは、守田と中村のように、すでにA代表でプレーした経験を持ちながら、まだ常連に定着できていない選手で、かつJ1で一定の実績を積んでいる成熟した選手。年齢的には、20代半ばが主流だ。
昨夏の移籍マーケットでいえば、FC東京から移籍した橋本拳人(ロストフ/ロシア)や室屋成(ハノーファー/ドイツ)らが、こちらにあてはまる。獲得クラブ側から見てみると、即戦力としての補強だ。
そしてもうひとつは、齊藤未月、鈴木、斉藤光毅のように、アンダーカテゴリーの日本代表で国際大会などを経験し、これからA代表を目指す将来有望な若手選手。こちらは、J1での実戦経験が浅い10代後半から20代前半がメインになる。
昨夏にヨーロッパに旅立った遠藤渓太(横浜F・マリノス→ウニオン・ベルリン/ドイツ)や藤本寛也(東京ヴェルディ→ジル・ヴィセンテ/ポルトガル)らも、この類に入る。獲得側からすれば"育てて売る"ことを前提とした、青田買い補強である。
そして、最近の日本人選手のヨーロッパ移籍におけるトレンドになっているのが、前者が占める割合よりも、後者の割合が急増しているという点だ。
たとえば、コロナ禍前の2019年は、とくにその傾向が顕著だった。
主なところでは、FC東京からレアル・マドリード(スペイン)に移籍し、初年度はマジョルカでプレーした久保建英を筆頭に、中山雄太(柏→ズヴォレ/オランダ※冬の移籍)、安部裕葵(鹿島アントラーズ→バルセロナB/スペイン)、安西幸輝(鹿島→ポルティモネンセ/ポルトガル)、三好康児(横浜FM→アントワープ/ベルギー)、菅原由勢(名古屋グランパス→AZ/オランダ)、食野亮太郎(ガンバ大阪→マンチェスター・シティ経由→ハーツ/スコットランド)、中村敬斗(ガンバ大阪→トゥウェンテ/オランダ)、北川航也(清水エスパルス→ラピード・ウィーン)などなど。
バルセロナのカンテラ(下部組織)で育ち、すでにFC東京時代にA代表デビューを飾っていた久保のケースは例外として、それ以外の選手の多くは、いずれもアンダーカテゴリーの代表でプレーし、J1でまだ十分な経験を積んでいない段階でヨーロッパに旅立った"金の卵"たちである。
そういう意味では、いわゆるヨーロッパの5大リーグではなく、セカンドグループとされるリーグの中堅以下のクラブが主な移籍先となるのも、当然と言える。とくに最近は、「ヨーロッパでプレーする選手が増えた割には、トップレベルで活躍する選手が少ない」と言われることが多いが、現在の移籍傾向からすれば何ら不思議なことではない。
生き馬の目を抜くヨーロッパサッカーのピラミッドでステップアップを果たせる金の卵は、ほんのひと握り。これは日本人選手に限った話ではなく、世界各国からヨーロッパに挑戦する若手選手に共通した話なのである。
もちろん、ひと昔前の日本人選手の移籍傾向は違っていた。たとえば、移籍ラッシュとなった2010年W杯以降のザックジャパン時代を振り返るとわかりやすい。
セレッソ大阪のJ2時代にすでに日本代表デビューを飾っていた香川真司(→ドルトムント/ドイツ)はある意味で特殊な例だが、W杯後にヨーロッパに旅立った川島永嗣(川崎→リールセ/ベルギー)、長友佑都(FC東京→チェゼーナ/イタリア)、内田篤人(鹿島→シャルケ/ドイツ)、岡崎慎司(清水→マインツ/ドイツ)、細貝萌(浦和→レバークーゼン経由→アウクスブルク/ドイツ)、槙野智章(サンフレッチェ広島→ケルン/ドイツ)、清武弘嗣(C大阪→ニュルンベルク/ドイツ)などは、いずれもJ1でそれなりの実績を積んだ日本代表選手たち。それが、日本人のヨーロッパ移籍の主流だった。
その移籍先も主要リーグに限られていて、まだセカンドグループのリーグが日本マーケット未開拓の時代である。2011年の夏にバイエルン(ドイツ)に青田買いされたG大阪の宇佐美貴史や、アーセナル(イングランド)からオファーを受けた宮市亮は稀なケースで、当時のマーケットでは、将来有望な日本人の金の卵の信用度はまだ低く、即戦力となり得る成熟した日本人選手こそが獲得ターゲットだった。
それは2010年以前の時代から続いていた傾向であり、柿谷曜一朗(C大阪→バーゼル/スイス)、山口蛍(C大阪→ハノーファー)、武藤嘉紀(FC東京→マインツ)らがヨーロッパに渡ったアギーレジャパン時代以降も変わらなかった。
変化の兆しが見え始めたのは、2018年W杯以降だ。当時西野ジャパンでレギュラーを張っていた選手のうち、Jクラブに所属していたのは昌子源のみ。そのほか、W杯ベスト16入りを果たした日本代表メンバーでヨーロッパを経験していなかったのは、植田直通、遠藤航、中村航輔、東口順昭、大島僚太の5人しかいなかった。
要するに、日本代表クラスはほぼヨーロッパ組で占められていて、マーケット的には、獲得側クラブはその下の世代にターゲットを移さざるを得なくなった、というわけである。そうなると、ピラミッドの上部に位置する主要リーグではなく、セカンドグループ以下のクラブが主な移籍先になるのが、マーケットの法則だ。
たしかに移籍のハードルは低くなった。だが、激しい代表の競争のなかで勝ち上れる確率はどうしても低くなる。おそらくこの傾向は、日本代表がヨーロッパ組で占められている限り、今後も続くだろう。
理想的な例は、シント・トロイデン(ベルギー)からボローニャ(イタリア)にステップアップし、さらに評価を上昇させている冨安健洋だ。その国籍に関係なく、青田買いされた金の卵としては、移籍マーケットにおける成功例に数えられる。それは、シント・トロイデンからシュトゥットガルト(ドイツ)にステップアップした遠藤航にも同じことが言える。
果たして、この冬に旅立った5人の行方はいかに。とりわけ彼らがヨーロッパでステップアップを果たせるかどうかは、今後の日本代表を占ううえでも注目に値する。