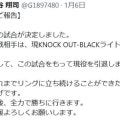川崎フロンターレが天皇杯を制して今季二冠を達成した。圧倒的な強さを誇った川崎を牽引してきたのが、背番号10を背負う大島…
川崎フロンターレが天皇杯を制して今季二冠を達成した。圧倒的な強さを誇った川崎を牽引してきたのが、背番号10を背負う大島僚太だ。中村憲剛が引退し、新たなシーズンを迎える2021年、若きリーダーは何を思うのか。
2020年11月25日、等々力で行なわれたガンバ大阪戦。川崎フロンターレが4点をリードして迎えた、86分のことだった。大島僚太は、自身が交代することがわかると、一瞬、守田英正のほうに目を向けた。
前節の大分トリニータ戦、キャプテンを務める谷口彰悟が退場して出場停止となったことで、この試合では副キャプテンの大島が代わってキャプテンマークを巻いていた。そして交代時にその腕章を託す相手は、もうひとりの副キャプテンである守田の予定だったからだ。

日本最強チームで背番号10を背負う大島僚太
しかし、目が合った瞬間、守田が自分と同じ考えであることがすぐにわかった。大島は交代ゾーンへと歩みを進めると、待ち受ける背番号14の左腕に、ぎこちない手つきでキャプテンマークを巻いた。
中村憲剛は、試合後にこのシーンを「ちょっと、泣きそうになった」と振り返っている。それを聞いた大島は、「僕としてはそんなに深く考えずに、ここは憲剛さんがつけるべきだと思っていました。だから、泣きそうになったと聞いた時は、びっくりしましたね」と、予想外の反応に驚きを隠せなかった。
大島がピッチを退いてから川崎はさらに1点を加え、それからほどなくしてタイムアップの笛が鳴った。2位のG大阪との直接対決を5−0の圧勝でモノにした川崎は、11月25日、ホームの等々力で2年ぶり3度目のリーグ優勝を成し遂げている。
その瞬間をベンチで迎えた大島は、実は複雑な感情を抱いていたという。
「もちろん、うれしかったんですけど、優勝して、等々力で喜ぶ憲剛さんの姿がもう見れなくなると思ったら、急に寂しさが湧いてきて......」
2020年シーズンかぎりで現役を退く中村の偉大さを、あらためて実感した3度目の優勝だった。
史上最速、最多勝点、最多勝利と、圧倒的な強さを示して優勝を成し遂げた2020年の川崎だったが、シーズンが始まる前は期待と不安の入り混じる状況だった。4−3−3の布陣による、新たなスタイルにチャレンジしたからだ。
これまでの川崎のサッカーは、風間八宏監督が築いたパススタイルがベースとなっていた。あとを引き継いだ鬼木達監督がそこに守りのエッセンスを加え、攻守のバランスに優れた勝てるチームへと進化を遂げている。
しかし、2020年は4−3−3の新システムを採用し、より高い位置からボールを奪い、素早く相手ゴールに迫るサッカーを目指した。切り替えの速さやインテンシティの高さが求められるスタイルの導入は、まさに大きなチャレンジだっただろう。
大島自身も当初は、新スタイルの習得に難しさを感じていたという。
「極論すれば、攻撃は点を取る、守備は点を取らせない。そのスタイルを11人がどうやってすり合わせていくか。ある意味でイチから作っていった状況だったので、やりがいがありながらも、同時に難しさも感じていました。
ただ、今までやって来たことを肯定しすぎたら、チームの進化が止まってしまうとも思っていました。だから今までのことを肯定するより、否定するくらいの気持ちで、固定概念を壊しながら1年間を過ごしていたと思います」
2017年、2018年とリーグ連覇を実現し、2019年はルヴァンカップで優勝と、3年連続でタイトルを獲得した川崎は、今まさに黄金時代にあるだろう。それでも、既存のスタイルを捨ててまで新たなサッカーにチャレンジしたのはなぜか。そこには、横浜F・マリノスに完敗を喫した2019年の悔しさがあったからに違いない。
「たしか、あの試合で僕たちのリーグ優勝の可能性が絶たれたんです。相手のスピードやインテンシティの高さがすごくて、ここ数年で一番強いと感じましたし、90分が本当に長く感じられた試合でした。それをホームでやられたのは本当に悔しかったですね。だから、マリノス戦への想いは監督からも感じられていましたし、僕たちもその悔しさを晴らしたいと強く思っていました」
当初は半信半疑だった新スタイルへの順応は、キャンプを終える頃にはすでに手応えとしてあったという。そして大島自身も、新たなポジションであるインサイドハーフで新境地を開拓していく。
これまでプレーしてきたボランチからひとつポジションを上げたことで、「前に出ていく作業というのは常に意識していました」と振り返る。もっとも、高い位置を取ることで、必然としてボールに触る機会は少なくなる。ボールタッチの回数を増やしながらリズムを作っていく大島にとっては、やりづらさもあったはずだ。
「触りたいなと思いますし、関わりたい気持ちはもちろんありますけど、僕が意図して動くことや立ち位置を変えることで、味方がボールを受けられるようになる。動くことで相手をコントロールできるという作業には、楽しさを感じました。
ただ、試合を見返した時に『全然ボールに触れてないな』と思うこともありましたよ(笑)。だから、触った時にどれだけ決定的な仕事がこなせるか。そこは、今後の課題として捉えています」
新たな役割を求められ、新たな発見があった。
2020年は23試合に出場して、キャリアハイに並ぶ3得点をマーク。ハードスケジュールのなかで2019年のように長期離脱がなかったことも含めて、大島は「課題が残ったという意味では満足できないですけど、課題を見つけられるだけのチャレンジをしたという意味では、満足しています」と、自身のパフォーマンスに及第点を与えた。
大島にとっては、進化の1年でもあった。
静岡学園高から川崎に加入した2011年当時を、大島は自身の身体能力や特徴を踏まえ「プロになってから前目でプレーするのをあきらめていた部分もあった」と振り返る。
「でも、2020年は前に絡んでいく作業ができた。10年前では想像できなかったプレーができたという意味では、プロで9年間培ってきたモノが出せたのかな。だから『進化した』と言われれば、そういう言葉も当てはまるのかなと思います」
若いと思われていた大島も、すでに27歳。中堅としてチームを引っ張っていく立場も担った。とりわけ2020年シーズンは、大卒ルーキーの三笘薫をはじめ、若手の台頭が目立った。そんな彼らの活躍に、大島は目を細める。
「若い選手たちの勢いであったり、前への推進力は、今までのフロンターレになかった部分。僕自身の刺激にもなりましたし、サポーターのみなさんも、アグレッシブな姿を楽しめたと思います。なにより、相手が脅威に感じていたんじゃないですかね。彼らの躍動は優勝の要因のひとつだと思うし、頼もしさしかないですね」
そうした若手の台頭がもたらしたのが、チーム内での競争だ。その激しさを物語る出来事が、一度目の10連勝を達成した時期にあったという。
「連戦で選手を入れ替えながら戦ったんですが、最初に10連勝した時は、先発の組み合わせがけっこう同じだったんですよね。だから、一緒に試合に出る選手たちの間では、自分たちがスタメンの時に負けてたまるか、という結束感みたいなものが生まれていました。
正直、ピリついていたところもあったと思います。さすがに自分たちが出てない時に負けろとは思わないですけど、お互いに結果を出して、プレッシャーを与え合う。同じチームなのに、変な関係ではありましたね(笑)」
そんなチームをまとめた鬼木達監督の存在も忘れてはならない。新型コロナの影響で中断したリーグ再開前のエピソードを、大島は明かしてくれた。
「自粛生活明けで選手が集まった時に、監督から『まずは絶対に感染しないようにやっていこう』という話がありました。そして、自分たちがプレーできるのは、医療従事者の方だったり、たくさんの関係者の尽力があるということを忘れてはいけないと。
大変な状況のなか、自分たちが勇気づけられるようなプレーを見せて、絶対にタイトルを取らなければいけない。そう熱く話された時に、本気でタイトルを取りに行く想いがあらためて芽生えましたし、チームの心がひとつになった瞬間でしたね」
絶対に感染しないという指揮官の覚悟は、見た目の変化からも伝わってきたという。
「監督の髪の毛がどんどん伸びていくんですよ。全然、切りに行かないので。選手たちに強制はしなかったですけど、監督は感染のリスクをできるだけ排除しようと必死だったと思います。自身の言葉に責任持って行動されている姿を見て、あらためてついて行きたいと思わせてくれました」
激しいチーム内競争と、鬼木監督が示した男気。コロナ禍における異例のシーズンで、川崎は史上最強と呼ばれるチームにまで上り詰めたのだ。
そしてもうひとつ、川崎優勝の原動力となったのは、やはり中村の存在だろう。
長期離脱から復帰し、突如の引退発表。クラブのレジェンドの現役ラストシーズンを飾りたいという想いは、間違いなく川崎の優勝の要因となった。
もっとも、中村のいない来季の川崎は、どんなチームになるのだろうか。大島は「イメージできないと言えば現実から逃げているようですけど、やっぱり、憲剛さんがいないフロンターレは想像できないですね」と、寂しそうに語る。
それでも、中村がいなくなる事実は変わることはなく、残った選手たちが想いを引き継いでいくほかない。
「そうですね。いなくなったことでチームが沈んでしまえば、悲しむのは憲剛さんだと思いますから。これまでに伊藤宏樹さんだったり、憲剛さんが、フロンターレという大きな船を作ってくれた。それを(小林)悠さんだったり、彰悟くん、僕も含めた生え抜きが束になって、この船をもっと大きくしていかないといけない。僕自身、思い切り責任を背負い込みたい部分も正直ありますし、舵を取るくらいのつもりで、やっていきたい覚悟はあります」
責任を背負い込むと同時に、偉大なる先輩が背負った「14番」を引き継ぎたいという想いは? そんな質問をぶつけると、大島は少し悩んで、こう答えた。
「チームから言われれば、断ることはないと思います。ただ、1年くらいは間を置いてほしいですね(笑)。2016年に10番を打診された時は、すぐにつけたいと思いましたけど、やっぱり14は重すぎますから」
プロ入りから10年、中村からは多くを学び、大きな影響を受けたという。そして、よきお手本がいなくなることで、大島のなかには新たな想いも生まれている。
「憲剛さんに対しては憧れの部分から入って、いろんなことを学ぶことで代表にもつながった。人のプレーを見て、盗むことの重要性を実体験として得られたので、僕自身も伝えていきたい想いがあります」
自身の経験を還元したいのは、地元・静岡の子どもたちだ。
「僕自身、静岡で育てられましたし、静岡のサッカーがまた盛り上がってほしい気持ちもある。チームメイトの長谷川竜也も静岡出身で、一緒に地元で子どもたちに教えることをやろうと考えています。
長谷川を見てドリブルが好きになってくれてもいいし、僕のプレーをマネしようとしてくれてもいい。どう感じるかは子どもたち次第ですけど、やることに意味があると思っています。今まではそういうことをやらないタイプでしたけど、プロになって10年が経ち、新しいことに挑戦してみたい気持ちが湧いてきました」
もちろん、伝えるだけではなく、自身のさらなる成長も求めている。次なるターゲットはしばらく離れている日本代表へ再び戻ることだ。
「なかなか活動できない状況ですけど、この前の試合を観たりすると、やっぱり日本で一番優れている選手たちが集まる環境だと思うので、目指すべきところです。実際にそこでプレーした喜びも経験していますし、リオ五輪で戦った選手たちが多いので、また一緒にプレーしたい想いもある。
選んでほしい? そうですね。結果を出し続ければ呼ばざるを得なくなると思うので、それくらいの選手になることが目標です」
ここ4年で3度の優勝を成し遂げた日本最強チームのナンバー10は、決して現状に満足していない。川崎をさらに強くするために。日本代表で活躍するために。クールな雰囲気とは対照的に、その想いはどこまでも熱かった。