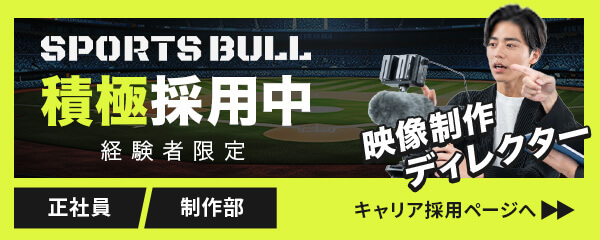負けたら終わり。日本の部活動スポーツの大会で当たり前のように行われているトーナメント大会は、こう形容される。ゆえに、早々に負けてしまうチームは、試合経験を得られない。そんな環境を変えていこうと、日本のバスケットボール界ではリーグ戦導入を促…
負けたら終わり。日本の部活動スポーツの大会で当たり前のように行われているトーナメント大会は、こう形容される。ゆえに、早々に負けてしまうチームは、試合経験を得られない。そんな環境を変えていこうと、日本のバスケットボール界ではリーグ戦導入を促進している。ここでは、そんなリーグ戦構想の現状をレポートする。
現在、国内ではアンダーカテゴリーのリーグ戦構想が進められているのをご存じだろうか。これまで、中学や高校の大会といえばトーナメントが主流だったのだか、それだけでなくリーグ戦の導入を進めているのだ。 端的に言えば、一般的なトーナメントでは1回戦で半数が負けてしまう。つまり勝ち残ったチームは何試合も公式戦を経験できるが、勝ち残れないチームは場合によっては大会の数しか公式戦をできずに終わってしまう。そうした状況は広く普及・育成を考えていけばプラスにはなり得ない。そこでリーグ戦構想が立ち上がったのだが、その背景を日本バスケットボール協会(JBA)技術委員会ユース育成部会においてアンダーカテゴリーのリーグ戦構想を担当する岩崎賢太郎氏(日本スポーツ振興センター/ハイパフォーマンススポーツセンター)は以下のように説明する。
「現在のU18カテゴリーは男女合計約8,000チーム。全体の50%が1回戦で敗退するとすれば、実に4,000チームが1回しか試合ができないシステム─、それがトーナメントです。一方で仮に6チームのリーグ戦であれば、5試合は経験できます。また、指導者にしても、負けたら終わりではなくなるので、5試合を通した選手起用を考えることもでき、より多くのプレーヤーに試合の経験を創出することにつながると思われます。また、たとえ試合に負けても、次の試合に向けて、チームとして個人として修正して臨むチャンスが生まれます」
2016年からスタートしたJBA技術委員会(東野智弥委員長)において、アンダーカテゴリーの育成改革の一つとしてリーグ戦文化の醸成を検討、2017年からは、山本明ユース育成部会長を中心にワーキンググループを立ち上げ、「リーグ戦文化の醸成を通して拮抗した試合環境を創出すること」「プレーヤーに一定試合数を確保すること」という2点を軸に、リーグ戦のシステム設計やガイドラインを作成してきた。それを各都道府県の育成担当者に向けて発信し、意見を聞きながらここまで進めてきたという。 具体的にはまず都道府県内におけるリーグ戦の実施、その次の段階として全国の強豪が集うトップリーグ、また、各ブロックレベルの強豪によるブロックリーグの創設へとつなげ、三層構造のリーグ戦環境を整えることを目指している。

岩崎賢太郎氏

長竹潤氏
そうした中で、すでにリーグ戦を開催している地域がいくつも出てきている。「実はU18カテゴリーでは2019年度は20都府県が実施、今年度は34都府県でリーグ戦が行われる予定でしたが、新型コロナウイルスまん延の影響で、その大部分は中止となってしまいました」と岩崎氏。しかし、昨年の11月~12月に第1回のU18リーグ戦を開催し、その経験、実績から今年度も引き続きリーグ戦の開催を決定したのが群馬県である。
群馬県のU18(高校)の登録数は男子64校、女子55校。参加チームは東西2地区に分かれ、その中で男子は4部(3部がA、Bの2リーグ)、女子が3部にレベル分けしてそれぞれ6チーム前後のリーグを組んだ。群馬県U18カテゴリー部会長の長竹潤氏(高崎商高女子バスケットボール部顧問)は「レベル分けはチームの希望と、これまでの大会での実績を合わせて分けました」と説明する。そしてリーグ戦実施にこぎ着けるまでの課題に「日程の確保」「会場の確保」「審判の確保」の3つを挙げた。 「日程の確保」は、既存大会等との兼ね合いがあることと、昨今言われる教職員の働き方改革への取り組みもある。さらに、学校による3年生の引退時期の違いも考慮し、11月からの日程で、参加は1、2年生に限ることに決めた。もともと、この時期には各地区で交流戦を行ってきており、それを廃止しリーグ戦に当てることにしたのだ。

高校生向けの審判講習
さらに、各リーグの自主運営とすることで、試合日程の調整をリーグ内で行うようにし、基本的には半日、1コートで1、2試合をそれぞれの学校などを会場として行うことを原則とした。これまで練習していた時間、コートで試合を行うことで「会場の確保」を実現し、教職員の負担も増えないことになった。 「審判の確保」は高校生審判を登用した。高校生向けの審判講習を行い、実際のゲームでも審判を務められるようにすることで、不足を補った。
実際に行ってみると、3部、4部といったチームからの感謝の声が多かったという。コーチとなって日が浅いなど、あまりネットワークのないコーチにとっては練習試合を組むこともままならないが、リーグ戦によって試合経験をプレーヤーに提供できるだけでなく、指導者のネットワークを広げることにもなったという。さらに、それぞれのリーグが自主的に運営することで、試合運営のノウハウも蓄積され、それによって、この夏には3年生のための特別リーグ戦を実施することにもつながった。 「リーグ戦なら、スケジュール、対戦チームがあらかじめ決まっています。さらに対戦する2チームが集まるだけなので、コロナ対策もしやすいのです。健康チェックシートなどを付けていただくことで、保護者の観戦も可能になりました」と長竹氏。もちろん、今年度も11月よりリーグ戦を開催している。
群馬県の事例は全国のU18部会の会議でも共有されており、参加チームの感想や課題なども含め、他地域の参考にもなっているはずだ。前述の岩崎氏は「群馬県は60チーム程度ですが、6チーム程度のグループに分け、それぞれのリーグが自主的に運営していくことができれば、もっと登録数の多い地域でも実施は可能ではないでしょうか。実際、チーム数が160を超える規模で、県トップリーグと地域リーグをつなげて実施している兵庫県の例もあります。あとはトップリーグ、ブロックリーグまで創設できれば、より拮抗したゲームを行う環境となるでしょう。海外ではリーグ戦が当たり前ですし、日本でもすでにサッカー界では長期間のリーグ戦環境が整備されています。そうした事例を参考にしながら、バスケットボール界に適したリーグ戦環境が構築できればと思っています。もちろんU18のクラブチームが参加できることも前提に考えていますし、各地域のリーグ戦時期を調整し、昇降格のある三層のリーグ構造を目指します。そのためにも現場の方々の理解を得られるように、しっかりとコミュニケーションを取りながら進めていきたいですね」と話す。
現時点では、まだ試験的に短期間のリーグ戦が実施されている状況であり、さらに長期的なリーグ戦とするためには、既存の大会との関連性や、オフシーズンをどのように設けるか、また、指導者の多くを占める教職員の働き方の問題など、課題は多くありそうだ。それを一つずつクリアしていきながら、日本のアンダーカテゴリーにおいてもリーグ戦文化が築かれていくのだろう。
飯田康二/月刊バスケットボール