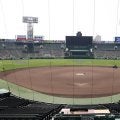「令和に語る、昭和プロ野球の仕事人」 第13回 土井正博・後編 いまやセピア色の世界となりつつある「昭和」──。だが、…

「令和に語る、昭和プロ野球の仕事人」 第13回 土井正博・後編
いまやセピア色の世界となりつつある「昭和」──。だが、令和となった今もけっして色あせることのない、個性あふれる選手たちを忘れずにおきたい。
「昭和プロ野球人」の過去の貴重なインタビュー素材を発掘し、その真髄に迫るシリーズの13人目は、1962年に「18歳の四番打者」として売り出され、過大なプレッシャーを乗り越えて通算465本塁打、2452安打を重ねた土井正博さん。引退後は名コーチとしても名を馳せた土井さんが語る自身の体験は、プロの打撃の繊細さと奥深さを感じさせるものだった。

1976年、太平洋の珍しいユニフォームを着た土井正博(写真=共同通信)
* * *
"名伯楽"としての話をうかがう前に、もう少し現役時代、土井さんが若くして近鉄バファローズの4番に座った頃、打線の主軸として最も大事に考えていたことを聞きたい。
「まず、ゲームに出なアカン、ていう頭がありましたね。1年間、通して出るっていう責任がありましたので。それは4番の宿命で、最低限です。数字としては最低3割。その上で30本、100打点が理想でしょうね」
初めて打率3割を超えた67年以降、土井さんは3年連続で3割、71年から再び3年連続3割と安定した数字を残している。本塁打は20本台が多かったものの、71年は自己最高の40本で113打点。ただ、それでもリーグ1位ではなく、同年は大杉勝男(東映)が41本、門田博光(南海)が120打点でタイトルに輝いた。
また、67年の土井さんは147安打で二度目のリーグ最多安打ながら打率は2位で、首位打者は張本勲(東映)が獲得。近鉄時代は惜しくも打撃三部門のタイトルを逃していたことから、[無冠の帝王]とも呼ばれていた。
「なかなか獲れなかったのは、三部門、どれかひとつはいつでも獲れるわ、抜かせるわ、と安心したんが理由でしょう。だいたいボクはその時期、遊びまくってましたから。それはもう給料はようけもらえますし。エエ車乗りたい、エエもん食いたい、エエ家に住みたい。そういうことでプロに入りましたから。ホンマ、しっちゃかめっちゃかに遊びましたよ。ハッハッハ」
昔気質の野球人ならではの豪快さに触れた気がして、何だかうれしくもあった。ただ、そこまで言い放てるのも、[無冠]で終わらず、太平洋(現・西武)に移籍した75年に初の本塁打王に輝いたからこそではないか、と思う。やっと獲れた、という感慨もあったのではないか。
「なかったですね。ボクはあんまりこだわってなかったのでね。獲れたときはプロに入って15年もたってましたんで、最後のあがき、みたいなね。エッヘッヘ。そういう形じゃなかったかな、と思いますね」
そこまでタイトルへのこだわりがなかった、とは意外だった。その一方で土井さんは78年、パ・リーグ最多タイの6試合連続本塁打という記録をつくり、73年にも5試合連続を記録。日本記録は王貞治の7試合連続だが、それに次ぐものとして誇りにしているのではないか。
「あの、6試合のときは、7試合目に出なかった後、8試合目にまた打ってるんです。1試合、置いてすぐにね。ただ、あのときは怖かったですね。ものすごく見えるんですよ、ボールが。もう縫い目が見えるぐらい。
なんだ、いつでもヒットできるなあ、いう感じですよ。自分のとこへ、スーッと吸い込まれるように見えるわけです。それでボール球ならやめればいいし、エエとこにきて振れば必ずホームランかヒットになるような感覚になってたんですよね」
ゾーンに入る、という状態だろうか。球種もまったく関係ないとしたらすごすぎる。
「ハイ。球種も関係なかったです。だから自分で、今何打ったんかな、と思うぐらい。どう動こうが、もう止まったように見えるんですよね。フーッと止まったように見える。なんぼ速いボールでも。体の調子もエエし、気持ちも余裕がある。何もかも揃ってたんでしょうね。野球をするためにね」
聞くほどに背筋がゾワッとする。土井さんはやや目を細め、握り拳をボールに見立て、ゆっくりと球筋を描いていた。それだけ心身ともに状態がよかったのだと思うけれど、単に「絶好調」という言葉で片付けたくない気もする。ただ、それでも「怖かった」のはなぜなのか。
「そんだけ見えてるヤツが、だんだんだんだん、普通の状態に戻っていくことが怖いんです。普通は、丸っこいボールがくるだけでしょう? そんときは糸まで見えてるわけです。それがゲームやっていくうちにボヤけてきてしまう。いや、ボヤけるほうが普通なんですけど、ついに丸っこいボールに見えて、ウワーッ! と思うたときにはもう、スランプの始まりなんですよ」
絶叫に近い大声に気圧(けお)された。記録を誇りにしているどころか、逆にスランプにつながっていたとは、バッティングの奥深さを感じずにいられない。土井さんは67年に25試合連続安打という記録もつくっているが、そのときも同じように見えて、なおかつ怖かったのだろうか。
「近いものはありました。ただ、やはり、それからガタッときますのでね。見えないでくれー、と祈るときもありましたよ。ハッハッハ。だから、それだけ怖いんです。これはスランプなるんちゃうかな、と自分で思い込んで、暗示かけてしまってるんでしょうね。そうなったときにはもう、打席でしっくりこないんですよ」
土井さんはそう言いながらスッと立ち上がり、スタンスをとって打つ構えをした。
「結局、スランプの手前ぐらいの悪いときっていうのは、こうやって構えたときに、ヒュッと止まって絞れない。あっ、あれっ? あれっ? としっくりこなくなって、そのうちにピッチャーが投げてきたりね。打席で力が入らない。タイミング取っても、どこで取ればいいか、ヒュッと止まるところがないんですよね。ダダダダダーッと流れてしまったり。
それで今度、逆に流れるのを意識して止めようとすると、ググッと締めすぎてるから、打ちにいくときにポンポーンと飛び出してしまったりね。フワーッとしたものがない。そのへんになってきたらもう、それがスランプなんです。頭ん中がこんがらがってしまって、なんでもないボールを速く感じたりしてしまうんですよ」
苦笑しながら腰を下ろす土井さんを見て気づいた。これまで、取材の場で、いい打ち方、よくない打ち方の説明を受けたことはあっても、スランプの状態が再現されるのは初めてだった。その状態を見ていて感じたのは、何か自分で気づかないうちに疲れがたまっていて、本来の体の動きができていないということだ。

取材当時の土井さん。名コーチとしても名を馳せた
「悪いときは微妙に構えが違うんですよね。最初の構えが違うから、そっからひとつずつズレてくる。ボクはこれ、近鉄で若い頃に関根さんに教わったんです」
「関根さん」とは関根潤三。近鉄球団が創立したときのメンバーで、当初は投手として活躍。のちに打者に転向して結果を残した野球人だ。
「関根さんは当時、ベテランでしたけど、単身で来られていたので、若手のいる合宿所で食事してたんです。帰ってくると、必ずガラスの前でバットを構える。サッ、ファッと。違う、違う、これだ、OK、と自分で納得してから食事される。で、ボクは聞いたことあるんです。『バット振らないんですか?』と。
そしたら、『土井よな、オレみたいな小さな体でバット振ってたら、明くる日のゲームに持たない』と。『オレの信念としたら、構えがよかったら、上のボタンがちゃんとかかれば下までスーッといく。構えが悪かったら、ボタンの掛け違いだから、なかなか下まで降りてこない』と言われましてね。ボク、それはずっと頭に残ってました」
当然とは思うが、土井さん自身はバットを振っていたわけだ。
「むちゃむちゃ振ってました。だけど、5〜6年すぎて安定してきたときには、キャンプでは振り込んでも、シーズン中はほとんど構えだけ。さっきも言うたとおり、1年間、ゲームに出る責任がありましたので、自分の体とうまく付き合わなアカンですからね。エエときのビデオを録って、悪いときのビデオと見比べて構えをチェックしました。
スランプの脱出法として、映像を使っていたんです。コーチになったときも、『エエときのビデオは絶対、バッグのなかに入れとけよ』と選手に言ってました。そうすれば、遠征に行っても、おかしいなと思ったときにはスコアラーの人にお願いして、悪いときのビデオを持ってきてもらって見比べられますから」
自分自身を助け、コーチの立場になってからは選手を助けた、土井さんなりのスランプ脱出法。その方法は、ボールが止まって見えるほど好調のときでさえ、自身でスランプの予兆を感じ取っていたからこそ編み出された、といえそうだ。
そして、このスランプ脱出法の原点は、チームの先輩である関根への質問から得られた助言だった。これは若い頃の土井さんが成長していく過程で、「オールスターで先輩方に聞いたら教えてくれた」という話につながっている。
「あっ、そうなんですね。選手は聞きたいことは口で聞いてね、やると。遠慮してたらスタープレーヤーになれないし。今は、こんなこと聞いたら恥ずかしいんか、っていう若い人が多いんですよね。プロ野球選手がこんなこと聞いたらかっこ悪いんやないか、って。
だけど、恥をかかなね、うまくならない。恥をかいたら、その恥の倍はうれしいことが出てくるんですよ。人間、うれしいことがないと前に進歩していかないですから」
土井さん自身、目で見て、口で聞いて、恥をかいてうまくなっていった方なのだった。
「そうせな仕方なかったですから。17でプロに入って、別当(薫)さんにつくってもらってね。だけど、コーチになってもそれはおんなしなんです。選手に聞かれて、ボクがわからんかったら、例えば、名球会の知ってる人のなかで聞いて、答えを出してあげるとか。
前にね、松井稼頭央をスイッチにしたときに、スイッチで成功した人に会わして、どうするかと。あとは左バッターの人ですね。右のボクではわからないところもありますからね。会わして、教えたってくれ、と。だいぶ、皆さんにお世話になりましたよ」
そういう背景があったとは知らなかった。たとえ指導者となっても、恥をかいて聞きに行く姿勢でいることがいかに大事か。立場を考えると簡単にはいかない、と思えるが、選手のときから聞きに行っていた土井さんには難しくなかったのだ。
「ボクはそうやって選手に的確な答えを出すことが大事と思ってます。で、松井稼頭央の場合は、左で当てて走るのか、振るのか、『後はもうキミが選択することだぞ』と言ったら、『振ります』って言ったんですね。
それでエエほうに向いてくれて、彼自身の選択も素晴らしかったし、自分に合うヤツを持っている人と出会えたのもよかったんですね。これはもう、中田君にしても、今度、プロに来たときにね、いい出会いができれば」
不意に、中田翔の名前が再び出てきた。今こそ、最初に聞いた中田の「壁」について聞いておきたい。
「まず、彼は清原(和博)と一緒で、手の伸びてくる力いうのはすごいんです。ちょっと外寄りのボールは手が伸びて、グワーンととらえたボールは場外でも持っていけるだけの力はあります。で、こういうバッターにひとつの試練が来るとしたら、去年、甲子園で斎藤君にやられたわけでしょう? 彼みたいなピッチャー、形的にプロに何人いてるか、っていうことなんです」
早稲田実の斎藤祐樹との対戦。中田のバットが空を切るシーンが思い浮かんだ。
「あのとき、高めのボールでやられましたよね。で、インサイドでやられましたよね。それはまるっきり、清原とそっくりなんです」
イメージだけではなく、長所にも「壁」にも、清原と中田に通じるものがあったとは......。
「で、それをどう、うまくやるかっていうと、あんまり触りすぎないことです。この人を育てなアカン、と必死になればなるほど、彼に負担かかりますのでね。誰か1人、ちゃんと付いてあげて、ゆっくりつくっていくほうが、スッと出てくる道があるんじゃないかと思います。ただでさえ、マスコミから『新人王、新人王』って騒がれますからね。清原のときもそうでしたし」
近鉄、太平洋、クラウン、西武で21年間プレーした土井さんは1981年限りで現役を引退。85年、二軍打撃コーチとして西武に復帰すると、翌86年、清原の入団とともに一軍打撃コーチに昇格して苦労している。マスコミが清原に対して「新人王」と書き立てるなか、当初、土井さん自身も「新人王を獲らせたい」と考えていたからだ。
「ただ、あのときは球団の方から『焦ることは何もない』と言われましてね。やっぱり、清原にしても、中田君にしても、もう登竜門は持ってるわけですから。キャンプから一軍で連れてく、という登竜門をね。ということは、監督なり、コーチなり、エエ指導者に巡り合えるか。それがいちばんのポイントでしょう、中田君の」
土井さん自身、別当監督と巡り合い、[18歳の四番打者]として抜擢され、つくられていなかったら、その後の野球人生はなかった──。そう言っても過言ではないだろう。
「そうなんです。そのへんの人生の違い、人間の運いうのは、どこにね、つながっていくか。とにかく、素晴らしい人は素晴らしいように育ってもらわないと。ね?」
(2007年10月11日・取材)