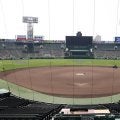親善試合について語る時、推しはかりたくなるのは相手の勝ち気だ。日本の親善試合といえばホーム戦。9割方、スタジアムが日本…
親善試合について語る時、推しはかりたくなるのは相手の勝ち気だ。日本の親善試合といえばホーム戦。9割方、スタジアムが日本人の観衆で埋まる中で行なわれる。おのずと絶対に負けられない戦いになる。敗戦や失敗を怖がる日本人気質がこれに拍車を掛ける。
「勝利にこだわりながら......」とは森保一監督の口癖だが、「ながら......」と言う勝利と、戦術や新戦力を試すなどの要素は、8対2ぐらいの関係にある。勝ち気満々で戦う日本に対し、相手は必ずしもそうではない。5対5ぐらいの感覚で臨んでくる。親善試合は、このカルチャーギャップと言うべく温度差に、気を配りながら観戦する必要がある。厳しく言ってしまえば、親善試合で日本ほど喜べない勝利を重ねている国も珍しい。
温度差が一番現れやすいのがメンバー交代だ。何人をどのタイミングで代えるか。交代は必ずしも戦力アップを意味しない。常時、新陳代謝が求められる代表チームの場合はとりわけ、テストの意味合いが多分に含まれる。
日本対カメルーン戦の交代枠は6人で、森保監督が4人を代えたのに対し、カメルーンのトニ・コンセイソン監督は5人を代えた。カメルーンのメンバーは、PCR検査でコロナ陽性だった選手が不在のため全部で18人。コンセイソン監督は控えGKと1人のフィールドプレーヤー以外、16人をピッチに送り込んだ。
一方、森保監督は交代枠を2枚余して試合を終えた。2人の控えGK以外にも、6人のフィールドプレーヤーが出場機会を狙い、アップをくり返していたにもかかわらず、そのまま、試合を終えた。

カメルーンに0-0で引き分けた日本代表。ドリブルで攻め込む久保建英
後半30分を過ぎた頃から、試合は日本ペースに移行した。後半39分には左ウイングの位置でボールを受けた交代出場の久保建英がタテ突破を決め、センタリング。大迫勇也に惜しくも合わず......というチャンスを作った。終了間際には同じく交代出場で右ウイングバックの位置に入った伊東純也が、右サイドを突破。ペナルティエリア手前で反則を受けると、そのFKを、キッカーの久保がGKを泳がす際どいシュートを見舞った。
終わり方がよかったのは日本。0-0という結果に悲観的になる人は少ないかもしれない。だが、森保監督が交代枠をさらに2枚切っていたらどうだっただろうか。日本はペースを握ることができていただろうか。
いわゆるテスト色の強い交代は、後半41分に投入した菅原由勢(原口元気と交代)のみだった。勝ちたかったから、ではないだろうか。勝ち気がテストを大きく上回った結果ではないだろうか。
これまで、森保監督はこのパターンをくり返してきた。敗戦を恐れるあまり交代が遅れる。あるいは、交代枠を使い切れないという好ましくない采配をくり返してきた。今年1月に行なわれた直近の試合=アジアU-23選手権の初戦、対サウジアラビア戦などはその典型的な例になる。森保監督への信頼感が大きく揺らいだ瞬間でもあった。その采配は今回のカメルーン戦、13日に行なわれるコートジボワール戦の、一番の見どころといっても過言ではなかった。
親善試合の後半は、両監督が交代カードを切り合う場となるため、交代枠3人で行なわれる公式戦等に比べ、内容は慌ただしくなる。落ち着かない展開になる。どちらかと言えば、点が入りやすい状況になる。そうした中で、変に勝負にこだわる監督もいたりするので、親善試合の後半は何かを語る場として適さないのだ。真実が宿るのは前半の戦いになる。
カメルーン戦の前半。日本は4-2-3-1の布陣で高い位置からプレスを掛けにいった。前のアタッカー4人が、カメルーンのディフェンダーに忠実にプレッシャーを掛ける。3回に1回程度、それがうまくいった。しばしば高い位置で奪還することに成功した。
ボールを同じラインの高さで、同じ回数奪い合えば、ボール支配率は50対50に近づく。ボール支配率は、ボール奪取と密接な関係にある。とすれば、日本の支配率はもっと高くていいはずだった。だが、その関係はカメルーンの57対43だった。
カメルーンは、3回に2回程度、日本のプレスをかいくぐるとボールをよく繋いだ。4-3-3の特性を活かし、両サイドを広く使ってパスを展開した。パスを繋ぐサッカーが好きな日本を、その点で上回った。
日本はせっかくボールを奪っても、すぐに奪い返されてしまった。展開がまったくできていなかった。パスコースが多いはずの4-2-3-1の特徴を出せずじまいだった。
出たとこ勝負。真ん中付近の難しいエリアで難しいパス交換をし、あっさり奪われるケースが目立った。パスが有効に繋がる美しいサッカーはどちらかだったかと言えば、カメルーンだった。
この試合の一番の誤算はここにある。「連係・連動」という言葉を好んで口にする森保監督だが、ガチンコ勝負となった前半は、それがまるでできなかった。
原口元気、堂安律はサイドでフリーな状態でボールをもらえず、その背後で構えるサイドバックとのコンビネーションを図る機会も少なかった。エース格の南野拓実と大迫勇也にしても、何かをしたというわけではなかった。攻撃はサッパリだった。中でもひ弱に見えたのが柴崎岳と中山雄太で構成する中盤の真ん中だ。相手の勢いに飲まれていたという印象が強い。
先述のとおり、ラスト10分で流れは日本に移ったが、それ以外の時間で決定的なチャンスはもちろん、惜しいチャンスさえほとんど作れなかった。重く見るべき事態だと思う。展開力のないサッカー。選手の感覚に任せた、出たとこ勝負のサッカーでは、W杯ベスト8は夢の夢。交代選手(久保、伊東)の活躍で、終わり方がよかったように見えたカメルーン戦だが、そちらに目を奪われすぎると本質を見誤る。見るべきは前半の戦いぶりにあり、なのだ。