今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、春夏の甲子園大会が中止となった。なかでも夏の甲子園はこれまで数々の名勝負…
今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、春夏の甲子園大会が中止となった。なかでも夏の甲子園はこれまで数々の名勝負が繰り広げられ、高校野球ファンを虜にしてきただけに残念でならなかった。
そんななか、20年前に打ち立てられ、いまだに破られていない記録がある。2000年夏に智弁和歌山が樹立した1大会通算100安打と13本塁打だ。この記録に近づいたチームはいくつかあったが、追い抜くことはできなかった。

圧倒的な攻撃力で2000年夏の甲子園を制した智弁和歌山ナイン
以来、智弁和歌山には「強打」「豪打」のフレーズが付いてまわり、全国の高校を震え上がらせた。当時のメンバーで「5番・捕手」として活躍した後藤仁は、今でもあの夏のことを鮮明に記憶している。
「あの時、自分たちはとにかくよく打ったというイメージが強いと思うんですけど、1回戦(新発田農/新潟)はバントがひとつも決まらなくて......翌日はバント練習ばかりしていたんですよ(笑)」
後藤はチーム本塁打13本のうち3本塁打を放った右の強打者だ。同志社大でもレギュラーとして活躍し、現在は地元・和歌山で医療機器を扱う会社の営業マンとして日々奔走している。
当時の夏の甲子園は、まず3回戦までの組み合わせが決まり、準々決勝以降はその都度、抽選によって対戦相手を決めていたのだが、最初の組み合わせが決まった瞬間、後藤は言葉を失った。
「初戦の新発田農に勝ったら、2回戦が中京大中京(愛知)。さらに勝てば、3回戦はPL学園(大阪)と明徳義塾(高知)の勝者でした。組み合わせを見て、頭の中が真っ白になりました」
それでも智弁和歌山にとっては、絶対に負けられない理由があった。
じつは、前年秋の近畿大会で智弁和歌山は東洋大姫路(兵庫)に初戦敗退を喫してしまった。翌年春に開催されるセンバツ大会の選考も兼ねていたが、普通に考えれば出場は"絶望"のはずだった。
だが、旧チームの主力メンバーが多く残ったこと、直前に出場した熊本国体が台風によりハードなスケジュールを強いられたことも考慮され、近畿大会で1勝もしていないにも関わらず、センバツに選出されたのだ。
そのセンバツ大会で準優勝を果たしたものの、チーム内には「このままでは満足できない」という空気が支配していた。
「センバツでは早く負けて『ほらな』って言われるのが嫌で......もし今みたいなネット社会だったら、相当叩かれていたかもしれないですね。準優勝できたのはよかったですが、やっぱり優勝したかった。でも、夏に向けてプレッシャーはありませんでした。『これだけやれば甲子園に行ける、甲子園で勝てる』という練習を1年の時からやっていましたから」
当時の智弁和歌山は1学年10人の少数精鋭(現在は12人)。和歌山を中心に関西圏の有望な選手が集まり、入学直後から徹底的に鍛え上げられた。
「入学すると『こういうメニューをやるから』と練習内容を伝えられるのですが、ほとんどがランメニュー。めちゃくちゃきつくて、リタイアして途中で帰った同級生もいました」
今でこそ"猛練習"は異論を唱えられる時代となったが、当時は鍛えてなんぼという風潮が強かった。そこで鍛えられた精神力は、当時の智弁和歌山ナインにとって大きな武器となっていた。
3年夏の甲子園でも、それは遺憾なく発揮された。2回戦の中京大中京戦では、7点リードするも徐々に追い上げられ1点差まで詰め寄られるが、最後まで逆転を許すことはなかった。
そして3回戦の相手はPL学園(大阪)。さすがに「負けるならここやろうと思っていました」(後藤)と語ったように、智弁和歌山ナインにとって間違いなく格上の相手だった。
ところが、序盤から智弁和歌山打線がPLの2年生右腕・朝井秀樹(元巨人)に襲いかかり、5回表が終わった時点で9対1。思わぬ大差に5万人を超える観客からはどよめきが起こっていた。
ただ、後藤は点差があることを感じていなかった。
「PL戦は何点取っても安心できなかったですね。相手はみんな野球がうまくて、走塁もそつがない。打ちそうな雰囲気がありますし、リードしていても怖かったですね。智弁和歌山は打つけど、野球が大味でしたから(笑)」
終盤、PLの反撃にあうも11対7で破った。この勝利で自信を得たのもつかの間、準々決勝の相手は柳川(福岡)に決まった。同じ年のセンバツでは同じく準々決勝で対戦し、その時は1対0で勝利したが、エース香月良太(元巨人)は大会ナンバーワン右腕と評されるなど、優勝候補の一角に挙げられていた難敵だ。
試合はリベンジに燃える柳川のペースで進み、7回を終えて2対6。だが8回裏、武内晋一(元ヤクルト)のソロで1点を返すと、一死一、二塁で6番・山野純平が起死回生の3ランを放ち同点に追いつく。後藤がその時を振り返る。
「山野が打った瞬間、球場内がシーンとなったんです。打球がスタンドに入った瞬間、爆発するような歓声が響いて......その時、『これが甲子園か』って鳥肌が立ったのを今でも覚えています」
試合は延長に入り迎えた11回裏。智弁和歌山は二死一、二塁から後藤がサヨナラ打を放ち、激戦に終止符を打った。
「最近の高校生は、速いピッチャーなら145キロを軽く超えてきますよね。自分たちの頃は、140キロに達していれば速いなというレベルでした。それでも香月は自分のなかでは一番のピッチャーでした。智弁和歌山の選手は、6月の猛練習のおかげで夏の甲子園の頃になると疲労が取れてベストコンディションになり、どんな投手でも打てるようになるんです。でも香月は、低いと自信を持って見逃した球もストライクゾーンに入っている。それだけ伸びがありました。高校生であれだけの球を投げられる投手はほとんどいないと思います」
準決勝で光星学院(青森)を破った智弁和歌山は春夏連続して決勝に進出。夏の頂点を争う相手となったのは東海大浦安(千葉)だった。センバツの決勝では東海大相模(神奈川)に敗れていたため、同じユニフォームの学校には負けられないと、高嶋仁監督をはじめ、全員が意気込んでいた。
だが、これまでの5試合はリードすれば一度も勝ち越されることはなかったが、決勝は取ったら取り返される展開を強いられた。「流れとしては一番苦しかった」(後藤)と振り返ったが、主将の堤野健太郎の2本の本塁打を含む20安打11得点と打ち勝ち、全国制覇を成し遂げた。

強肩・強打の捕手として智弁和歌山の全国制覇に貢献した後藤仁氏
それにしても、なぜここまで打ち勝つことができたのか。ストレートな問いに後藤は「時代が違うから仕方ないのですが」と前置きしたうえでこう語った。
「根性論というのがまだ残っていた時代だったと思います。『自分たちは絶対に負けない』『打ち負けない』っていう自負がありました。センバツのこともあったし、夏こそはという気持ちが強かった。だから、猛練習にも耐えられることができた。あの夏の記録が残っているおかげで、今でもこうやって思い出してもらえる。ありがたいです」
甲子園で通算68勝を挙げた高嶋監督は2018年の夏を最後に勇退し、中谷仁が監督に就任した。今も"強打の智弁和歌山"は健在だが、投手は昨年の池田陽佑(ようすけ/現・立教大)に続き、この夏も小林樹斗が150キロをマークした。
「自分たちの時にそれだけのピッチャーがいたら......とは思いますが、もしいたらあそこまで打てていないと思います。智弁和歌山の投手がいいって、ある意味"らしくない"ですよね(笑)。高嶋先生から中谷さんに監督が代わり、野球のスタイルも変わった。また新しい智弁和歌山になっていくと思うと、OBとしても楽しみです」
ちなみに、いまやすっかり智弁和歌山の名物応援曲となっている『ジョック・ロック』は2000年春から演奏されることになったのだが、同じくよく演奏される『サンバ・デ・ジャネイロ』は2000年の夏から使用されている。選曲にあたり、こんなエピソードがあったという。
「じつは僕らのクラスに応援団のやつがいて、新曲を披露するのにいい曲はないかという話になったんです。その時、僕が海外の名曲を集めたCDアルバムを持っていて、そのなかに『サンバ・デ・ジャネイロ』が入っていたんです。それで自分が『これがいいんじゃないか』と言って決まったんです」
記録にも記憶にも残った2000年の夏。あれから20年の時を経て、智弁和歌山はどんな伝統を紡いでいくのだろうか。




































































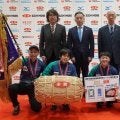



![アルカラス、難敵ポールを退け3年連続の8強進出!史上最年少の生涯グランドスラムに邁進[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012516260245513700.jpg)



