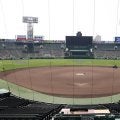球史に残るコンビ「アライバ」対談 後編前編:不仲説もあった2人の関係性は?>> 初の共著『アライバの鉄則』(廣済堂出版)…
球史に残るコンビ「アライバ」対談 後編
前編:不仲説もあった2人の関係性は?>>
初の共著『アライバの鉄則』(廣済堂出版)を刊行した荒木雅博(中日一軍内野守備・走塁コーチ)と井端弘和(侍ジャパン内野守備・走塁コーチ)。同書に収録された「アライバ対談」の中で語られた、攻守でのコンビプレーの裏にあった秘話をお届けする。

攻守で息の合ったプレーを見せた井端弘和(左)と荒木雅博(右)photo by Sankei Visual
今でも「アライバプレー」と呼ばれる二遊間のコンビプレーがある。
センターに抜けようかというゴロをセカンドが逆シングルキャッチし、そのままカバーに入ったショートにグラブトス。ボールを受け取ったショートがファーストに送球し、アウトを奪うというものだ。
この一連のプレーは荒木、井端による「アライバコンビ」の代名詞になった。多くの球児がこのプレーを模倣しようと、練習に励んだ。
アライバそろっての対談では、やはり「アライバプレー」の話題が出た。荒木の記憶では、試合中に二遊間のゴロを捕った際、井端の声が聞こえたのがきっかけだったという。
「とっさに井端さんにトスをして、アウトにできた。それがスタートだったのかなと。もしかしたら、井端さんはもっと前からあの位置まで走り込んで、僕に声をかけてくれていたのかもしれないけど」
その荒木の独白を受けて、井端は「ヒントになったのはダブルプレーなんだよね」と明かした。
「(セカンドが)二遊間のゴロを目いっぱいの体勢で捕ってしまうと、一塁に投げるための力が残っていない。でも、ダブルプレーの時はグラブトスをすればゲッツーを取れることもある。俺が荒木の近くにいれば、アウトになる可能性がちょっとは高くなるんじゃないか、とね。数パーセントでもアウトにできる可能性が上がるなら、やってみようと思ったんだ」
その言葉を受けて、荒木はヒザを叩いて「そう、それがすごいんです!」と熱弁した。
「井端さんは、僕がトスしないときも近くまで走り込んで、準備してくれていましたからね」
グローブをはめて守備について語る
「アライバ」photo by Ishikawa Kohzo
井端は「ヒットは捕らない」という信条を持っていた。誤解を招きかねない言葉だが、若手時代に当時のエース・今中慎二からかけられた言葉がきっかけだった。
「三遊間のゴロを横っ飛びで止めたんですけど、送球が間に合わずにアウトにできなかったんです。今中さんに謝ると、『お前、ケガするぞ。あんな打球止めたって、セーフなんだからな』と言われました。その言葉を聞いて、プロ野球というものを少し理解できたような気がしたんです」
それ以来、ヒット性の打球は無理して追わないようになっていた井端だが、二遊間のゴロを捕る荒木の近くにはいつも走り込んでいた。それは、アウトにできる可能性を感じていたからだ。
そんな労力をかけながらも、井端は「あのプレーの選択権は荒木にある」と語る。
「捕った時点で荒木に力が残っているかどうかは、俺にはわからないことだから」
その言葉を受けて、荒木は首を横に振ってこう返すのだった。
「僕からすると、選択権は僕にあるように見えて、実は井端さんの手のひらの上でうま〜く転がされていた感覚でしたよ」
二遊間のコンビとして2004年から2009年まで6年連続でゴールデングラブ賞を受賞したアライバコンビだが、攻撃面でも1番・荒木、2番・井端のコンビを組んでいた。
当時はアイコンタクトでヒットエンドランを決めるという離れ業を演じていた。アライバの攻撃面に関するやりとりをそのままお届けしてみよう。
荒木「僕、いつも取材で『井端さんが次の打順にいるから思い切っていけた』という話をしていたんです。ご存じの通り、僕は初球から狙い球が来れば打ちにいくタイプで、初球であっけなく凡退すると『先輩、頼みます』と祈るしかなかったですから」
井端「2人で足して、ちょうどいい感じを保っていればいいだけの話。俺はずっとそう思っていた。荒木と俺のふたりで調和がとれていればいいと。逆に荒木が粘ってくれて、2番の俺がいきやすい環境を作ってくれたこともあったし」
荒木「そうですか」
井端「そういう時は、『たまにはこっちも初球をかまさないと』と、初球から攻めていけた。もしくは荒木が初球を打ったあとでも、相手バッテリーが『井端は初球を見逃すだろう』と簡単に投げてきたボールを狙って打つこともあったし」
荒木「そうでしたね。ヒットを打つことが一番のダメージになりますからね」
井端「理想を言えば、2人で20~30球を投げさせて、どちらも塁に出て、先発ピッチャーを5回持たずしてマウンドから引きずり降ろせるならそれがいい。すべての試合でそういうわけにはいかないけど、『2人の間でうまく調和がとれていればいいのかな』と思ってやってきた」
キーワードは「調和」だった。一時、「1番・井端、2番・荒木」の組み合わせを試された時期もあったが、うまく噛み合わなかった。荒木がアグレッシブに打ちにいき、井端は調和を取りつつクリーンアップにつなぐ。こう書くと井端への負担が大きいように感じられるが、井端は「不満はなかった」と語る。
「2番は制約が多くて窮屈なバッティングをすることも多かったけど、不満はなかった。進塁打で打率が下がっても、逆にヒットエンドランを成功させて打率が上がることだってある。俺のような打者が全打席、普通に打っていたら、高打率は残せなかったかもしれないから」
一方で、荒木は「井端さんに盗塁成功率を上げてもらった」感覚があるという。
「盗塁のスタートをうまく切れなくて、『やばい、切っちゃった』というときに井端さんがファウルにしてくれたことが何度もありましたから。『なんでこんなことができるんだろう?』と、あの技術はすごいと思っていました」
対談中、何度も震える瞬間があった。赤星憲広(元・阪神)に対してアライバ両者とも「天敵」と意識していた話題が出た時。「守りにくかった投手」というお題でアライバとも意外な投手の名前で一致した時。井端は塁上の荒木の顔を見ただけで、盗塁するか否かを読み取れたという逸話が語られた時。中日の現状についてアライバが共通の問題意識を抱いていることが判明した時......。
他にも、アライバは今の野球界にとって貴重な金言を次々に発していった。2人の言葉のやりとりは、まるでアライバプレーそのものを見ているようだった。
なぜアライバコンビは最強の二遊間であり続けられたのか。その答えを追求していけば、野球というスポーツをますます奥深く堪能できるに違いない。
(敬称略)