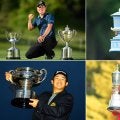あまりに惜しい、控え選手だった。 センターを守る背番号15が力強く左腕を振ると、ボールが低い軌道で伸びていく。シー…
あまりに惜しい、控え選手だった。
センターを守る背番号15が力強く左腕を振ると、ボールが低い軌道で伸びていく。シートノックとはいえ、このスローイング能力は全国屈指に違いない。少なくともこの選手が登場した春のセンバツで、ここまで鮮烈な送球にはお目にかからなかった。
──大阪桐蔭じゃなかったなら……。
そう思わずにはいられなかった。せっかくすばらしい能力を持っていても、腕自慢が集まる大阪桐蔭では控えクラスなのだ。
さらに驚くべきことに、この選手は春のセンバツの大会公式パンフレットに名前すら載っていなかった。大会直前のメンバー変更で甲子園ベンチに滑り込んだのだ。
私が大阪桐蔭の控えセンターを目撃して、4年の時間が過ぎた。そして、大学に進んだこの選手は今や、ドラフト候補の仲間入りをしている。

昨年秋のリーグ戦で5本塁打を放ち、阪神大学リーグの新記録を樹立した天理大・大石航輝
名前を大石航輝(こうき)という。
「なんか景色がちゃう感じっすね。高校時代は野球以外のことも考えていたんです。将来は指導者になるとか、トレーナーとか整体関係とか、野球関係の仕事じゃなくてもいい就職先につきたいとか。でも、今は野球中心で考えています」
天理大に進んだ大石は昨年秋のリーグ戦で5本塁打を放ち、阪神大学リーグの新記録を樹立した。その後、12月には愛媛県松山市で開かれた大学日本代表候補強化合宿にも招集されている。
密かに大石の動向を気にしていた私は、「いったい何が起きたのか?」と不思議に思っていた。というのも、その前年に天理大が大学選手権に出場した際、2年生の大石は「9番・ライト」として出場した。あの控えセンターが大学でレギュラーになったのか……と感慨を覚えたものの、その時点ではドラフト候補と呼べる次元ではなかった。
急速な進化の裏に何があったのか。コロナ禍で春のリーグ戦が中止になり、大学最後のリーグ戦に向けて調整する大石にリモート取材を申し込んだ。
大石は兵庫県西脇市の黒田庄という地域で生まれ育った。
「後ろに山、前に川、横に田んぼ……。緑があって、自然豊かなド田舎ですね(笑)。広場がぎょうさんあったので、学校が終わったらずっと外で遊んでいました。街灯がなくて真っ暗になるので、夜は家におったっすけど」
三木シニアでプレーした中学時代のある日、練習中にチームの会長が血相を変えて「大石、どこや~!」と叫んだ。会長のもとへ向かうと、思いがけないことを告げられた。
「桐蔭がOKやぞ。行くやろう?」
練習を見にきた大阪桐蔭の西谷浩一監督が、大石に興味を示したという。当時の大石はエースで4番を打ち、最速135キロの注目選手だった。だが、大石は反射的に「いや……」と言い淀んだ。素気ない反応に、会長は「何を悩むねん!」と返す。事の重大性を自覚していない大石に、焦れたのだろう。
大阪桐蔭は毎年約20名の野球部員を迎え入れる。だが、いくら本人が入りたいと希望しても、年間数十名の中学3年生が入部を断られている。大阪桐蔭の野球部に入るということは、それだけハードルが高いのだ。
しかし、あまり高校野球を見ていなかった大石にとって、大阪桐蔭は「藤浪(晋太郎/阪神)さんと森(友哉/西武)さんがいたチーム」くらいの認識しかなかった。さらに自分の力がエリート校で通用するとも思えなかった。それでも悩んだ末に、大石は大阪桐蔭に入学する道を選ぶ。
「桐蔭は全国トップクラスの20人が厳選されて入ってくる。たとえレギュラーになれなくても、人生の経験として生きてくるやろう」
だが、入学して早々に、大石は現実を思い知らされる。
「『俺は野球がうまいから桐蔭に来たんや』みたいなやつばかりで、うわ、やべぇところに来たな……と」
高山優希(現・日本ハム)ら同期には好左腕が複数おり、大石は入学早々に「持ってるものが違う」と悟る。左肩を痛めたこともあり、すぐ外野手に転向した。
1年生部員は学校から生駒山のグラウンドまで、ランニングして通わなければならない。「ほぼ登山」という練習前のトレイルランで、大石はいつも最下位だった。
「最初は生きていくので精いっぱいでした」
肩痛が癒え、ようやく投げられるようになった春には、新しい1年生が入ってくる。徳山壮磨(現・早稲田大)ら、のちに2017年春のセンバツを制覇する学年である。うんざりしても不思議ではないが、大石は「逆に楽しみだった」と振り返る。
「年下でも『どんなやつ、おんねやろ?』と、ワクワクしてしまうんです。本当はダメなんでしょうけどね」
2年秋からベンチ入りし、3年春のセンバツには前述の通り外野の控えで出場。だが、3年夏は大阪府大会のベンチ入りを逃した。代わりにベンチ入りしたのは、1年生の藤原恭大(現・ロッテ)、根尾昂(現・中日)だった。
「バッティングの調子がどん底まで落ちてしまって、焦ってすべて悪い方向にいってしまいました。藤原と根尾はほんまビックリの連発でした。とくに根尾はバッティングピッチャーで投げたんですけど、初球に打った打球が『センターライナーかな』と思ったらそのままホームラン。恐ろしいな……と思いましたね」
ベンチ入りを逃した大石は、自ら「応援団長」を買って出る。1年生を指揮して応援練習に精を出し、毎日バッティングピッチャーを務めてチームをサポートした。不満を抱いたこと、腐ったことは一度もないという。
「どの選手もチャンスはたくさんもらっていて、結果を出せなかったのは自分のせいなので。桐蔭に腐るようなやつは絶対にいません」
大阪大会は3回戦で関大北陽に1対2で敗れ、大石は高校最後の夏をスタンドで終えた。
高校卒業後、天理大に進学した大石だが、活躍するまでには時間を要した。2年時に大学選手権に出場した際も、リーグ戦で常時出場できたわけではない。大石に「レギュラーを奪ったと実感した時期は?」と尋ねると、こんな答えが返ってきた。
「去年(2019年)の秋も最初の2節は代打とか途中交代やったので、まだフルシーズン出たことがないんです。だからレギュラーと言っていいのか……」
3節目の大阪産業大との2回戦で、大石は満塁弾を含む2本塁打5打点と大暴れする。この試合を含め、残り5試合で22打数10安打、打率.455、5本塁打、15打点と神がかった猛打を見せたのだった。
いったい何が変わったのか? 大石に聞くと、「考え方と練習の取り組み方ですかね」という答えが返ってきた。
いかにも平凡な回答に思えたため、もう少し掘り下げようと「考え方とは、具体的にどういうことですか?」と聞いてみた。取材前の下調べでは「ウエイトトレーニングでパワーがついた」という要因が報じられていただけに、そんな回答が返ってくると予想していた。だが、なぜか言いにくそうな態度を見せた大石は「これ言ったら、ふざけてると思われるかもしれないんですけど……」と前置きをしてこう続けた。
「パワプロってあるじゃないですか」
── パワプロ? ゲームの?
「はい。昔は野球ゲームをあまりやってなかったんですけど、大学に入って寮でチームメートとパワプロで対戦するようになったんです。それでやっていくうちに、現実の野球もうまくなっていきました」
── ?
たしかに「冗談なのかな?」と思ってしまった。「パワプロ」とは、大人気ゲームシリーズ『実況パワフルプロ野球』のこと。だが、本人の大真面目な説明を聞くと、決して悪ふざけではないことが伝わってきた。
「現実の世界とパワプロの違いって、ストライクゾーンを立体でとらえるか、平面でとらえるかだと思うんです。パワプロでは9分割のストライクゾーンにカーソルを合わせて、タイミングよく打ったら飛んでいきますけど、現実世界で打とうと思ったら平面のポイントでは打てないじゃないですか。でも、僕の場合は今まで難しく考えすぎていたので、『ゲームみたいに平面でいいんじゃないか?』と考えてみたら、現実にうまいことマッチして打てるようになったんです」
ゲームで繰り返し対戦するうちに、今まで藤原忠理監督から教わってきた配球論が理解できるようになったという。さらに「チェンジアップを打つときの間合いや、外に逃げていくスライダーの見逃し方もパワプロで学びました」と大石は語った。
開眼のきっかけがゲームにあることは確かのようだが、この言葉を額面どおりに受け止めると、大石という選手の本質を見誤るかもしれない。チーム内で誰よりもグラウンドで過ごし、ストイックにトレーニングに励む姿をチームスタッフは目にしているからだ。
藤原監督はこう証言する。
「自分からは言わないんですけど、ここまで伸びたのは彼の努力あってこそだと思います。190人近い部員がいるなかで、誰よりも早くグラウンドに来て、自分のバッティングに納得いかなければ遅くまで残って練習している。高校時代に控えで悔しい思いをしたからこそ、強い思いを秘めて取り組めたのだと思います。もともと飛ばす能力はありましたが、トレーニングの成果で体をしなやかに使えるようになり、ボールについていけるようになりました」
昨秋の大爆発を受け、大石は西谷監督から「どないしたん?」と驚かれたという。
「西谷先生から『よかったやん』と言ってもらえてうれしかったですね。高校時代は期待を裏切ってばかりで、褒めてもらった記憶があまりないんです。『なんでそれを高校の時にやらんねん!』とも言われましたけど」
そう言って、大石ははにかんだ。西谷監督には、「パワプロ効果」の件はとても言い出せず、伏せておいたそうだ。
卒業後の進路は「藤原監督にお任せしています」と大石は語る。変にプロを意識すると、プレッシャーになる。目の前の野球に集中すれば、結果は後からついてくる。そう考えてのことだ。
最後に、大石に聞いてみた。「大阪桐蔭じゃなかったら、もっと早く出てこられたのに……と思うことはありませんか?」と。
答えは、ほとんど即答だった。
「ないですね。むしろ、桐蔭に行ってなかったら、今の自分はありません。西谷先生から言われてきた『最後は人間性』ということは、今も意識しています。野球だけやっていても、うまくはなれない。生活面をしっかりすることが成長につながっていく。桐蔭で学んだことは、今もめちゃくちゃ生きていますから」
そう言って、大石は画面越しにその日一番の誇らしげな表情を見せた。