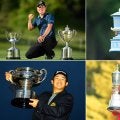「悲運のエース」が沖縄から見つめる高校野球の未来(前編) 昨年は「球数制限」の話題が、野球界を席巻した。そして日本高等学…
「悲運のエース」が沖縄から見つめる高校野球の未来(前編)
昨年は「球数制限」の話題が、野球界を席巻した。そして日本高等学校野球連盟は、ひとりの投手が1週間で500球に達した場合(登板中に達した場合は打者との対戦が完了するまで)、それ以上投げることを認めない制限を、今年3月19日から開催予定のセンバツ大会を含むすべての公式戦で実施することを決定した。まだ改善の余地はあるだろうが、高校野球は大きく変わろうとしている。そんななかで注目を集めつつあるのが、大野倫だ。

最上級生となり沖縄水産のエースになった大野倫
中年以上の高校野球ファンにとっては、甲子園で負傷した”悲運のエース”として記憶しているかもしれない。大野は高校卒業後、九州共立大に進み、巨人、ダイエー(現・ソフトバンク)を経て、今は故郷の沖縄で少年野球の指導者になっている。その起伏に富んだ野球人生について、じっくりと話を聞いた。
大野は1973年4月3日、沖縄県うるま市(当時は具志川市)に生まれる。イチローや松中信彦、小笠原道大などと同学年だ。
「親父は保健体育の教員でした。野球はかじる程度でしたが、スポーツは万能でした。おふくろは美容室を営んでいました。姉と妹がいる3人兄弟の真ん中です。具志川は海も近いし、山も目の前だし、遊ぶ環境は整っていました。学校が終わったら、海に行ったり、山に行ったり、秘密基地をつくったり。大自然のなかの野生児みたいでした」
野球と出会ったのも早かった。
「小学校1年の時、近所の友達が野球を始めて、僕もやるようになりました。その頃から頭ふたつくらい飛び抜けていました。体が大きいからスピードボールを投げられたし、打っても当たれば大きかった。でも、最初は遊びでしたね」
そんな大野の目の色が変わったのが、当時具志川球場で行なわれていた中日ドラゴンズの春季キャンプに行ったことがきっかけだった。
「たしか4年生くらいだったと思います。キャンプのオフの日に、『野球教室』が行なわれて、宇野勝選手、大島康徳選手、都裕次郎投手、藤王康晴選手がいたんです。学校を抜け出して見に行ったのですが、都さんに教えていただいたのを覚えています。体だけは大きかったので『いいボール投げるな』とか褒められて、プロ野球選手に強いあこがれを抱くようになりました。それまで、なんとなく遊びで野球をやっていたのが、甲子園やプロに行きたいと思うようになったのはそこからですね」
大野の野球への打ち込み方は劇的に変わった。そして小学校5年の時に、大野がエースで4番だった田場小学校スポーツ少年団チームは沖縄県チャンピオンとなる。
「当時はボーイズやリトルシニアなどの硬式のクラブチームは沖縄になかったので、具志川東中学の軟式野球部に進みました。でも、中学では県内ベスト4どまり。球は速かったのですが、変化球は一切投げませんでした。小細工に弱くて、バントで揺さぶられて負けるパターンでした」
しかし、大野は屈指の好投手として沖縄県下で、その名を知られるようになっていた。
沖縄は1952年から夏の甲子園の予選に参加するようになる。1975年から単独の大会となり、毎年甲子園に代表を送るようになった。しかし、沖縄県勢は健闘するものの、なかなか決勝戦まで勝ち上がることができなかった。
「仲田幸司(阪神、ロッテ)さんがいた興南高校が『日本一になるんじゃないか』みたいな雰囲気がありました。でも、そこまでいかなかった。そのうちに、沖縄水産が台頭してきて、僕が中学の時には、上原晃さん(中日、広島、ヤクルト)がエースで準々決勝までいきました。でも、当時は県民の皆さんも全国制覇なんてイメージすらわかない時代だったんじゃないかな。
僕自身は、当時、高校野球はあくまでプロに行くステップだと思っていました。ドラゴンズキャンプでプロ野球に触れた経験が強烈だったし、巨人の原辰徳選手が大好きだったので、投手で巨人に入団して、原さんのチームメイトになりたかったんです。中学3年の時には、沖縄水産で甲子園に出て、それからプロに行くと漠然と考えていました」
その沖縄水産の栽弘義監督が、直接、大野をスカウトにやってきたのだ。
「その頃は部活がない時は、学校が終わったら家の裏の陸上競技場でサッカーをやっていました。そしたら母ちゃんが『沖水の栽先生が来るから、家に帰ってきなさい』と呼びにきた。でも、まさかと思ったので帰らなかった。遊び終わって夕方になって、家に帰ったら、栽先生たちが4〜5人で来ていた。母ちゃんに『どんだけ待たせんだ!』と怒られたけど、栽先生はテレビで見たとおりのにこやかな表情でした。当時、沖縄尚学、興南、那覇商などからも声がかかっていましたが、栽先生に会う前から、自分の中では沖縄水産だと思っていたので、先生が来られたその場で『行きます』と即答しました」
沖縄県立沖縄水産高校は、沖縄本島最南部の糸満市にある。「海邦丸」という実習船を持ち、漁業従事者や船員、水産関係者を育成する水産高等学校だ。1980年に、豊見城高で春夏合わせて6回の甲子園出場を果たした栽弘義が野球部監督に就任してから、沖縄県下屈指の強豪校になった。
「僕の家があった具志川から糸満までは車で1時間半かかります。当時は公共交通の便も悪かったから、当然、下宿でした。はじめは野球部の寮に入ったのですが、上下関係がすごく厳しくて、寝る時間もなかった。食事はバイキング形式だったのですが、先輩がほとんど食べてしまうので、僕ら1年は食べるものがなかった。
入学前に栽先生から『体が細いから体重を増やしておきなさい』と言われて、トレーニングジムに通って10キロほど増やしたのですが、入学後にどんどんやせ細ってしまって……。栽先生はそれを見ていて、1年の夏が終わった頃に、先生の自宅の前に建てた合宿所に入れていただくことになった。バッテリーを中心に10人くらいだったと思います。この合宿所では、毎朝、バケツ1杯といっても過言じゃない量のご飯を食べた。それでまた体重が元に戻りました」
当時はまだ、厳しいスパルタ指導が当たり前の時代だった。
「練習は長かったですね。朝練をして、授業のあとは通常の練習があり、夜練もあった。当時は夜の10時から11時ぐらいまで練習していました。休日の日は、それこそ1日中練習していましね。当時の沖縄水産は、沖縄県内から優秀な選手が集まっていました。1年生だけで、入学当初は73人もいました。でも、1日で辞めるような選手もいて、半年で23人になりました。
競争もさることながら、厳しい上下関係や、勝ちを突き詰める環境に適応できなかったんですね。僕が入学した時点で、沖縄水産は5年連続して夏の甲子園に出場していました。甲子園に行くことが義務付けられたチームでした。栽先生のすごいところは、甲子園に連続出場しても緩むことなく、チームを引き締めていたところですね」
しかし大野が1年生の1989年の夏は、沖縄大会の準決勝で興南に敗れ、甲子園出場はならなかった。
「その時、『沖縄水産って負けることがあるんだ』と驚いたのを覚えています。僕は1年生でしたがベンチ入りし、2回戦で1イニングだけ投げました。あとは見ているだけでしたから、経験を積ませるためのベンチ入りだったんですね」
次期エースとして期待されていた大野だったが、新チームになると野手に転向した。
「制球に苦労して、いったん投手を離れて外野手に専念しました。走り込みや投球練習はしていましたが、試合ではほとんど投げませんでした。5番を打っていて、中距離打者で打率は残していましたね。1学年上に神谷善治さんという先輩がいて、身長は175センチほどで、球速も135キロぐらいでしたが、シュートとスライダーを両サイドに決めて、ほとんど打たれませんでした。2年の時は、先輩に甲子園まで連れていってもらった感じでしたね」
この1990年の夏、沖縄水産は県勢として初めて甲子園の決勝に進出する。しかし、天理(奈良)に0対1で敗れ、悲願達成はならなかった。
夏が終わり、新チームがスタートした。大野は最上級生となった。
「チームが負けた瞬間から、僕はエースになりました。いよいよ来たな、と思いました」
中編につづく