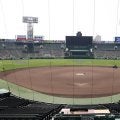数年前にベストセラーになったビジネス書に「GRIT~やり抜く力」というものがある。GRITとは副題にあるとおり「や…
数年前にベストセラーになったビジネス書に「GRIT~やり抜く力」というものがある。GRITとは副題にあるとおり「やり抜く力」のことで、要約すると、粘り強く困難に立ち向かうこと、自発的に取り組むこと、物事に集中し続ける能力などを言う。

浦川流輝亜の先制ゴールを皮切りに、前半で勝負を決めた青森山田
高校サッカー選手権大会でベスト4に進んだ青森山田高校の選手たちを見ると、この「GRIT」に長けているように見える。
サッカースタイルは、攻撃時は4-2-3-1、守備時は4-4-2システムをベースに、オーソドックスな戦いを志向するが、守備では2トップが献身的にボールを追い、サイドハーフは上下動をいとわずに、逆サイドにボールがあるときは、必ず最終ラインに戻る。センターバックは常にマークすべきFWを自由にさせず、相手の足元にボールが入れば素早く寄せ、プレーが終われば最終ラインを再構築する。
攻撃では、浦和レッズ加入内定のMF武田英寿、横浜FC加入内定のMF古宿理久を筆頭に、長くて正確なボールをサイドに散らしてスペースを使い、パスを出したあとは足を止めずに動き続ける。これらはすべて、サッカーにおいて基本的なことだが、相手があるスポーツゆえに、基本に忠実なプレーをし続けるのは難しい。
だが青森山田の選手たちは、誰もが基本的なことを当たり前に、試合を通してやり続ける。まさに、GRITである。
昨年は1年生ながら選手権で優勝を経験し、今年も最終ラインで奮闘する、U-17日本代表DF藤原優大は「今年のチームは誰も、絶対にサボりません。足がつるまで走って、やり切ったところで交代してくれます。全員がそれをやれるチームだからこそ、勝てているんだと思います」と胸を張る。
黒田剛監督はサボらず徹底する部分について「日頃のトレーニングや日常生活から、(甘さを)許さずに積み上げてきた」と話し、こう続ける。
「いろんな自由であったり、楽することを、自分たちで排除しながら積み上げてきました。彼らの誠実さや取り組みすべてが、ピッチの中で顕著に出るんです。24時間365日をどうコントロールしていくかを、彼ら自身が考えてできるようになってきた。そんな1年間を過ごしたことによって、こういう戦い方ができるのだと思う」
昌平高校との準々決勝は、前半で3-0と一方的な展開となった。前半10分には、MF松木玖生が持ち前の技術と身体能力で右サイドを突破してクロスをあげると、MF浦川流輝亜が押し込み、今大会無失点の昌平ゴールをこじ開けた。続く前半19分には、相手のクリアミスをゴール前で拾ったMF後藤健太が決めて2-0。
前半アディショナルタイムには、MF武田が左サイドに絶妙なパスを送ると、そのままゴール前に駆け上がり、浦川のクロスに頭で合わせて3点目を奪取。初戦で興國、2戦目で國學院久我山といった強豪を破った昌平に対し、ゴールラッシュで試合を決定づけた。
後半に2点を取られて追い上げられたが、それに関しては昌平の攻撃陣を褒めるべきだろう。後半9分にはエースのMF須藤直輝が決めると、後半35分には途中出場のFW山内太陽が追加点。前回王者であり、今年度の高円宮杯プレミアリーグチャンピオンを相手に3点差をつけられながら、1点差に詰め寄った。
だが、それ以上は青森山田が持ち堪え、「体を寄せてゴールを隠しながら、ゴールを空けない。ペナルティーエリアに進入させない部分はかなりやってくれた」と黒田監督が振り返るとおり、追加点を許さなかった。
3点リードしたあとに2点を奪われたが、スコア以上に青森山田の強さが際立った試合だった。守備ではセンターバックの箱崎拓と藤原が常に声を掛け合いながら、相手のキーマンを潰し、サイドハーフの浦川と後藤も、相手ボールの時は忠実にスペースを埋めるポジションをとる。
徹底したリスク管理でゴール前に防波堤を築くと、攻撃ではキャプテン武田を起点にサイド攻撃を実行し、DF内田陽介のロングスロー、武田、古宿という正確なプレースキッカーもいる。攻守の安定感は、頭一つ抜けている。
準決勝の相手は、新潟県代表の帝京長岡高校に決まった。次の試合まで5日空くが、黒田監督が「(中断期間に)山田のサッカーとはなんぞやと整理する。そしてコンディションを上げていく。そこは抜かりなくやりたい。(選手たちを)絶対に勘違いさせないようにしないとね」と話すように、過去3度の選手権で2度頂点に立った経験を活かし、準備に余念はない。
前回王者の青森山田は、準決勝で対戦するJ内定トリオを擁する帝京長岡に対しても、持ち前の『やり抜く力』を発揮し、高円宮杯プレミアリーグに続く2冠、そして2000、2001年度の国見高校以来となる大会連覇に向けて、頂点を目指して突き進む。