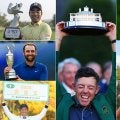連載第24回 イップスの深層〜恐怖のイップスに抗い続けた男たち証言者・赤星憲広(2) 亜細亜大で本格的にイップスになった…
連載第24回 イップスの深層〜恐怖のイップスに抗い続けた男たち
証言者・赤星憲広(2)
亜細亜大で本格的にイップスになった赤星憲広は、内野手をあきらめ外野手に転向した。バックホームなど、腕を思い切り振るロングスローはなんとかなった。問題はカットマンまで正確に返すショートスロー。それでも送球難をごまかしつつ、自慢の快足とシュアな打撃で大学では活躍することができた。
赤星は常に「俺はイップスじゃない」と自分に言い聞かせていた。だが、依然として送球に確固たる自信を持てないままでいた。

快足を武器に1年目からレギュラーを獲得した赤星憲広
「たとえばバッティングピッチャーみたいに打たせて取るようなボールを投げようとすると、ストライクが入らないんです。だから『バッティングピッチャーをやって』と言われると、『ちょっと待って』と躊躇していましたね」
赤星が考えるイップスの怖さは「メンタルだけでなく、技術的にもおかしくなっていくこと」だという。はじめは送球エラーの強いショックから自分に取り憑いた悪魔は、いつしかメカニズムにも侵食してくる。
「だいたいの選手は、野球を始めた頃から自分がどうやって投げているかなんて気にしないものです。壁に当たって初めて『どうやって投げていたっけ?』と原点に戻ろうとする。でも、そこで戻そうとするとおかしなことになる。今まで『普通にやればできる』くらいに思っていたから、戻そうとしてもどうしても違和感が生じるんです。そこから本格的にイップスになっていくのだと思います」
送球イップスになったことで「野球は守り」という信条を持っていた赤星の野球観は根底から崩れた。それでも赤星が幸運だったのは、類まれな快足という武器があったことだ。赤星は東都大学1部リーグ通算45盗塁をマークするなど、外野手として活躍。社会人のJR東日本を経て、2000年のドラフト4位指名を受けて阪神に入団した。
プロに入ってみて意外だったのは、程度の差はあれ、赤星に限らずイップスの選手が当たり前のように存在したことだ。
「練習に入れば、わりとすぐにバレるんですよ。『こいつ、ショートスローが苦手なんだな』って。でも、プロまで来てイップスなんて恥ずかしいと思っていたら、意外と僕以外にもいるんですよ。『国内最高峰の舞台にもいるんだ』と思えて、そこでちょっと解放された感じがありました」
あくまでも、「自分はイップスではない」と信じ続けていた。だが、周りにも送球に不安がある選手を目の当たりにして、赤星は「『送球が悪い』ということを受け入れることも必要だな」と考えるようになった。なぜなら、プロでイップスの気(け)がある選手の多くは、自分なりに工夫して欠点を補っていたからである。
「その人の置かれた状況に応じて投げられる投げ方を身につけているから、それなりに投げられているんです」
どんなに不格好であろうと、きちんと狙ったところに送球できればそれでいい。そう思えたことで、苦手なショートスローを克服するためにチャレンジできた。そのひとつが「ヒジをロックする投げ方」である。
「イップスの人は『あそこに投げなきゃ』と思うほどボールを離せなくなって、ヒジがだんだん前に出てくるんです。そこからボールを離そうとすると、抜くか引っかけるかしかない。だからいっそのこと『ヒジが出ないようにしよう』と意識しました」
野球選手の大半は腕を柔らかく使おうと考えるものだ。「ヒジがしなるフォーム」は称賛されるポイントにもなる。しかし、赤星はヒジを固めて投げる方法を模索した。
「ヒジを固めて、あとは手首だけ使う。ヒジから先をうまく使う練習をしました」
続いて取り組んだのは「変化球を投げること」である。その意図は「指にかける感覚を取り戻すため」だ。赤星は言う。
「イップスの人はどこで力を入れるべきか、その力加減がわからなくなるんです。野手ならピッチング、とくにスライダーやカーブといった変化球を投げる練習をするといいと思います。ボールに指をかけないといけない球種だし、前でリリースしないと投げられない。イップスになるとボールを離すタイミングがわからなくなるので、僕はこの練習がハマりました」
練習中のシートノックでは時折、カットプレーに入ったショートの鳥谷敬にスライダーを投げることもあった。鳥谷は虚を突かれた反応を見せるものの、赤星の意図を知って理解してくれたという。
「トリ(鳥谷)はイップスになったことがまったくないんです。だから『なんでそうなるんですかねぇ?』なんて言っていて、僕は『みんなお前みたいな鋼のメンタルじゃねぇんだよ!』と言い返していました(笑)。でも、トリも大学時代から周りにいたイップスの選手を見てきたそうで、僕のことも受け入れてくれました。周りに理解してくれる人がいるかどうかも、とても大事だと思います」
鳥谷のほかにも、ともに外野を守った金本知憲も寛容だった。試合中にレフトの金本とキャッチボールをする際、赤星は少しリリース感覚に危険を感じると「カネさん、すみません!」と断りを入れてからスライダーを投げた。先輩とのキャッチボールで、遊びともとれる変化球を投げることは本来なら緊張感が走りそうなもの。だが、金本は嫌な顔ひとつせず、それどころかスライダーを投げ返してくることもあった。
キャッチボールで変化球を投げることは、赤星にとって「困ったときの一手」になっていった。
課題のショートスローを克服するために編み出したのは「下から投げる」という方法だった。これは社会人1年目の経験が大きく生きた。
JR東日本に入社した赤星は、チーム事情から1年目はショートとしてプレーした。もちろん、その時点で送球への不安は健在であり、当初は「ちょっと待って......」と後ろ向きだった。それでも、すでに内野手としてのプライドを捨て去っていたこともあり、今度は「ワンバウンド送球でもいい」と割り切れた。人工芝の球場が多かったこともあり、叩きつける送球でもなんとかしのげた。
あとは併殺時などのショートスローをどうするか。そこで赤星は二塁ベースカバーに入ったセカンドに送球する際、試しにアンダースローのように低い角度からボールを投げてみた。すると、今までにない感覚があったという。
「めちゃくちゃいい球がいったんです。下からだと腕が体に巻きつくのではなく、投げたい方向に腕が伸びて、手が体の前で振れる感覚がありました。『これや!』と思いましたね」
プロ入り後、ショートスローの選択肢のひとつとして、赤星の頭にアンダースローが浮かんだ。さほどあわてる必要がない状況では、赤星は下から軽く腕を振ってカットマンまで返すようになった。こうして、あの手この手を駆使してイップスであることを相手に悟られないようにしたのだった。
短い距離が苦手な赤星にとってロングスローは比較的、苦ではなかった。それでも、赤星にはプロとして痛い弱点があった。一軍レベルとしては肩が弱かったのだ。その弱点も赤星は武器を生かした工夫でカバーする。
「二塁ランナーをセンター前ヒットでホームに還さないためには、三塁ランナーコーチの腕を回させなければいい。ではランナーコーチはどの時点で腕を回すかといえば、センターが打球を捕る直前なんです。だから打球に対してブワ〜ッ! と早くチャージすれば、ランナーコーチは『この勢いでは厳しい』とストップの指示を出すんです」
肩の強さではなく、得意の足を抑止力にする。赤星は逆転の発想でピンチを乗り越えていたのだ。
赤星は取材中、何度もこんな言葉を口にした。
「僕はイップスではなく、『弱点』だと思うことにしていました。イップスと思うとまるで不治の病のように感じてしまうけど、弱点だと思えば、ほかの部分でカバーしようという発想になりますから」
6度のゴールデングラブ賞受賞は、赤星の超一流の足を生かした守備範囲の広さが大きな要因だったことは間違いない。その上で「弱点」を補う数々の工夫があったからこそ、「赤星=名手」というイメージが崩れることはなかったのだろう。
(敬称略/つづく)