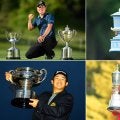連載第5回 新リーダー論~青年監督が目指す究極の組織 1998年8月20日、夏の甲子園準々決勝第1試合。この日の甲子…
連載第5回 新リーダー論~青年監督が目指す究極の組織
1998年8月20日、夏の甲子園準々決勝第1試合。この日の甲子園は早朝だというのに、グラウンドに立つとすぐに汗が体中から噴き出した。試合開始8時30分時点での気温は27.7度。だが、三塁コーチャーズボックスに立つPL学園・平石洋介の頭は冷静だった。
「あっ、やっぱりわかる」
事前に確認していたとおり、横浜の捕手・小山良男(元中日)の構えはパターン化されていた。

今年1月、PL学園のチームメイトから衝撃の真実を告げられた楽天・平石監督
小山がどっしり腰を落とすように構えたら、松坂大輔(中日)はストレートを投げる。腰を浮かしながら体のバランスを取って構えたら変化球——1回の攻撃で平石は確信した。
当時のドキュメンタリー番組で「平石が横浜バッテリーの球種を読み、かけ声でそれを打者に伝えていた」との解釈がなされていたが、それは誤りだ。
番組では「いけ! いけ!」がストレート。「狙え! 狙え!」が変化球と紹介されていたが、このかけ声自体がPL学園の伝統で、この試合に限らず用いられていた。今でこそこうしたサインの伝達は”スパイ行為”とみなされ禁止されているが、当時はそうしたルールはなかった。そして平石のかけ声だが、実際の正解はこうだ。
「いけ! いけ!」は外角で、「狙え! 狙え!」は内角である。
この意図を、当時コーチだった清水孝悦(たかよし)が解説する。
「外角ならバッターは『変化球もあるかも……』って頭に入れる。内角は高校生の場合、ほとんどの確率で真っすぐしかきません。せやから、それ1本に絞れるわけです。そこに小山のクセがはまったんです」
だが、平石は小山のクセを見抜きながらも、選手たちには告げていない。清水が前日にスタメンの選手一人ひとりに狙い球を明確に指示していたからだ。この手のインタビューで「僕の手柄ではない」と否定し続けている平石が念を押す。
「何回も言っていることですけど、松坂が潰れないなら、キャッチャーの小山をかく乱させようと思って声を出していただけで……。清水さんから指示されている選手もいたし、ミーティングで話し合ったこともあったんでね。選手が打ってくれたので、ああやってクローズアップされましたけど、実際は違うんですよ」
ただし、ひとりだけ例外がいた。この試合で先発した稲田学は「平石の声を聞いて打った」と言うのだ。
2回裏、一死二、三塁。カウント1ストライクからの2球目。平石のかけ声は「いけ! いけ!」だった。外角である。実際、小山は外角に構えていたが、カーブは逆球となってインコースに入ってきた。それでも変化球が頭にあった稲田はうまく反応し、センターへの犠飛となった。その後も打線がつながり、PLは幸先よく3点をリードした。
じつは平石がそのことを知らされたのは今年の1月。同級生が集まった場でのことだった。
「そうやったんや!」
21年目の真実に、平石は目を丸くした。
「ああやって、僕のかけ声がみんなを打たせたみたいになって放送されるのが申し訳なくて……。それが嫌で、取材のたびに訂正させてもらっていたんですけど、稲田からその話を聞いて『お前、オレの声を聞いて打ったんか』って(笑)」
もうひとつ、この同級生の集まりで初めて知った真実があった。それは今まで平石が「いまわしき記憶」として忘れたくても忘れられない8回裏のシーンだ。
PL学園1点リードの8回裏、二死一塁。打席には4回に本塁打を放っている小山を迎えた。カウント2ストライク1ボール。この時、平石は迷っていた。
ベンチから見た外野は遠近感がつかみにくい。あらかじめライトに下がるよう指示を出したものの、どうも不安が残る。「結構下がっていると思うけど、もっとライトをうしろへ下げるべきか」と。
ふとスタンドに目をやる。いつものように球場入りした時点で清水の姿を確認しているため、どの場所にいるかは把握している。だが、観客数の少ない地方球場と違って、大観衆が詰めかける甲子園では、とてもじゃないが清水の表情をくみ取ることはできない。
「ええんや、それでええんや」という平石にとって精神安定剤となっていた清水との”阿吽の呼吸”が取れない。もっと下げるべきか、それともそのままか……。平石は迷った挙句、ライトにもっと下げるように指示を出した。
この決断が大きな間違いだった。目一杯、ライトが下がっていると思いながら、ベンチでの平石の指示を見ていたファーストの三垣勝己が、ファーストベースから離れてしまったのだ。
その刹那、平石が気づく。
「三垣、違う! ベースに戻れ」
しかし声を張り上げた時には、投手の上重聡はすでに投球モーションに入っており、一塁走者の加藤重之がスタートを切っていた。バッテリーのウエストも実らず盗塁を許し、直後に小山のセンター前で同点とされた。
平石は自分の判断ミスから同点を許した一連のプレーを悔いた。「思い出したくない」と目を背け、つい最近まで、心の奥底でわだかまりとして残っていた。
だが、この一件も平石の思いとは違っていた。気づかされたのは捕手・石橋勇一郎の回想だった。
「あれはランナーを走らせようとしてやったことだから。あの時、オレもアイコンタクトしてたんだよ」
「は?」
平石がまたも目を丸くする。
要するに、平石が21年間も自分のミスだと信じ込んでいた三垣への伝達は、じつはバッテリーを含めたアイコンタクトで成立していたのだ。
事実、カウント2ストライク1ボールからの4球目、石橋は大きくウエストしている。つまり「とっさに外した1球」ではなく、相手を仕留めるための作戦だったわけだ。ただ、その作戦に引っかからず、二盗を成功させた加藤が一枚上手だったということである。
「おまえ……それもっと先に言えよ! 今までずっと、あれが嫌で嫌で。おまえら本当にやろうと思ってたの?」
すると石橋は、いともあっさりこう答えた。
「やろうと思ったからやってん。そしたらめっちゃいいスタート切られた」
21年目にして思わぬ真実を告げられた平石が、少し安堵したように「あのシーン」についてあらためて語る。
「結局、僕がファーストのポジションを下げた云々ではなく、ファーストランナーを刺す前提での作戦をやろうとしていたみたいです。あのプレーについては本当に後悔していたし、わだかまりとして残っていたんですけど、あいつらの話を聞いて少し心が救われたっていうのはあります」
選手たちが8回の一連のプレーを共有した一方で、清水の視点は少し違っていた。
「冷静に考えるとおかしなプレーなんですよ。1ボール2ストライクでしょ。ストライクを放っておけばバッターは絶対にバットを振るわけですから。バッターオンリーでいいわけなんですよ。たとえ勘違いでベースから離れてしまったとしても、あそこはストライクを取ることが最優先。やっぱり、みんな冷静ではなかったんでしょうね」
わずかな隙を突かれ、試合は振り出しに戻った。この時点で、この先、球史に残る死闘が繰り広げられるとは、誰も想像していなかった。平石はあらためて野球の怖さ、ワンプレーの大事さを実感させられた。