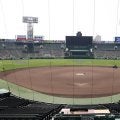外角に鋭く曲がり落ちたスライダーに、バットが空を切る。マウンド上では”大会の主役”が笑顔で…
外角に鋭く曲がり落ちたスライダーに、バットが空を切る。マウンド上では”大会の主役”が笑顔でガッツポーズをつくる。ブラウン管には優勝校の選手たちが歓喜の輪をつくる様子が映し出される。
「横浜・松坂! 決勝戦のノーヒット・ノーラン!」
アナウンサーが渾身のフレーズを読み上げる。1998年夏の甲子園、横浜高(東神奈川代表)のエース・松坂大輔(現・中日)が京都成章との決勝戦でノーヒット・ノーランを達成。”平成の怪物”。高校野球史にその名を刻み込んだ瞬間だった。
偉業達成の瞬間、京都成章の「2番・ライト」で出場していた田坪宏朗(たつぼ・ひろお)は、一塁ベース上にいた。

現在はスポーツメーカーに勤めている元京都成章の田坪宏朗氏
「ああ、これで終わりなんやな」
大記録の誕生とともに告げられた高校最後の夏の終わりに、最初は実感がわかなかった。力強く校歌を歌う横浜ナインの姿を見つめた時、「そうか、ついに終わったんや」と現実を噛みしめた。あの夏から11年が経過した今、決勝で顔を合わせた松坂の印象をこう振り返る。
「あの頃って、まだ140キロが出たら『速い!』と言われていた時代。そのなかで150キロ投げてましたからねぇ。決勝でも球威は十分で、スライダーもすごかったですけど、やっぱり真っすぐのイメージが強いですね」
1998年夏の甲子園は、高校野球史に残る大会として語り継がれている。沖縄水産・新垣渚(元・ソフトバンクほか)、浜田・和田毅(現・ソフトバンク)、東福岡・村田修一(現・巨人二軍打撃コーチ)、鹿児島実業・杉内俊哉(現・巨人二軍投手コーチ)、関大一・久保康友(現・メキシコリーグ)を筆頭に、のちにプロ野球界を湧かす選手たちが出場し、大会を盛り上げた。
そんな粒ぞろいのなかでひと際強い輝きを放っていたのが、松坂だった。松坂擁する横浜は同年春のセンバツも制しており、各校が「打倒・松坂」を掲げて甲子園に乗り込んできた。その結果、延長17回の死闘を繰り広げたPL学園(南大阪戦)戦や、最大6点差を逆転した明徳義塾(高知)戦などの名勝負が生まれた。
当然、田坪たち京都成章も横浜、松坂との対戦を意識していたのだろうと思っていたが、実状は少々異なっていた。
「いや、もう全然です。横浜を意識できるほど、自分たちに力があるとすら思っていませんでした。正直、夏も甲子園に戻って来られるかもわからなかったですし」
春のセンバツは京都成章だけでなく、京都西(現・京都外大西)も同時出場。前年夏の甲子園準優勝を経験したメンバーが残る平安(現・龍谷大平安)にも力があり、「京都成章1強」の状況ではなかった。
それでもしぶとく京都大会を勝ち上がると、甲子園でも快進撃を続けていく。初戦は仙台(宮城)を10-7で下すと、2回戦では当時急速に力をつけていた如水館(広島)を5-3で退けた。
地方大会、甲子園を勝ち進むなかで、田坪たち京都成章ナインには、ある感覚が生まれていった。
「県大会だけでなく甲子園の序盤も含めて苦しい展開の試合が多かった。そこを勝ち抜いていくなかで、『勝てる気はしないけど、不思議と負ける気もしないな』と感じはじめていました。意識も『とにかく勝とう!』というよりも、各々のやるべきことをやろうという感じ。それがよかったのかなとも思いますね」
その不思議な感覚は、その後も続いていく。準決勝では主砲・古木克明(元横浜ベイスターズほか)を擁する豊田大谷(愛知)を相手に6-1。とうとう決勝進出を果たし、絶対王者・横浜と対戦することになった。
前日に映像で松坂を研究したが、チーム全体での狙い球は決めず、各自で球種、コースを絞る形をとった。そのなかで田坪は「低めの真っすぐ」の見極めをテーマに置いた。
第1打席で目の当たりにした松坂の直球をこう振り返る。
「『ワンバンかな?』と思った真っすぐが真ん中付近にくる。ひと目でもすごさは伝わってきましたね」
平成の怪物が投じる快速球に圧倒されたが、戦意は失わなかった。頭に浮かんだのは「打てない気もしないな」という、「不思議と負ける気もしない」に似た感情だった。
松坂の快投、京都成章のエース左腕・古岡基紀の粘りの投球が繰り返され、スコアボードが数字で埋まっていく。8回を終え、京都成章が3点ビハインド。その時点で、松坂は1本の安打も許していなかった。否が応でも”快挙”への期待が膨らむなか、9回表の攻撃が始まった。
一死後、主将の1番・澤井芳信が三塁ゴロに倒れ、いよいよ球場は異様な雰囲気に包まれる。球場が騒然とした状況で田坪は打席を迎えたが、ここでも平常心を保っていた。
「いま言うと笑われるかもしれませんが、打席が回ってきたとき『よし打ったろう!』と思っていたんです。変に力むでもなく、『甘い球がきたらいくぞ!』と。自分が最後のバッターになるとも思っていなくて……」
事実、第2打席に四球を選ぶなど、田坪は松坂のボールを見極めていた。いくばくかの自信を胸に、左バッターボックスに足を踏み入れた。
初球は抜け気味のスライダーが外に外れてボール。2球目は直球を投じ、外に決まってストライク。3球目はワンバウンドするスライダーを見極め、4球目は高めに浮いたストレートに手を出しそうになりつつも、バットを止めた。
カウント3ボール1ストライク。「高めの甘いストレート、来い!」。意識を研ぎ澄ませ狙い球を待ったが、松坂の右腕から放たれた直球は大きく高めに外れた。この試合、2つ目の四球を選び、一塁へと向かった。
一塁ベース上に立ってもなお、田坪のなかに”不思議な感覚”は残り続けていた。
「9回ツーアウト。ここまで追い込まれても『次のバッターがなんとかするんじゃないか』という思いが消えませんでしたね。まだ試合は終わらないんじゃないか、と」
だが、田坪の祈りは届かず、続く打者が空振り三振に倒れ、京都成章の夏が終わった。「勝てる気もしないけど、負ける気もしない」。その思いがあったからか、最初は敗れた実感がなかった。
京都大会初戦から甲子園の準決勝まで、校歌は”歌う側”だったため、久々に相手校の校歌を耳にした時、敗戦が一気に現実として押し寄せた。
「終わったんやな……。そうか、やっと終わったんか」
目の前の一戦に集中し、どこか夢を見ているような感覚で戦ってきた夏が幕を閉じた。悔しさはあったが、解放感と達成感も同時に感じていた。
「春のセンバツで大敗(初戦で岡山理大付に2-18で敗戦)して、恥をかいて……正直、甲子園は嫌な思い出しか残せていませんでした。でも、無理かなと思っていたなかで、夏も甲子園に戻って来て、決勝まで勝ち進むことができた。決勝でノーヒット・ノーランをされて悔しさはありましたが、『やっぱ甲子園っていいところやな。努力は報われるもんなんやな』と」
夏の決勝には、ひとつ”エピローグ”が残されていた。神奈川で開催された国体の決勝で、再び横浜と対戦したのだ。
「1-2で負けたんですが、松坂から(チームで)8本ヒットが打てた。ノーヒット・ノーランの映像は嫌でも流れるけど、むしろこっちの映像を見たいんで流してくれんかなあ、と思いますね(笑)。この試合があったから、野球を嫌いにならずにいられたのかな、とも思います」
野球を嫌いにならなかった——この言葉どおり、田坪は大学でも野球を続け、卒業後は野球をはじめ、数多くのスポーツ用品を小売店に卸す問屋に就職。その後、「もっと野球に深く関わりたい」と、スポーツメーカーのウイルソンに転職。野球を担当し、今年3年目を迎える。
現在はグラブの企画、開発に携わっている。仕事柄、現役の高校球児と関わる機会も少なくない。
「メーカーで働いていて『これを現役の時に知っていればなあ……』と思うことがいくつもありますね(苦笑)。とくに思うのは、正しい使い方や手入れの仕方。高校の時に使っていたグラブは、変な手入れの仕方をしてしまったせいで、めちゃくちゃ重かった。グラブの軽さを維持できる手入れの仕方を知っていたら、もっと守備範囲も広がっていたのかなと。そういったことを、現役の選手たちに伝えていきたいですね」
平成の怪物と決勝を戦った過去を、自ら話題にすることはほとんどない。
「負けているし、『自分が”松坂世代”を名乗っていいんかなあ』という負い目みたいなものもあります。でも、年齢を言って、『京都の高校で野球をしていました』と話すと、気づかれることも多いですね(苦笑)。覚えてもらえるので、得しているのかな、と思うようにはなっています」
試合の続きを信じて、一塁へと駆け出したあの日のように。野球を嫌いにならなかった男は、いまも”松坂世代”の一員として、野球の世界で一歩ずつ歩みを進めている。