夏の県大会が始まる直前、智弁和歌山の名誉監督である髙嶋仁に、教え子も多く残る現チームへの期待を尋ねた。すると、こん…
夏の県大会が始まる直前、智弁和歌山の名誉監督である髙嶋仁に、教え子も多く残る現チームへの期待を尋ねた。すると、こんな答えが返ってきた。
「記録がかかっとるのが3人おるからね。これは何とか達成してほしいと思うとるんです」
高嶋が言う”記録”とは、黒川史陽、西川晋太郎、東妻純平にかかる「5季連続甲子園出場」で、つまり和歌山大会を制することを指していた。あえて個人記録への期待を口にしたところに、1年時から高嶋の厳しい叱責にも食らいついてきた3人への思いが伝わってきた。
「5回続けて甲子園に出るということは、1年の夏から甲子園に出るチャンスを全部ものにしたということやからね。ほんまに大したもの、価値があります。ウチでは道端(俊輔/現・明治安田生命)が5回出たけど、岡田俊哉(中日)や西川遥輝(日本ハム)は4回。5回出場というのは過去に9人しかおらんと聞いて、余計に達成してほしいなと思うようになったんです」

5季連続甲子園出場を果たした智弁和歌山の主将・黒川史陽
これまで5季連続甲子園出場を果たしたのは、以下の9人である。
堤達郎(高松商/1977夏~79年夏)
荒木大輔(早稲田実業/1980年夏~82年夏)
小沢章一(早稲田実業/1980年夏~82年夏)
黒柳知至(早稲田実業/1980年夏~82年夏)
清原和博(PL学園/1983年夏~85年夏)
桑田真澄(PL学園/1983年夏~85年夏)
梅田大喜(明徳義塾/2002年夏~04年夏)
鶴川将吾(明徳義塾/2002年夏~04年夏)
道端俊輔(智弁和歌山/2009年夏~11年夏)
戦前は旧制中学制度により6回出場した選手もおり、この9人というのは戦後の記録であるが、それにしても偉大な記録である。そんな高校野球史に残る選手が、この夏の智弁和歌山には3人もいるのだ。
夏の甲子園大会の開幕日。開会式を終えると、49校の主将が室内練習場に集まり、それぞれ取材を受けていた。5度目の入場行進を終えた黒川は、記者との受け答えも慣れたもので、貫録を漂わせていた。もちろんそれだけではない。試合時の甲子園球場の雰囲気も、打席から見える景色も、黒土の感触も、夏の日差しや浜風も……さらに言えば、大会中の過ごし方、宿舎の部屋の様子や周辺の地理もすべて熟知している。
「宿舎も5回目なので、久しぶりに家に帰ってきたみたいな感じです」というコメントからも、余裕がうかがえる。
高校野球の世界では、よく”経験力”という言葉が使われる。2004年のセンバツで史上最速となる創部3年目で日本一に輝き、同年夏も甲子園準優勝に輝いた済美の話を、当時の監督である上甲正典に聞いたことがある。
「選手は本当によくやってくれました。経験力っていうのはすごく大きくて、ウチの選手たちは創部と同時に入ってきました。つまり先輩がいないから、1年の時からすべての大会に出て経験を積んでいったんです。3年になった時には『どこと対戦しても負けられない』という気持ちになっていたんじゃないかな。それくらい、高校生にとって経験というのは大きいんですよ」
黒川にあらためて連続出場することへのメリットを聞くと、「5季連続というより、甲子園で4回負けてきた。そこを経験していることが一番だと思っています」とキッパリ言い、こう続けた。
「負けを知って成長できたということを、野球をやるなかで感じてきました。だから甲子園で4回も負けを経験できたということを、この夏、絶対に生かさないといけない。負けたからこそ悔しくて練習をやってきたし、強くもなれた。だから結果につなげないといけない」
そんな黒川の言葉を聞きながら、高嶋の口癖が脳裏に浮かんだ。
「選手が伸びるのは、腹の底から『くそったれ!』と思う悔しさを味わった時」
黒川たちにとってひと際大きかったのが、昨年の大阪桐蔭の存在だ。根尾昂(中日)、藤原恭大(ロッテ)らが最上級生となった代のチームとは、一昨年秋の近畿大会、昨年のセンバツ、春の近畿大会と3度対戦し、いずれも敗れた。しかし、史上最強とも言われたチームと公式戦で3度、しかも黒川、東妻、西川らは2年生として対戦した経験は智弁和歌山に大きな財産を残した。
では、王者・大阪桐蔭との対戦は、黒川たちのなかに何を残したのだろうか。
「大阪桐蔭には『日本一になる』というだけじゃなく、『達成しないといけない』という雰囲気を感じました。だから日本一を目指すなら、チーム全員が本気で『日本一になる』と強く思わないと達成できない。キャプテンとしてそこは言い続けてやってきました」(黒川)
「日本一になるためには、大阪桐蔭のあのレベルまでいかないといけない。登録メンバーに入っていない選手も『日本一になる』と徹底して練習に取り組んでいるという話を聞いて、自分たちもそこを求めて1年間やってきました」(東妻)
黒川は「5季連続甲子園出場」と「日本一」という明確な目標をもって、智弁和歌山に入学してきた。父・洋行氏が1993年のセンバツで上宮(大阪)の主将として日本一を経験。その影響もあって少年時代から「やるからには日本一」と、常にそこを目指して野球に打ち込んできた。
まさにその考えは、高嶋がつくり上げた智弁和歌山の教えに通じるもので、黒川がここで主将としてチームを引っ張っていることに必然性を感じてしまう。黒川の強い思いは、時にチームに緊張感を走らせたが、そんな時に支えとなったのが東妻と西川のふたりだった。黒川がふたりへの思いを口にする。
「ふたりがいてくれたのは、本当に自分にとって大きかった。心から信頼できるふたりなんです。試合のなかで考える場面があったとしても、グラウンドに東妻と西川がいると安心できますし、すぐに声をかけて考えを聞いたりもします。これだけの信頼関係を築ける仲間というのは、これから先もないだろうと思うぐらいで、自分はキャプテンですけど、東妻と西川には頼るところは頼ってやってきました。3人だからこそやってこられたという思いは、本当に強いです」
夏の和歌山大会は、まったく危なげのない戦いで制した。そのなかでも3人の活躍が光った。打順は、春の近畿大会から黒川が3番→1番、西川が2番→3番、東妻が4番→6番に移ったが、これが見事に機能した。
和歌山大会では、黒川.444、西川.526、東妻.529と揃って高打率を残した。黒川は2本の本塁打も放ったが、真骨頂は決勝での先頭打者本塁打。春の大会以降の打順変更は、監督である中谷仁のなかの「黒川を1番に」からの発想だった。
当初、好打に足もある細川凌平が1番を打っていたが、より打線に勢いをつけ、相手の出鼻をくじく迫力ある打線を求めたところ、黒川に白羽の矢が立った。そして中谷が求めた迫力ある打線の象徴が、和歌山大会決勝での黒川の先頭打者本塁打だったのだ。
西川は2番を打っていた時、走者との兼ね合いのなかで高度なバッティングを求められた。ミート力の高さと器用さゆえの要求だったが、3番となった今、西川は「2番の時の経験が生きています」と言った。状況に応じ、走者を還すバッティング、ランナーを進めるバッティング、長打を狙うバッティング……を使い分け、打線に厚みを持たせた。
そして正捕手の東妻は、センバツの準々決勝(明石商戦)で悔しいサヨナラ負けを経験し、春の大会では途中交代を命じられるなど、苦しい時間が続いた。現役時代に捕手だった中谷監督から「もう一段上まで上がってこい」と厳しい指導を受けるがそれに耐え、和歌山大会では見事なリードで投手陣を引っ張り、5試合でわずか1失点と成長の跡を見せた。
「夏の直前までずっとつらかったです。中谷監督からリードの中身についてアドバイスをもらって、自分なりに考えてやるんですけど、うまくいかないことの繰り返しで……。でも最後は『やるしかない』と開き直って、やってきたことをすべて出すしかないとシンプルにいったのがよかったと思います」
三者三様、求められることに対応し、チームを勝利に導いた姿を見ると、やはり経験を積んできた彼らの強さを感じずにはいられなかった。
当然だが、経験を積んできたのは5季連続甲子園出場を果たした3人だけではない。今回ひと桁の背番号を背負う9人はいずれも甲子園は2回以上経験しており、エースの池田陽佑、外野手の根来塁、2ケタ背番号ながらスタメン出場もある野手の久保亮弥は4度目の甲子園である。ちなみにベンチ入りの18人中、初めての甲子園となるのは、1年生の徳丸天晴、中西聖輝と、2年生左腕の矢田真那斗だけ。
智弁和歌山の3度の日本一を振り返ると、1994年のセンバツ日本一の時は、前年夏の甲子園で2勝を挙げたメンバーが7人残っていた。1997年夏の優勝も、レギュラー9人中6人が前年に春夏連続出場を果たした時のメンバーで、2000年夏も下級生の時からチームの中心にいた堤野健太郎、池辺啓二らの活躍によって成し遂げられたものだった。
ただ、2000年以来の日本一を見据えつつ「勝つことは簡単じゃない。どんな状況でも絶対に緩めないこと」と黒川が言えば、和歌山大会を制した直後に東妻も「ここまではいい感じできましたけど、甲子園はわからないです」と浮かれることなく、冷静に語っていた。甲子園の怖さ、勝負の怖さを知っているからこその言葉なのだろう。
いよいよ3人にとって、5度目の甲子園が始まる。明日の第1試合で米子東(鳥取)と戦う。
「西川は朝が弱いので、アップの時からしっかり声を出して、頭も体もきっちり起こして、初回から全力で入っていきます」
そう笑顔で西川をいじった黒川だが、すぐに表情を引き締め、決意を口にした。
「東妻、西川と一緒にプレーできる最後の大会。寂しい思いもありますけど、最後まで3人でチームを引っ張って……もう絶対に負けられない。必ず日本一になります」
覚悟をもって挑む最後の甲子園。はたして、どんな結末が待っているのだろうか。




































































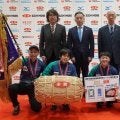



![アルカラス、難敵ポールを退け3年連続の8強進出!史上最年少の生涯グランドスラムに邁進[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012516260245513700.jpg)



