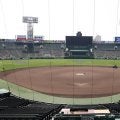負けないエース・斉藤和巳が歩んだ道(3) 1999年、2000年にパ・リーグを連覇したホークスは、2003年に斉藤和…
負けないエース・斉藤和巳が歩んだ道(3)
1999年、2000年にパ・リーグを連覇したホークスは、2003年に斉藤和巳を中心とした投手力と、チーム打率2割9分7厘を誇った強力打線でリーグ優勝を飾り、日本一に登り詰めた。しかし、その後はリーグ優勝から遠ざかることになる。
2004年に新設されたプレーオフ(クライマックスシリーズ:CS)で勝てなかったからだ。ホークスにとっての”鬼門”を勝ち抜かない限り、リーグ優勝も日本一も見えない。2006年プレーオフは斉藤にとっても、チームにとっても格好のリベンジの場だったのだが・・・・・・。 
2006年のCS第2ステージでファイターズに敗れ、マウンド上でうずくまる斉藤
【王監督のためにも負けられなかったCS】
ホークスは短期決戦で勝てない。
2年続けてプレーオフで負けたホークスは、そう言われるようになった。シーズン1位で臨んだ2004年のCSは、第2ステージでライオンズに敗れて2位に終わった。親会社がダイエーからソフトバンクに代わった2005年は、シーズンで89勝を挙げるなど抜群の強さを見せたものの、やはりCSでマリーンズに敗れて”下克上”を許した。
「三度目の正直」と臨んだ2006年のシーズンで3位だったホークスは、日本シリーズに進むために同2位のライオンズ、同1位のファイターズに勝たなければならなかった。
その年のペナントレースで26試合に登板し、初めて投球回数が200イニングを超えた斉藤には疲労があったはずだ。だが、目標はリーグ優勝をして、日本一になること。チームを離れて胃がんの治療に専念していた王貞治監督に、いい報告をすることだった。
斉藤はライオンズとのCS第1ステージ第1戦に先発し、その年に17勝をマークした松坂大輔と投手戦を演じる。エース対決は0-1で敗れたものの、チームは第2戦と第3戦に勝利してファイターズとの第2ステージに進んだ。
シーズン1位のファイターズには1勝のアドバンテージがあり、第1戦で敗れたホークスは早くも窮地に追い込まれた。負けられない第2戦、ホークスはエースをマウンドに送った。ずっと中6日という登板間隔を守ってきた斉藤にとって、6年ぶりの中4日での登板となった。
ファイターズ先発の八木智哉との投げ合いで、両チームとも無得点のまま9回裏を迎えた。ファイターズの先頭打者は森本稀哲だった。斉藤は足の速い一番打者にあっさり四球を与えてしまう。
斉藤が振り返る。
「完全にスタジアムの雰囲気に飲まれました。9回表にホークスが0点で終わった瞬間、『1点取られたらサヨナラ負けになる』と思ってしまった。そして、初球、2球目とボールが続き、スタジアムの空気が変わりました。メンタル面で後ろ向きになったのがダメだった」
2006年のファイターズは、シーズン中に「引退宣言」をした新庄剛志がファンを盛り上げていた。2002年に本拠地を北海道・札幌に移転して以降の初優勝を目前に、ムードは最高潮に達しつつあった。ファンが見たかったのはファイターズのサヨナラ勝ちであり、監督、選手たちの胴上げだった。
【五番・稲葉に対して計算どおりの投球】
二番の田中賢介が送りバントで森本を二塁へ進めた。ワンアウト二塁で、三番の小笠原道大が打席に向かう。
「森脇浩司監督代行がマウンドに来たので、小笠原さんを敬遠して(フェルナンド・)セギノール勝負を指示されると思っていました。ところが森脇さんは『和巳、どうしたい?』と聞いてきた。僕は勝つこと優先なので、プライドなんて関係ない。『敬遠します』と言いました」
四番は斉藤が”カモ”にしていたセギノールだった。その後には稲葉篤紀、新庄が控えていた。
「セギノールで勝負というよりも、セギノールでダブルプレーを取りたかった。だけど、『あんまり欲張っても』と思ったので、三振を取りにいきました」
狙いどおりに三振を奪った斉藤は、ツーアウト一、二塁で稲葉を迎 えた。このシーズン、打率3割0分7厘、26本塁打、75打点を挙げた稲葉はチャンスに強いバッターだ。
「もうランナーは関係ない。稲葉さんとの勝負だと思いました。『このバッターさえ抑えれば延長戦になる。球数を考えれば、最後だろう』と。もし稲葉さんに打たれれば、サヨナラ負けが決まる。そうなれば、長かったシーズンがそこで終わる。力を振り絞ってギアを上げました」
初球の渾身のストレートはアウトコースに外れてボールの判定。このとき、稲葉はフォークに狙いを定めていたのだが、斉藤が知るはずもない。
「際どいところでボールになりましたが、ここまでは計算どおりでした。ツーボールにはしたくない。ストレートは続けにくいから、2球目にフォークを選びました。僕はよくストライクゾーンの低めにフォークを落としてゴロを打たせていたんですが、稲葉さんに引っかけさせたかった。投げたコースも計算どおり。ただ、ほんの少しだけ甘く入ってしまった」
稲葉が捉えた打球は斉藤の左に転がり、それを捕ろうとしてグラブを伸ばしたが、届かなかった。斉藤は倒れ込んだままの姿勢で、打球を目で追った。
「際どいところに打球が飛んだのは、ファイターズに勢いがあったから。自分の力のなさも痛感しましたが、彼らはやっぱり強かった。勢いと強さが最後のプレーに出たと思う」
打球は試合出場経験の少ないセカンド・仲澤忠厚とセカンドベースの間に飛んだ。仲澤は横っ飛びで捕ろうとした。
「パッと見た瞬間に、仲澤が捕れそうな位置にいるのがわかりました。(ショートの川﨑宗則が待つ)二塁へのトスがふわっと浮いて『セーフかも・・・・・・』と思った後に塁審が両手を広げて、その瞬間に森本がホームに走るのが見えました。もう間に合わへん。『すべてが終わったな』と思いました」
キャッチャーの的場直樹が川﨑からの送球を受けたときにはもう、森本がホームを踏んでいた。それを見たスタジアムの観客とファイターズの選手たちが喜びを爆発させた。
一方の斉藤は、マウンドに手を着いたまま動けなかった。その瞬間は、何の感情も沸いてこなかった。
【魂と意思と責任をボールにこめて】
それから13年が経った今も、稲葉への投球を的場は強烈に覚えている。
「1球目のストレートがいいボールすぎました。『これで打たれるはずがない』と思いました。あとで稲葉さんが『フォークを狙っていた』と聞きましたが、僕が出したサインは間違っていない。
セカンドにゴロが転がって、小笠原さんが二塁に全速力で走るのを見て、『間に合わない』と思いました。三塁コーチャーを見たら、白井(一幸)さんが腕を回していたから、『ホームに投げろ』と言ったんですが、野手には聞こえませんでした」
ショートの川﨑からの送球を受けた的場はそのまま崩れ落ちた。
「全員がベストプレイをした結果です。和巳は全力で投げた。仲澤も川﨑も、一塁ランナーの小笠原さんも、やるべきことをやった。ちょっとした差が勝負を分けただけ。送球を受けた瞬間、和巳がうなだれているのが見えて、『あぁ、終わったんや・・・・・・』と思った瞬間、緊張の糸が切れました」
もう一度あの場面に戻れるとしたら、どんな選択をするだろうか。
「同じサインを出すでしょう。後悔はありません。ただ、森本をフォアボールで出したのはもったいなかった。あれでスタジアムの雰囲気が変わってしまった。ファイターズの応援がものすごく盛り上がって、『嫌だなあ』と思いました。和巳のいいストレートを見逃して、フォークを狙って、センターに強い打球を打った稲葉さんがすごかった」
ゲームセットのあと、斉藤がどうしたのか、的場は知らない。
「みんなで『和巳がいない』となって探したんですが、見つからなかった。もし会っても、かける言葉がなかったでしょうね。僕はホテルの部屋に戻って、ずっとひとりでいました。この試合について、和己と細かい話をしたことがありません。でも、きっと彼も後悔はないでしょう。魂と意思と責任をボールにこめて投げるピッチャーでしたからね」
【斉藤和巳というピッチャーのすべてが見えた】
マウンドに右手を着いたまま動かない斉藤に肩を貸し、ベンチまで抱えて歩いたのは、フリオ・ズレータとホルベルト・カブレラのふたりだった。9回を投げ終えて燃え尽きた192センチのエースは、大柄の外国人選手ふたりがかりでなければ動かせなかった。
そのシーンを、療養中の王が見ていた。
「あのシーンに、エースの責任感が表れていた。斉藤和巳というピッチャーのすべてがね。どれだけ責任感を持ってマウンドに上がっていたのか、どんな思いで勝つことを目指していたかがわかった」
当時、巨人に在籍していた小久保裕紀もテレビで試合を観戦していた。
「外国人選手に抱えられながらベンチに戻るのを見て、『オレがグラウンドにいたら、最初に近づいていって、連れて帰ってやったのに』と思いました。試合後にはきっと、人目につかないところにいたはずです。悔しすぎて、ひとりになりたかったんでしょう」
斉藤は身を削る覚悟でマウンドに上がり、敗れた。
【「負けないエース」が燃え尽きた】
北海道移転後初めての優勝に沸くファイターズの選手、ファンの歓声も、斉藤の耳には届かなかった。記憶は途切れ途切れにしか残っていない。
斉藤が振り返る。
「マウンドから見えた景色、ベンチ裏まで連れていってもらったことなどは覚えています。誰かに肩を叩かれたけど、自分の力では立ち上がれなかった。そのまま、ベンチ裏でずっと泣いていました。ロッカーまでどうやって歩いていったかはわからないけど、お通夜みたいに静まり返っていて、その空気に触れた瞬間にものすごい責任を感じました。『オレのせいで……』と」
胸にあったのは、チームメイトに対して申し訳ないという思いだけだった。チームメイトの気持ち、療養中の王監督への思いを背負ってマウンドに上がった斉藤の戦いは終わった。
斉藤はその後、チームとは別行動を取った。自分で航空券を手配し、福岡ではなく、ひとりで東京に向かった。何もする気にならず、何もすることができず、しばらく部屋に引きこもった。絶望感を抱いたままで。
気持ちを切り替えることなどできなかった。斉藤の時計はここで止まってしまった。
2003年に20勝を挙げてエースになり、2004年に10勝、2005年に16勝、2006年に18勝を積み上げた斉藤の肩はもう限界にきていた。
2007年は登板間隔を空けながら6勝を挙げ、マリーンズとのCSにも登板した。しかし、10月8日のピッチングを最後に一軍から消えた。その後に2度右肩を手術し、長くリハビリを行なったものの、二度とマウンドに上がることはなかった。
2003年からの4年間で64勝16敗を上げた斉藤の勝率は8割。しかし、リーグ優勝できたのは2003年だけだった。「負けないエース」はホークスを勝たせることはできなかった。
小久保は言う。
「『野球選手は、活躍できなくなってやめるか、体が壊れてやめるかだ』。これは根本陸夫さんに言われた言葉ですが、この意見に僕は賛成です。体が元気で、どこも痛くなくても、戦力外を通告されることもある。だったら、壊れるまで投げるというのは幸せなのかもしれない。
和巳は、投げられなくなるまで投げた。そういう意味では、幸せだったかもしれませんね。だからこそ、いまでも彼のことがクローズアップされるのでしょう」