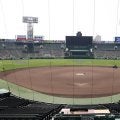2005年7月25日、水戸市民球場。3点差を追う9回二死、常総学院の勝田憲司はネクストバッターズサークルから祈るよ…
2005年7月25日、水戸市民球場。3点差を追う9回二死、常総学院の勝田憲司はネクストバッターズサークルから祈るような気持ちで戦況を見つめていた。打席に立つ選手が塁に出れば自分まで回ってくる。「この劣勢をなんとかしてやろう!」という気持ちもあったし、2年半をともに過ごした仲間への信頼もあった。
しかし打者のバットが空を切り、主審の右手が上がりかかった……その瞬間、球場中が歓喜とため息に包まれたが、勝田は打席で泣き崩れる仲間に向かって「走れ!」と大声で叫んでいた。空振り三振かと思われたが、相手キャッチャーのミットからボールがこぼれていたからだ。
だが、勝田の声はスタンドの大歓声にかき消され、仲間の耳には届かなかった。ゲームセット。受け入れがたい現実を前に、勝田はその場で呆然と立ち尽くしていた。

かつてはプロ注目のスラッガーだった勝田憲司
あれから14年の月日が流れた。
久しぶりに顔を合わせた勝田はすっかり頬がこけ、大人の顔つきになっていた。
今回、勝田と会うきっかけをつくってくれたのは、昨年、DeNAを退団し、今年から社会人野球のJFE東日本でプレーすることになった須田幸太だった。
須田と勝田は、茨城県石岡市の府中中学校の軟式野球部出身で、須田は勝田の1学年先輩にあたる。今年2月にある媒体で須田のインタビューをした際、当時の茨城の高校野球についての話で盛り上がり、そこで勝田の話題になった。すると須田が「勝田、今度、格闘技やるみたいですよ」と教えてくれた。
格闘技――勝田が選んだ新たなステージは、意外な気もしたが、どこか納得するところもあった。なぜなら、高校時代に勝田を取材した際、彼の口から当時人気が高かったK‐1や総合格闘技についての興味をそれとなく聞かされていたからだ。とはいっても、あくまで”見る側”としての興味であり、まさか”やる側”の人間になるとは、当時は思いもしなかった。
ひとつ意外だったのは、勝田の現在の年齢である。高校卒業後、八戸大学から社会人野球の住友金属鹿島に進んで2年間プレー。野球を辞めてすぐの格闘技転向なら「なるほど」と納得できるのだが、そこから数年の歳月が経ち、勝田は今年32歳になる。
しかし、キックボクシングを始めて今年で3年目を迎えるという。その間、地下格闘技の大会にも数試合出たというから、まったくの素人でもないようだ。
勝田が言う。
「(最初に地下格闘技に出た時は)サンドバッグとか、何も練習していなくて、いきなりぶっつけ本番で試合に出た感じで……それから2試合目が決まった時は『さすがに練習しなきゃダメだろう』と思って、いまのジム(Bombo Freely)に通わせてもらうことになりました」
ジムに通い始めた当時の体重は98キロもあったそうだ。そこから3年かけて30キロ近く減量し、現在は70キロ前後まで体を絞ったと話す。ただ勝田の姿を見る限り、不健康そうな感じもなく、無理な減量をした様子はない。むしろ、体調はジムに通い始めた3年前よりもよくなっていると言う。
「本格的に(キックを)やり始めて、『もっと、もっと』と追求していくうちに、いまに至りました。今度がキックボクサーとしてのデビュー戦になるんです」
4月21にキックボクサーとしてデビュー戦が予定されているという。ちなみに、地下格闘技時代の戦績は4戦3勝(3KO)1分。並み居る喧嘩自慢の男たちから強烈な打撃を一度も喰らったことがないというから、よほどセンスがあるのだろう。ちょっぴり期待が持ててきた。
じつは勝田には、格闘技デビューのほかにいろいろと聞きたいことがあった。
そもそも14年前の勝田は、高校野球ファンの間では名前を知らない者はいないというぐらい全国でも名を馳せたスラッガーだった。名将・木内幸雄監督に素質を高く評価され、1年夏からベンチ入りを果たし、その夏には坂克彦(元阪神など)、大崎大二朗(元東京ガス)らとともに全国制覇も経験している。
高校通算本塁打数は31本。その数字自体に派手さはないが、その後プロに進んだ好投手から、打った瞬間それとわかる豪快な一発を放つなど、打者としてのインパクトは絶大だった。当時の高校野球専門誌を開けば、ドラフト候補として大きく取り上げられていたし、あの頃の活躍を思えば、一度もプロの世界に足を踏み入れなかったことが意外なほどである。
不躾と思いつつ、なぜそれほどの逸材が大学、社会人と進むなかでプロスカウトの目に留まらなかったのか。
「高校を卒業して、大学の時に右ヒジを手術したんです。1年の秋に最初の手術をして、2年の春に靱帯も切れちゃって……『もう野球はできないのかな』と、その時に思ったんです」
それでも大学、社会人と野球は続けてきたが、ヒジの違和感がなくなることはなかった。リハビリをしても動かすことへの恐怖がつきまとい、高校時代にプロのスカウトから高く評価されたバッティングを見失ってしまった。
「自分は右投げ左打ちなので、バッティングで右ヒジを使うじゃないですか。ひねった時に痛みが出て……その痛みをかばうあまり、右手が使えなくなったんです。それが原因で、その後はまったく打てなくなりました」
大学4年の時は指名打者として北東北大学野球連盟のベストナインに選出されたが、バッティングの感覚は高校時代とまったく違っていたと言う。社会人に進んでからもそれは変わらず、結局、野球を続けることを断念した。
「野球をやっている時は誰もがプロを目指してやっていると思うんです。でも、やっている本人しかわからない部分もあると言いますか、(高校時代に)周りからはいろいろと評価をされてきたのかもしれないですけど、自分のなかでは『プロになれる』と思ったことは一度もなかったんです」
プロ野球選手になりたい気持ちはもちろんあった。そのために友人や家族と過ごす時間を犠牲にしたし、大学入学時は茨城を離れて八戸に向かう新幹線のなかで涙を流した。
「そういうこと(高校や大学の寮生活)も含めて自分が好き好んで、その道を選べていたら、プロになれたのかもしれないですが……。そこが自分のなかで欠けていた部分だったし、弱さというか、それが後悔かと言われたら後悔かもしれないです。小さい頃からプロを目指して野球をやっていたから、プロに行けなかった悔しい気持ちはもちろんあります。でも、プロに行って失敗してしまった時のことを考えてしまう弱い自分もいました。もちろんそれも自分次第なのはわかっています。ただ、野球のほかに何ができるのかと言われたら本当に当時は何もなかったので……。『このまま野球だけ続けていっていいのか』という迷いもあったし、先のことまで考えてしまう自分もいたんです。結局、自分自身が中途半端な人間だっただけの話なんですけどね」
プロに入って2、3年でクビになる選手を数多く見てきた。高校時代、勝田としのぎを削った春田剛(水戸短期大学附属高校→中日)も入団後はケガに泣き、わずか2年で現役を引退した。それだけ生き残りが厳しい世界である。当然、勝田が言うように「中途半端な人間だった」の一言で片付けられるわけがない。
「みんなが遊んでいる時に練習をしてという生活を続けてきたので、学生の頃の思い出は何もないんですよね。当時は『遊ぶことは大人になってからいくらでもできる』とか言われましたけど、若い時にしかできないこともあるわけじゃないですか。そう思っていたのが当時の自分なので、そこが甘さだったんだなって思います」
そんな自分を断ち切るため、3年前からキックボクシングを始めた。
「スポーツで生きてきた人間だったので、どうせなら体を動かすのがいいかなと思って。その時にふと格闘技を思いついたんです」
ジムの代表を務める初代WFCAムエタイ世界ライト級王者の桜井洋平会長とのスパーリングでは、これまで感じたことがないくらいの痛みや衝撃を感じることもあったという。同時にプロのリングに立つ怖さも徐々に感じている。
「もちろん怖さはありますよ。本当だったら、会長も今の自分の技術では試合に出させたくなかったと思うんです。昨年の6月にプロテストには受かったけど、プロとしての技術を見せられる試合ができるかって言ったらできないし、まだ体力も全然ないので……。そんななかでもこれまでお世話になった先輩が引退するということを昨年末に聞かされて、自分もそこに華を添えたいというか、試合に出る決心を固めました。自分は先輩の前の試合なので、ジムに勢いをつけるためにも絶対勝ちたいと思っているんです」
その言葉には強い決意が込められていた。32歳という年齢のことは自分が一番わかっている。だから、キックボクシングのチャンピオンになりたいとか、K-1に出たいとか、そういう思いは一切ない。1試合1試合を懸命に戦い、その結果どこまでいけるのか……。
別れ際、勝田はこんなことを言った。
「高校野球は今でも見に行きます。きっと、プロよりも高校野球が好きなんだと思います。あれだけ地元の人たちから応援してもらえるのは、高校野球しかないって思うんです。石岡一高が今年の春、センバツに出るとなった時、街中のいたるところに旗が立てられて。木内監督も『甲子園は人を育てる』って言っていましたけど、本当にそうだと思います。甲子園を経験することで、選手としても人としても成長できるし、人への感謝の気持ちを自然と持てるようになる。甲子園は自分が頑張ってやってきたことをお披露目して、さらに成長するきっかけをつくってくれる場所でした。まさに教育の場でした。
だから、いつか自分が培ってきたもので、茨城はもちろん石岡市に恩返ししたいと考えている。
「格闘技人生が終わったら。また野球に携わることもやりたいと思っています。生まれ育った石岡市で、子どもたちに野球を教える野球塾を開きたいなと思っているんです」
ひとつの夢は終わったが、またひとつの夢が始まろうとしている。