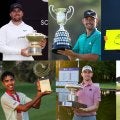2018年の高校野球界は、まさに大阪桐蔭の独壇場だった。全国の高校球児が「打倒・大阪桐蔭」を掲げるなか、史上初とな…
2018年の高校野球界は、まさに大阪桐蔭の独壇場だった。全国の高校球児が「打倒・大阪桐蔭」を掲げるなか、史上初となる同一校による2度目の春夏連覇を達成した。
2000年生まれの選手が多く揃う彼らは”ミレニアム世代”と呼ばれ、2016年春の入学時から注目を集めていた。

甲子園100回大会を制し、史上初となる2度目の春夏連覇を達成した大阪桐蔭
「今はネット社会で、入学前から『根尾(昂)はどうだ』とか『今年の大阪桐蔭はすごいのが揃った』と話題になり、そこへ彼らが最上級生の時に100回大会……そうした盛り上がりもあって、正直やりにくさはかなりありました」
まだ何も始まっていないのに過剰な注目を浴び、大阪桐蔭の西谷浩一監督は世間の騒ぎと目の前の選手たちとの間にキャップを感じていた。
注目の筆頭だった根尾についても、こう語る。
「入学当初の中田(翔)なら、誰が見てもすごいですし、大きく騒がれても仕方ないという気持ちでしたが、根尾の場合はそれとは違う。打者としての力で言うなら、森友哉は飛び抜けていましたが、そことも違う。
もちろん根尾もいい選手ですが、森はほかにいないレベルのバッターでしたから。でもそういうことを言うと、僕が謙遜しているようにとられてしまって……。世間の注目と、とくに下級生時の根尾や藤原(恭大)の実力との間には、まだまだ大きなギャップがありました」
根尾は2年時に春夏連続して甲子園を経験しているが、31打数8安打(打率.259)、0本塁打、7打点。投手としても2試合に登板して3イニングを投げたのみ。
一方の藤原も、1年夏からレギュラーとして出場しているが、2年時の2度の甲子園では37打数7安打(打率.189)、2本塁打、3打点。センバツ決勝の履正社戦で2本塁打を放ちインパクトは残したが、ともに本格的な活躍はこのあとだった。
「根尾については、僕らのなかでは段階を踏んで順調に成長していました。でも、みなさんが思う根尾には達していない。そういう状態が続いていたと思います」
それでも話題は常に先を走り、大阪桐蔭のミレニアム世代への注目度はマックスに膨れ上がった。その期待どおり、新チームは秋の大阪大会を制し、近畿大会も優勝。各地区の優勝校が集う神宮大会にも出場を果たしたが、ここでつまずいた。
「神宮大会でも『大阪桐蔭が優勝するだろう』という空気のなか、選手たちも確固たる自信がなく『勝てるかな』という雰囲気で戦ってしまい、次々とミスが出て、打線もさっぱり。(長崎創成館の前に)何もできないまま終わってしまった。
その日の夜、ホテルの僕の部屋に全員をぎゅうぎゅうに立たせて話をしました。『センバツは出られるだろうけど、このままじゃ強いと言われながら、コロッと負けるぞ。それでええんか』と」
決して周囲の評価に乗り、勘違いするようなチームではなかった。まして1学年上の代は春夏連覇に挑み、実現できなかった。日本一の道がどれだけ険しいかは実感として理解している。ただ、世間の盛り上がり、注目度はあまりにも高い。西谷監督もその部分に関しては選手たちに「そうじゃないぞ。わかってるな」としつこいほど言い聞かせた。
「報道などでは”最強軍団”と言われたりもしましたが、今の力はまったく違うと。寮でミーティングをする時、食堂に寮長が撮ってくれた歴代チームの写真が飾ってあるんですけど、それを見ながら『この年のチームは強かった』『この代も力があった』と。だから『お前たちが最強とは思っていない』という話もしました。
センバツに勝ったあとも『まだオレは世間が言うほど強いとは思っていない。ただお前らが春夏連覇をしたら、最強と言わざるを得なくなる。力を証明したかったら結果で示せ』と言いました。この学年は負けず嫌いな子が揃っていたので、そのあたりを刺激しながら……というのはありました」
西谷監督は常にチームとして目指すべきところを明確に示し、どうすればそこにたどり着けるのかを考え、動いてきた。もちろん目指すべき場所は、いつの時も日本一だ。
「コーチ時代も含め20数年やってきて、言い方はおかしいですけど、毎年食材が違うので料理の仕方は違う。ただ、『いい食材だから日本一おいしい料理をつくろう』ではなく、『毎年日本一を目指す』。ここはぶれていません。藤浪晋太郎がいるから、森友哉がいるから日本一じゃなく、日本一は毎年目指しています。僕はあきらめの悪い人間ですので、この食材でもなんとかならないか、いいやり方があるんじゃないか……いつも頭をひねってもがいています」
今回のチームについては、夏に向かっていくなかで日に日に内面について語ることが増えた。相手を上回る考え方、取り組みをやっていこう、と。それは野球に限らず、寮生活や学校生活も含め、すべてにおいて日本一を目指すことを目標にやってきた。
「このチームは、とくにその部分でキャプテンの中川(卓也)、副キャプテンの根尾というリーダーを中心にしっかりしたものを持っていた。そこを考えた時に思うのが、このチームは1学年上の(キャプテンの)福井(章吾)の代と”ニコイチ”だったということです。兄貴と弟分といった感じで相性がよかった。
福井たちのチームは、下級生が多くレギュラーで試合に出ていましたが、上級生たちはライバル心を持ちながらもやっかむような空気にはならなかった。人間的にもすばらしい先輩たちのなかで中川、根尾らの世代が育まれ、多くのものを早い段階で学んでいくことができたと思います」
キャプテンの福井を中心とした幹部ミーティングに、下級生の中川と根尾も参加。こうしたチームづくりには、西谷監督の明確な意図があった。
「2つの狙いがありました。ひとつは、もちろん次のチームを考えてのリーダーの育成。次の代のチームは中川と根尾が中心になるのはわかっていたので、福井には『ふたりをリーダーとして育ててやってくれ』とお願いしました。
もうひとつは、センバツを勝って夏へ向かうチームを考えた時、僕は2年生の成長なくして大きなレベルアップはないと思っていました。ただ3年生の気持ちもあり、僕の口からは言いづらい。それがある時、福井に『どうやったら夏を勝てると思う?』と聞くと、『3年生はもちろんですけど、2年生が成長することです』と。そこからは中川、根尾を軸に2年生を成長させる……これが夏までのテーマとなりました」
結果は夏の甲子園の3回戦で仙台育英に敗れたが、まさに”ニコイチ”のチームづくりが、2018年の春夏連覇の下地となった。
「年々、寮や学校、グラウンドにいい風土ができてきたと思います。夜、寮に行くと、みんないないのでどうしたのかと思ったら、食堂でミーティングをやっていた。ほかにも、自然と空き時間にバットを振ったり、ストレッチをしたり……上級生の真似からかもしれないですけど、自分たちでこうしようという空気ができ、行動できるようになってきた。そこは頼もしく感じます」
2018年の夏前、キャプテンの中川は次のように語っていた。
「去年のチームを思い返すと、まだまだやり切れていない、甘さがあった。そこを今年はもっと詰めていきたい」
あのチームを見てまだそう言える中川に、どれだけ高い意識を持っているのか……と驚かされた。その話を西谷監督に伝えると、こんな答えが返ってきた。
「そこは去年出ていたから言えることで、ミーティングにも参加して意識も高くなったけど、結果として勝てなかった。いくらやっても負ける時は負けますが、なぜ負けたかということを突き詰めていかないと成長はない。そういう意識が強かったんでしょう。よく僕が言うのは『単純に前のチームのいいところは引き継いで、悪いところは消していこう。そうすればチームは絶対にプラスにいく』と。それをしっかり実践してくれたのが、中川の代のチームだったと思います」
まさに”ニコイチ”でつかんだ2度目の春夏連覇だったのだ。
そしてその後の大阪桐蔭はと言うと……新チームのなかに旧チームからのレギュラーはゼロ。完全にメンバーが入れ替わり、リーダーも不在。予定していた投手陣にも出遅れが続いた。それでも秋の大阪大会で準優勝を果たし、近畿大会もベスト8。よくぞここまでという部分と、粘り切れなかった脆さ。旧チームに比べると、実績、実力、経験……すべてにおいて劣っていると言わざるを得ない。
「冬に腰を据えて、本気で鍛えてまた頑張ります」
西谷監督の言葉を待つまでもなく、チームが目指すのは2019年も変わらない。高校野球界の王者は、また高く険しい山を登り始めた。