西武×ヤクルト “伝説”となった日本シリーズの記憶(11)【同級生】ヤクルト・荒木大輔 前編…
西武×ヤクルト “伝説”となった日本シリーズの記憶(11)
【同級生】ヤクルト・荒木大輔 前編
()
四半世紀の時を経ても、今もなお語り継がれる熱戦、激闘がある。
1992年、そして1993年の日本シリーズ――。当時、”黄金時代”を迎えていた西武ライオンズと、ほぼ80年代のすべてをBクラスで過ごしたヤクルトスワローズの一騎打ち。森祇晶率いる西武と、野村克也率いるヤクルトの「知将対決」はファンを魅了した。
1992年は西武、翌1993年はヤクルトが、それぞれ4勝3敗で日本一に輝いた。両雄の対決は2年間で全14試合を行ない、7勝7敗のイーブン。あの激戦を戦い抜いた、両チームの当事者たちに話を聞く連載の6人目。
第3回のテーマは「同級生」。前回の西武・石井丈裕に続き、今回はヤクルトの荒木大輔のインタビューをお届けする。

1992年の日本シリーズで、一発に泣いた荒木氏
photo by Sankei Visual
「投げられる喜び」を感じていた1992年
――1992年、そして翌1993年の日本シリーズについてお話を伺いたいのですが、まず1992年は、チームが14年ぶりのリーグ優勝。荒木さんが長い故障から復活し、優勝を決めた試合に先発した年でしたね。
荒木 甲子園球場での試合(1992年10月10日)でしたね。阪神にも優勝のチャンスがあったので、球場中が黄色く染まっていたのをよく覚えています。でも、プロになっていろいろな経験をしてきてのマウンドだったので、ほどよい緊張感でした。冷静だったし、古田(敦也)のリードもちゃんと理解しながら、1球、1球、集中していた記憶があります。
――1992年9月24日の1541日ぶりの復活登板以来、チームに勢いがついたように思います。ご自身ではどのように感じていましたか?
荒木 あの日、球場中がざわついていたのは自分でもすごく感じていました。うれしさと楽しさ……いや、楽しいとまではいかないけど、とにかく投げられる喜びを一身に感じてマウンドに上がって、目いっぱい投げ込む。チームが優勝争いをしていて、大事な場面で投げられる喜びを感じていました。
――10月10日にセ・リーグ優勝が決まって、翌週17日には日本シリーズ開幕。どの程度「西武対策」をして臨んだのですか?
荒木 今のように交流戦がない時代だったので、西武打線ひとりひとりについてミーティングをして、特徴を頭に叩き込みました。たとえば、「早打ちなのかどうか」とか、「内と外なら、どちらが強いのか」とか、「セ・リーグで言えば、誰に似ているのか」などですね。
――たとえば、秋山幸二選手、清原和博選手などは、誰に似ているという分析でしたか?
荒木 いや、もう全然覚えていないです(笑)。僕ら投手陣はその程度の対策でしたけど、大変だったのは古田ですよ。シリーズ中はホテルニューオータニで合宿をするんですけど、古田の部屋に行くとビデオデッキがあって、ビデオがずらっと並んでいました。完全に他人任せなんだけど、「キャッチャーって大変だな」って見ていました(笑)。
極端な話、ピッチャーは何を投げたかなんてほとんど覚えていないけど、キャッチャーは1試合全部を覚えていますよね。たぶん、古田は今でも覚えているんじゃないのかな? 後に僕は伊東勤監督の下で西武ライオンズの投手コーチになりますけど、伊東さんの場合も「何回の誰々の何球目についてだけど……」と言うのに対して、僕は手帳を見て、「あっ、あのボールのことか」って感じでしたからね(笑)。
試合後のミーティングで、野村監督に反論

現在は日本ハムの2軍監督を務める荒木氏
photo by Hasegawa Shoichi
――この年のシリーズでは、ライオンズ・石井丈裕投手との、「早実同級生対決」が話題となっていましたが、ご本人としてはどのような心境でしたか?
荒木 やっぱり投げ合いたかったですね。ただ、向こうはすでに西武のエース格だったけど、僕はどちらかと言えばローテーションの6番目とか、谷間に登板するピッチャーだったので、実現するとは思っていなかった。結局、このシリーズでは2試合に先発登板させてもらうけど、一緒の試合で投げることはできませんでした。願いが叶うのならば、投げ合いたいという思いは強かったです。
――この年の石井投手は絶好調でしたけど、同じ投手として彼のピッチングをどのように見ていたのでしょうか?
荒木 とんでもないピッチャーですよ、彼は。だってこの年、3敗ぐらいしかしていないでしょ(15勝3敗3セーブ)。ウチの野手陣に聞いたら、キャッチャー・伊東(勤)さんの傾向もデータで出ていて、ある程度の特徴はつかんでいたのに、「それでも打てない」って言っていましたから。パームボールも、スライダーも、ストレートもみんなよかったし、コントロールも抜群でしたね。
――このシリーズでは第2戦の先発を任されました。初戦は杉浦享さんの代打サヨナラ満塁ホームランという、劇的な勝利を受けての一戦でした。
荒木 「絶対に勝ちたい。絶対に勝つ」という思いでマウンドに上がりました。でも、西武打線は全員が一流選手だったので、「勝てるわけがない」というか、力ではすべてにおいて向こうが上でした。それまで、テレビで日本シリーズを見ていた感覚があったからなのか、打線を見ても、ずらーっとあれだけの選手が並んでいるわけですから。意識したのは「クリーンナップの前には走者は出すな」ということぐらいでした。でも、翌1993年は「負けるわけがない」という思いでしたけどね。
――そんな思いで臨んだ1992年の第2戦。この日の調子はいかがでしたか?
荒木 ものすごく集中できていたし、調子はよかったと思います。
――この試合では6回を投げて、被安打は5、2失点。清原選手に打たれた2ランホームランが決勝点となって、0-2でスワローズは敗れ、荒木さんは敗戦投手となりました。
荒木 清原に打たれたカーブは失投ではなかったと思いますね。今でもよく覚えているのは、この試合の後のミーティングで野村(克也)監督に延々とこの場面の話をされたことです。「あれだけの強打者に対して、ずーっとカーブを続けている……」って言われたけど、清原はこのとき、カーブにタイミングが合っていなかったんです。だから古田もカーブのサインを出したし、僕も迷いなく投げた。
――それでも、野村監督の話は止まらなかった。
荒木 「あれだけカーブを続けたら打たれるだろう、馬鹿野郎」って言われて、僕もカチンときて、「じゃあ、何を投げればいいんですか?」と言い返しましたよ。野村さんに対してそんなことを言えるなんて、自分でもすごいなって思うけど。いくらタイミングを崩したとはいえ、結果的にホームランを打たれているのにね(笑)。古田もすごく怒られていたので、申し訳ないことをしましたね。
プロの世界では「酷使」も、やむを得ないこと
――1992年のシリーズでは、ライオンズの3勝2敗で迎えた第6戦の先発も任されました。このときは中6日での登板でしたね。
荒木 王手をかけられているというプレッシャーは感じなかったけど、この日の調子はあまりよくなかったですね。身体が重いというのか、モワーッとしたような感じで。だから、「投げミスをしないように」という意識でマウンドに上がったけど、結局、石毛(宏典)さんにホームランを打たれてしまった。
――4回表、五番・デストラーデ選手にヒットを打たれた後、石毛選手にライトに運ばれ、この回で降板となりました。
荒木 デストラーデのヒットはカーブの曲がりが小さくて、そこを打たれました。そして、石毛さんにはシュートを投げたのがスライダー回転して甘めにフワッと入ってきたところを見事に追っつけて打たれたっていうのが、すごく記憶にありますね。シリーズ中に気を抜いて投げるピッチャーなんていないんで、やっぱり疲れのせいなのか、本来の調子ではなかったのは間違いないです。
――この試合は秦真司選手のサヨナラホームランが飛び出して、延長戦でスワローズが勝利。3勝3敗のタイにしますが、翌日の第7戦で敗れて3勝4敗で涙をのみました。この年のシリーズを振り返ると、どんな印象がありますか?
荒木 下馬評では「西武有利」と言われていましたよね。でも、3勝4敗と接戦だったことで、「オレたちもやれるんだ」という自信が芽生えたのは確かです。それが1993年のセ・リーグ制覇につながったんだと思います。選手がみんな20代半ばで若かったですよね。当時、28、29歳ぐらいだった僕が年齢的には上の方でしたからね。
――この年のシリーズでは岡林洋一投手が、第1戦、第4戦、そして第7戦に先発。いずれも完投して、3試合で30イニングを投げています。岡林さんについては、どのように見ていましたか?
荒木 大エースですよ。アイツは絶対に弱音を吐かないし、本当にチームのことを考えられる男でした。野村さんの考える「エース像」、そのままの投手が岡林でした。責任感が強いからこそ、あそこまで投げ続けて結局は肩を壊してしまった。でも、ああいうピッチングをしたから、岡林は今でも評価されているわけですよね。もしも、このシリーズで2試合だけ投げていたら、ここまで評価が上がることもなかったはずです。
――翌1993年のルーキー・伊藤智仁投手のケースも含めて、しばしば「野村監督の酷使」が話題になりますよね。
荒木 僕らはアマチュアじゃないので、プロの場合は仕方ないことだと僕は思っています。仕事ですから。「連投したから、今日は休み」っていうのは、日本シリーズではあり得ないんでね。
(後編に続く)




































































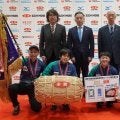



![アルカラス、難敵ポールを退け3年連続の8強進出!史上最年少の生涯グランドスラムに邁進[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012516260245513700.jpg)



