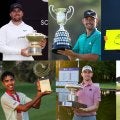打率.275(リーグ15位)、16本塁打(同18位)、80打点(同9位)――。 今季の数字だけを見ても好打者ぶりが…
打率.275(リーグ15位)、16本塁打(同18位)、80打点(同9位)――。
今季の数字だけを見ても好打者ぶりが伝わってくるが、捕手というポジションを考慮すると、その成績が一層光って見える(今季の成績は10月8日時点)。

正捕手としての地位を着実に固めつつある森友哉
高卒5年目の2018年シーズン、西武の森友哉は捕手として74試合、指名打者で49試合に先発出場し、10年ぶりの優勝の立役者になった。
球界の”絶滅危惧種”となりつつある「打てる捕手」の価値は、パ・リーグのキャッチャー陣と打撃成績を比べるとよくわかる。そもそも規定打席に達する捕手は田村龍弘(ロッテ)のみで、打率.241。本塁打と打点はリーグのトップ30位に入る者さえいない(※日本ハムの近藤健介は捕手登録だが、今季1度も捕手として出場していないので除外)。森は指名打者としての出場も3~4試合に1度ほどあるが、逆に打力の高さを示している。
「本当に『いいキャッチャーだな』って言われるようになるには、どんなにいい選手でも3年〜5年はかかります」
森を二軍時代から指導してきた秋元宏作バッテリーコーチは、ルーキーイヤーの夏にそう話していた。当時はピッチングマシーンの球を捕るという地味な練習を繰り返し、キャッチング技術を磨いた。キャッチャーにとって捕ることは原点で、そこから送球、リードにつながっていくからだ。
あれから4年が経った今季、森は74試合と西武でもっとも多く先発マスクをかぶった。球界トップクラスの守備力を誇る炭谷銀仁朗が41試合、大阪桐蔭の先輩でもある岡田雅利が28試合と両者を押しのけた格好だ。森は一軍で実戦経験を重ねることで、捕手として実力に磨きをかけたと秋元コーチは語る。
「練習でやってきたことをゲームでできるようになり、全体的にレベルアップしていると思います。リード面に関してはまだおっかなびっくりなところはあるけれども、そのなかであいつ自身が感じられることが増えてきているので。去年まではシーズン終盤の順位が決まったときに守っていたけど、今年は開幕からチームが首位にいるなかでマスクをかぶって、メンタルの成長も大きかったと思います」
9月15日、ゲーム差3.5で迎えた2位・ソフトバンクとの3連戦初戦がメットライフドームで始まる約5時間前、森は山川穂高とともに真っ先に戦いの場に現れた。同期入団のふたりは誰より早くグラウンドにやって来て、入念にウォーミングアップするのを本拠地でのルーティンワークとしている。
多くの時間をともにする山川が、チームのMVPとして挙げたのが森だった。
「僕は森が一番、苦労したと思っていますから。活躍したというより、苦労した人がMVPになるべきだと僕は考えます」(『週刊ベースボール』2018年10月15日号より)
苦労とは、捕手としての守備面を指している。たとえば優勝の行方を大きく左右する上記3連戦初戦で、ソフトバンクはエース・千賀滉大を先発に立ててきたのに対し、西武は3年間未勝利の郭俊麟(クォ・ジュンリン)に託した。誰が見ても、ホームチームは苦しい戦いを強いられそうだ。
今季の西武は先発投手によって捕手を使い分けるなか、郭の今季2度目のマウンドでコンビに指名されたのが森だった。初回に3点リードをもらうと、森は大胆なリードを見せていく。4番の柳田悠岐に対してカーブを2球続けたり、内角にチェンジアップを要求したりするなど、「緩い球」で積極的に攻めながら、郭を5回3失点と好リードして勝利に導いた。
カーブやチェンジアップは甘く入れば長打になりやすい球種だが、信頼度が高いから、ストレートを見せ球にするような組み立てをできたのだろうか。
「信頼度というよりも、バッター陣がまずストレートに照準を合わせて来ているなと感じていたので。カーブなり、チェンジアップでカウントを取れれば有利ですし。そうなると真っすぐ1本に絞るのはなかなか難しくなると思うので、いつもより少し多く使ったかなという感じです」
リードは捕手の個性が表れるから面白い。たとえば炭谷は「この球でアウトに取ろう」というストーリー性や計算力を感じさせ、岡田は投手のよさを引き出すのに長けている。
対して森は、打たれることを恐れず、大胆に攻めていける強さがある。ソフトバンクとの大一番が象徴的で、緩急を活かして郭をリードした。しかも相手は千賀で、3連戦のカード頭だ。捕手として得るものが大きかったのではないか。
「キャッチャーとしてというよりも、チームとして、首位攻防戦の1戦目にああいう形で勝てたのは大きいですね」
思わず質問を自省するほど、チームでもっとも多くマスクをかぶっている男のプライドを感じさせられる言葉だった。
今季は捕手として計81試合に出場し、パスボールはリーグで3番目に多い5個(楽天の嶋基宏が最も多く、112試合で9個)。秋元コーチの言うように、疑問の残る配球もある。
だが、キャッチングは目に見えて向上し、盗塁阻止率は甲斐拓也、髙谷裕亮(ともにソフトバンク)に続いてリーグ3位だ。なによりマスクをかぶることで、森はリード面の財産を蓄積させている。9月27日のソフトバンク戦の前には、こう話していた。
「シーズンを通してやっていると、相手の苦手なコースなどは、ひととおり頭に入っているつもりなので。そこは大きいかなと思います」
捕手としての配球力は、打席での力にもなっている。この試合で0−0の2回無死から栗山巧、中村剛也が連続四球で歩いた後の初球、バンデンハークが内角高めに投じた147kmのストレートを豪快なスイングでライトスタンドに突き刺した。
「フォアボール、フォアボールの後、(捕手とすれば)初球は取りにいきたいものですし。ピッチャー心理からしてもストライクをほしい場面なので、初球からいこうと決めていました。ストレート待ちでしたね」
森は基本的に球種やコースを読まず、「来た球を打つ」タイプだ。「読みが外れると打てないから」と、その理由を話していたことがある。
しかし今は、読んで打つケースも増えてきた。リーグ6位の得点圏打率.341という勝負強さは、そうした点と無関係ではない。森の打力からすれば今季の打率、本塁打、打点ともに満足できるものではないだろうが、キャリアハイを大きく更新する70四球(リーグ5位)は大きな成長だ(次点は2015年の44個)。
「打てる捕手」としてアピールし、森はチームでの地位を自らの手で高めていった。今季序盤、榎田大樹やウルフは炭谷と組み、今井をリードするのは岡田だったが、いずれも途中から森がマスクをかぶっている(シーズン後半、榎田は炭谷に)。リーグワーストの防御率4.24の西武は打ち勝つ戦い方を重視し、自然と森のスタメンが増えた。
存在感をグンと高めた今季、最後に残された注目点がある。シーズン終了後にポスティングシステムでメジャーリーグ移籍が濃厚な菊池雄星と、バッテリーが実現するのかだ。8月中旬、秋元コーチは森と組む可能性について、「そういう姿をみんな見てみたいと思う」と話している。
10月17日に開幕するクライマックスシリーズのファイナルステージでは、これまでどおりに炭谷が起用されるだろう。日本シリーズまで勝ち進むと、菊池が先発濃厚な初戦はセ・リーグ本拠地で開催されるため、指名打者制度は採用されない。ただ、炭谷が組むのではないか。
可能性があるとすれば、2勝3敗で迎えた場合の第6戦だ。後がなくなり、森の打力で勝負をかける可能性は決して少なくない。
もちろん、「みんな見てみたい」バッテリーが実現するには、チームが日本一を決める舞台まで勝ち進むことが大前提となる。そのカギを握るひとりが、「打てる捕手」の森自身だ。