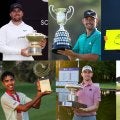西武×ヤクルト “伝説”となった日本シリーズの記憶(9)【同級生】西武・石井丈裕 前編() …
西武×ヤクルト “伝説”となった日本シリーズの記憶(9)
【同級生】西武・石井丈裕 前編
()
四半世紀の時を経ても、今もなお語り継がれる熱戦、激闘がある。
1992年、そして1993年の日本シリーズ――。当時、”黄金時代”を迎えていた西武ライオンズと、ほぼ80年代のすべてをBクラスで過ごしたヤクルトスワローズの一騎打ち。森祇晶率いる西武と、野村克也率いるヤクルトの「知将対決」はファンを魅了した。
1992年は西武、翌1993年はヤクルトが、それぞれ4勝3敗で日本一に輝いた。両雄の対決は2年間で全14試合を行ない、7勝7敗のイーブン。あの激戦を戦い抜いた、両チームの当事者たちに話を聞く連載の5人目。
「参謀」に続く第3回のテーマは「同級生」。今回は、西武の石井丈裕のインタビューをお届けする。
1992年に沢村賞、日本シリーズMVPに輝いた石井丈裕 photo by Kyodo News
荒木大輔と投げ合うことが嬉しかった1992年シリーズ
――早稲田実業高校時代の同級生・荒木大輔投手を擁するスワローズと、ライオンズが激突した1992年、1993年の日本シリーズから四半世紀が経過しました。
石井 人間というのは勝手なもので、いいことは覚えているんですけど、悪いことは忘れやすいですよね。1992年は一応、シーズンで活躍できて日本シリーズでも優勝し、シリーズMVPもいただいた。だけど、1993年は主力として起用してもらったのにシーズン後半は体がボロボロで、本当にキツかったという印象しか残っていません。
――1992年の日本シリーズは、荒木投手との比較から「同級生対決」と騒がれました。ご本人はどんな意識だったのですか?
石井 「特別な意識はなかった」と言えばウソになりますね。やはり、僕自身も試合で投げる以上、「彼にもいいところを見せたい」という思いはありました。
――高校時代は荒木投手がエースとして大活躍して、日本中の注目を浴びていました。一方の石井さんは、当時は控え投手でした。その辺りについての意識はいかがですか?
石井 当時は、そのこともよく言われていたけど、その点についてはあまり意識していなかったです。高校時代、僕は二番手だったけど、僕を含めたみんなが「大輔のおかげで甲子園に連れていってもらった」って考えていました。それは当時の和田(明)監督の指導がよかったんだと思うけど、みんなが「自分のこと」よりも「チームのこと」を優先していましたから。
――その和田監督が亡くなったのが1992年のことでした。そして、この年は荒木投手が、長いリハビリ生活を経て復活を果たした年でもありますね。
石井 彼が約4年ぶりに復活登板したその日(1992年9月24日)のことは、今でもよく覚えています。家に帰って、スポーツニュースで大輔の復活登板を知ってすぐに、彼に電話をしたんです。
――その一連の経緯は、荒木さんの書籍にも書かれていました。古い番号しか知らなかったから、荒木さんの実家に電話をして、新しい番号を調べたそうですね。
石井 そうです。それまでずっと連絡を取っていなかったから、高校の住所録を取り出して彼の実家に電話をかけて、お母さんに大輔の電話番号を聞いて電話をしました。「大輔が投げた」ということで、興奮していても立ってもいられなかったという感じですね。だって、テレビで知ったときに鳥肌が立ちましたから。
――どんな思いでその電話をかけたのですか?
石井 純粋にうれしかったんです。肘や肩というのはピッチャーの生命線ですよね。そこを故障して4年間もリハビリを続けることは、本当にキツいことだったと思うんです。それを乗り越えて復活したというのは、「同級生として」という思いもあったけど、「同じ投手として」という思いもあって喜びが込み上げてきたんです。彼がリハビリを続けている間は、何となくこちらからは連絡ができなかった。でも、このときはうれしくて電話をかけましたね。
複雑な思いで、荒木のピッチングを見ていた

当時を振り返る石井氏
photo by Hasegawa Shoichi
――あらためて1992年日本シリーズについて伺います。この年の石井さんは第3戦、そして最終第7戦に先発登板しています。まずは第3戦のことから教えてください。
石井 先発を告げられたのはシリーズが始まる前の合宿のときでした。この年は年間を通じて活躍させてもらったので、「この成績に恥じないように、とにかく日本シリーズでも頑張ろう」という気持ちが強かったですね。
――この年の石井投手は15勝3敗3セーブという好成績でした。初戦が渡辺久信投手、第2戦が郭泰源投手、そして第3戦が石井投手。森祇晶監督の本によると、「第3戦は第7戦を任せられる投手を起用する」と書かれています。実際に第7戦にも先発登板をしていますが、そういう説明は事前に受けていましたか?
石井 いいえ、特に聞いてはいません。当時の僕は自分のことでいっぱいいっぱいで、「とにかく、任された試合をしっかり投げよう」という気持ちだけでしたね。この年、僕はプロ4年目なんですけど、それまでに1990年、1991年と日本シリーズに出場していました。でも、この2年間はいずれもリリーフ登板で、先発を任されたのは1992年が初めて。ずっと「先発したい」と思っていたので、”待ちに待った”という感じでした。
――石井さんが登板する第3戦に先駆けて、スワローズは第2戦で荒木投手を先発に起用しました。この試合はどんな心境でご覧になっていたんですか?
石井 僕は第3戦の登板が決まっていたので、この日は上がりで、神宮球場のトレーナー室でマッサージを受けていました。本当に複雑な心境で見ていましたね(笑)。正直なことを言えば、この日の大輔は全盛期と比べるとボールのスピードが落ちていました。それでも、シュート系の球とカーブをうまく使って、当時パ・リーグ随一の西武打線を抑えているのを見て、「いろいろ考えて投げているな」と感心していました。
――その試合は、清原和博選手に2ランホームランが飛び出して、ライオンズが2-0で勝利。荒木投手は6回2失点で降板し、敗戦投手になりました。
石井 チームとしてはいい結果なんですけど、複雑……本当に複雑でしたね。でも、打たれはしましたけど、彼のピッチングを見て「本当に復活したんだな」と、うれしかったことを覚えています。
第3戦は清原和博の言葉に救われた
――そして、いよいよ第3戦を迎えます。この日のコンディションはいかがでしたか?
石井 そんなに悪くなかったんですけど、この日7回表に広澤(克実)さんにソロホームランを打たれるんです。このときに、ものすごくカリカリしたことと、それを敏感に感じ取ったファーストの清原くんがマウンドまで来てくれて、「落ち着いて、落ち着いて」と声をかけてもらったことをよく覚えています。
――当時の記事を読むと、石井投手は「基本的には温和で優しい性格だけど、マウンド上では意識して、闘争心を掻き立てている」と書いてありましたが。
石井 温和で優しいかどうかは自分ではわからないけど、どうしてもバッターを攻め切れない部分があったので、自分で気持ちを高めて、アグレッシブにいくようにはしていました。でも、清原くんのひと言で冷静になれましたね。この時点で2-1でしたけど、「冷静になって、行けるところまで行こう」と思っていました。
――結局、この日は9回を1失点で完投して、見事に勝利投手に。対戦成績を2勝1敗としました。
石井 1勝1敗のタイだったということはもちろんわかっていたけど、正直、そこまでの余裕はなくて、「とにかく自分の力を発揮しよう」という思いだけでしたね。それがチームの勝利にもつながるし。
――そして、この試合の終了後に第7戦の先発を告げられたんですよね?
石井 僕はもともと、「第7戦は(郭)泰源が先発して、僕はリリーフなのかな?」って思っていました。でも、第2戦でピッチャーライナーが当たって、「もう泰源は投げられない」となったことで、僕が先発することになりました。チームとしては一試合でも早く日本一が決まったほうがいいんだけど、個人的には「第7戦で投げたい」という思いも強かったです。
――3勝1敗で王手をかけたものの、第5戦、第6戦ともスワローズが驚異的な粘りを見せて逆王手。第7戦までもつれ込みましたね。
石井 正直言って、第3戦の登板はそこまでプレッシャーはなかったんです。自分のことだけ考えていたので。でも、第7戦は違いましたね。第5戦、6戦の負け方がよくなかったし、3勝3敗のタイだったということもあって、プレッシャーが全然違いました。ヤクルトには勢いがありましたから、なおさらでしたね。
(後編に続く)