2017年引退特集加地亮インタビュー(前編)今季終了後、現役から退いた加地亮 自分自身の中でだけ”ラスト…
2017年引退特集
加地亮インタビュー(前編)

今季終了後、現役から退いた加地亮
自分自身の中でだけ”ラストマッチ”と決めていた、J2リーグ最終節(11月19日)のアビスパ福岡戦。試合前に、監督やチームメイト、クラブにその決意を伝える考えは微塵もなかったという。シーズン終盤は、ベンチを温める時間が続いていたことを思えば、当然ピッチに立てずに試合を終えることも覚悟のうえで、だ。
頭にあったのは、いつものように先発のピッチに立つために自分のすべてを注ぎ込んで準備することのみ。そのうえで、監督に必要とされるか、されないかの判断を待ちたかった。
「僕の『引退』という決断によって、監督の考えが揺れてほしくはなかったし、自分自身も温情をかけられてピッチに立つつもりはなかった。これまでどおり、仲間とポジションを競い、試合に出場すること、勝つことを目指す。試合終了のホイッスルが鳴るまで、本当にそのことしか考えていなかった」
そして――。ファジアーノ岡山のDF加地亮は、20年のプロサッカー選手としてのキャリアを締めくくるラストマッチを、ベンチで終えた。
サッカーに注ぎ込んだ毎日を
1年間続けられる自信がないのなら
引退するべきだと考えた
『引退』の文字が、加地の胸の内で渦巻くようになったのは10月の中頃だったという。きっかけは、J2第34節(9月23日)のカマタマーレ讃岐戦だった。ケガから復帰し、13試合ぶりに先発のピッチに立ったものの、どこかしっくりとこない。
「自分の思う感覚に、体がついていかない」
当初は、それが長く戦列を離れたことによる”試合勘のなさ”だと考えていたが、讃岐戦以降も3試合続けて先発出場しても、感覚のズレが戻ってくる気配すら漂ってこない。
それでも、契約をあと1年残していたこともあってだろう。練習に熱を注ぐことで、浮かんでくる『引退』の二文字に蓋をしようと考えたが、その感覚は時間の経過とともに大きく膨らんでいく。
その事実に目を瞑(つぶ)ることができず、彼は2017シーズン限りでの現役引退を決断した。
「契約を1年残していたこともあり、また11月頭には何かを察したのか、珍しく長澤徹監督に呼び出され、『来年も一緒にがんばろうな』と言ってもらったこともあり、引退か現役続行か、何度も考えが行き来しました。でも、これまでやってきたことを、本当にもう1年やり抜けるのかと自分に問いかけたときに、『イエス』とは言えなかったというか……。
1〜2カ月ならやれたはずだけど、サッカー選手は”1年”で考えなければいけないし、その”1年”に含まれるのは、単に練習をして、試合を戦うことだけではないですから。むしろ、それ以外のところでいろいろなことに気を使わなければいけないし、それを実行するには責任と覚悟もいる。
特に僕の場合は、オフ・ザ・ピッチでのさまざまなケアがあってこそ、成り立っていた現役生活でしたから。『自分が思い描く』プレーのために、ピッチの内外でサッカーに注ぎ込んだ毎日を1年間続けられる自信がないのなら、引退するべきだと考えました」
その言葉にもあるように、加地のプロサッカー選手としてのキャリアはピッチ内外における徹底した自己管理に支えられてきた。
練習前には誰よりも早くクラブハウスに到着し、湯船に浸かって体を温める。そのあとは、時間をかけて体の隅々まで念入りにケア。そうして準備を整えたうえで、チームの練習に臨む。そのストイックさはサッカー界でも有名で、20年の現役生活のうち8年間を過ごしたガンバ大阪では、「加地より早くクラブハウスに到着した選手はいない」という伝説が残っている。
初めての海外移籍を実現したアメリカ・メジャーリーグサッカーのチーヴァスUSAでも、そのルーティンは変わらなかった。移籍当初、クラブハウスに湯船がないと知ると、子供用の大きめのビニールプールを持参してお湯を張り、湯船の代わりにしたこともあった。そんな加地のことを、周りの外国人選手は「アメージング」だと笑ったが、「まったく気にしていなかった」と加地は言う。
当時、ロサンゼルスの地で彼が話していた言葉が蘇る。
「アメリカの人たちは湯船に浸かる習慣も、人前で裸になる習慣もないですから。お風呂に浸かる=プールに入る感覚なのか、僕を真似て(湯船に)入ってくる外国人選手は常にスパッツを履いていました。おかげで、僕だけがすっぽんぽん(笑)。しかも、日本では当たり前だと思っていた裸でお湯に浸かり、歯を磨く僕の姿を見て、爆笑していた選手も大勢いました。
でも、まったく気にならなかったです。若いときならもう少し周りの目を気にしていただろうけど、今は『自分は自分』という感じで何を言われても平気。キャリアを積んで自分を貫けるようになったと言えば聞こえがいいけど、単に30歳を過ぎて図太くなっただけかも(笑)」
大分での2年間は僕にとって
かけがえのない時間。
プロサッカー選手としての基盤ができた
そんなふうにして、加地が体のケアに力を注ぐようになったのは、プロサッカー選手としては初期の時代、彼の言葉を借りれば「苦しみまくっていた」という1998年からの4年間の経験によるものだ。
1998年、セレッソ大阪でプロキャリアをスタートさせたが、滝川第二高校時代から、体も華奢で、フィジカルで勝負する選手ではなかった加地。そのため、加入直後から「僕のフィジカルでは、プロの世界で通用しない」という考えが頭をもたげ、苦しむようになる。
実際、試合に出場してもフィジカルの差を痛感することが多く、自信のあった”スピード”さえも鳴りを潜(ひそ)めていった。
「高校時代はスピードで勝負できたけど、プロの世界は基本的にみんな走るのが速いし、身体能力も高い。筋トレをするくらいでは、周りに追いつけないし、自分らしいプレーもできない」
その状況を打開しようと考えたのは2000年、J2の大分トリニータへの期限付き移籍を決断したときだ。
J2というカテゴリーも含め、加地にとってその選択は簡単なものではなかったが、「このままだと早々にプロサッカー人生が終わってしまう」という危機感のほうが勝ったのだろう。また、当時大分の指揮官だった石崎信弘監督が”育成”に定評があったことが、決め手になった。
「大分での2年間は、僕にとってかけがえのない時間になりました。『J2リーグでしっかり戦えないようでは、僕のプロ人生は終わってしまう』という危機感も自分を奮い立たせていましたが、その中で、石崎監督の半端じゃないキツさの練習メニューに鍛えられ、かつ、プラスアルファのトレーニングを取り入れながら、年間44試合という長丁場のリーグ戦をコンスタントに戦えたことで、プロサッカー選手としての基盤ができた」
そうした基盤をしっかりと作れたことで、以降のサッカー人生は一気に好転し、加速していく。
(つづく)
加地亮(かじ・あきら)
1980年1月13日生まれ。兵庫県出身。2006年ドイツW杯に出場するなど、日本代表でも活躍したサイドバック。滝川第二高校→セレッソ大阪→大分トリニータ→FC東京→ガンバ大阪→チーヴァスUSA(アメリカ)→ファジアーノ岡山







































































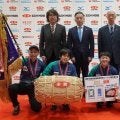



![アルカラス、難敵ポールを退け3年連続の8強進出!史上最年少の生涯グランドスラムに邁進[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012516260245513700.jpg)



