元広島・紀藤氏が振り返る1991年のリーグ優勝 1991年シーズンは山本浩二監督率いる広島がセ・リーグを制覇した。紀藤真…
元広島・紀藤氏が振り返る1991年のリーグ優勝
1991年シーズンは山本浩二監督率いる広島がセ・リーグを制覇した。紀藤真琴氏(株式会社EJフィールド代表取締役)は当時、プロ8年目の右腕でVメンバーの1人だ。ほとんどが中継ぎで36登板、3勝3敗、防御率4.44の成績。プロ5年目からは毎年フル回転しており、コンディションは万全ではなかったが、与えられた場面で懸命に投げた。泣き言は言わなかった。弱気にはならなかった。先輩のことを思えば……。その一心だった。
プロ8年目の紀藤氏は、開幕3戦目の4月10日の中日戦(ナゴヤ球場)での中継ぎ登板からスタートした。当時の中継ぎは複数イニングを投げるのが当たり前で、この年も1イニングで終わるのが珍しいくらいの使われ方だった。「もう大変でした。終盤に優勝のチャンスが出てきたら首脳陣からやっぱりムチも入るわけですけど、自分の場合は(それまでにも)何年も投げてきましたからね……」と振り返った。
この年のセ・リーグは、星野仙一監督体制の中日がトップを走っていたが、広島が9月に入ってひっくり返した。9月10日からの中日3連戦(ナゴヤ球場)に3連勝して首位に立ち、その勢いをキープして、10月13日の本拠地広島市民球場での阪神とのダブルヘッダー第2試合に1-0で勝利し、5年ぶりのリーグ優勝を決めた。
その間に紀藤氏も中日を突き放すべく、フル回転でチームを支えた。9月18日からのヤクルト3連戦(広島)では3連投リリーフ。19日の2戦目は0-1の9回に2番手で登板し無失点に抑えると、その裏、西田真二外野手が逆転サヨナラ2ランを放ち、勝利投手になった。さらに3連投目の20日は、1-1の4回から2番手で5イニングを投げるロングリリーフで無失点。打線が勝ち越して、2試合連続の勝利投手となった。
「3連投目に5回を投げるなんて、なかなかいないですよね。もう疲弊しちゃって。自分の体が壊れちゃう寸前までやっていた感じでしたね」と紀藤氏は苦笑する。優勝が決まった10月13日の阪神戦も、延長10回の末、2-3で敗れたダブルヘッダー第1試合に3番手で4回1/3、無失点のロングリリーフをこなした(敗戦投手は9回から登板の金石昭人投手)。その日の第2試合で優勝が決まったが「祝勝会とか印象に残っていない。とにかく疲れちゃっていて、それどころではなかった」と明かした。
特別な存在だった“炎のストッパー”「だから頑張れた」
しかし、どんな状況に陥っても弱音は吐かなかった。「津田(恒実)さんだったら、こんなところで痛いといっても、気持ちで克服して投げるんだろうな、とか、いつも考えていましたからね」。赤ヘルの“炎のストッパー”として一世を風靡した津田投手は、1991年4月14日の巨人戦(広島)を最後に、病のため戦線を離脱した。悪性の脳腫瘍だった。この年の逆転Vは、広島ナインが“津田のために”との思いで成し遂げたものだが、紀藤氏にとっても5歳年上の津田氏は特別な存在だった。
「(入団当初から)よく叱咤激励していただきました。ダラダラしたピッチングをしたら『ちゃんと投げぇよ! お前は』って怒られましたし、津田さんの影響というのは大きかったです。自分の体のことも気にかけてくれて、いい病院を紹介しようか、なんてよく言われました」。1993年7月20日に32歳の若さで亡くなった津田氏の座右の銘「弱気は最大の敵」は紀藤氏にも響いた。「だから頑張れたというのもあるんです。津田さんはもっと投げたかったでしょうから……」。
3勝4敗で敗退した西武との日本シリーズでの紀藤氏は、第1戦(10月19日、西武)で石毛宏典内野手に満塁弾を浴び、第6戦(10月26日、西武)では秋山幸二外野手に3ランを被弾するなど、結果を残せなかった。「もう球が走っていませんでしたね」。もちろん、それもバネにするつもりだったが……。翌1992年は右肘痛に悩まされ、オフに手術した。また乗り越えなければならない試練の時がやってきた。(山口真司 / Shinji Yamaguchi)













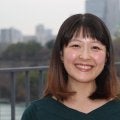

























































![アルカラス、デミノーを破り全豪で初の4強入り!準決勝で世界3位ズベレフと激突[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012722260253640600.jpg)






