日本サッカーは「右肩上がり」の成長が続いている。男女の代表チームや欧州での個々の活躍が目を引くが、そのベースにあるのは…
日本サッカーは「右肩上がり」の成長が続いている。男女の代表チームや欧州での個々の活躍が目を引くが、そのベースにあるのは「選手育成」の充実だろう。サッカージャーナリスト後藤健生が、日本サッカー界の未来を照らす「才能」たちに目を向ける!
■新世代の目に映る「現代サッカー」
さて、15歳以下の選手の大半は2010年または2011年の生まれである。
1952年生まれの僕とは、実に、60年近い年齢差がある。冗談抜きで、「彼らが引退する頃まで自分は生きていられるだろうか……」と思わざるを得ない。
彼らが生まれ、物心がついた頃には2018年のロシア・ワールドカップが行われていたはず。「日本がワールドカップに出場したことがなかった時代」どころか「日本がグループリーグを勝ち抜けなかった時代」すら知らない世代なのだ。
高円宮杯の決勝の舞台となった味の素フィールド西が丘は、日本でも最高の芝生が存在する。なにしろ、スタンドが小さいから日照時間も十分で芝生の育成にはもってこいの環境なのだろう。
当然、彼らは、あるいは決勝戦と同時開催となっている「高円宮妃杯JFA第30回全日本U-15女子選手権」決勝戦に出場している彼女らは、冬場になるころには芝生が禿げあがって砂埃が舞い上がっていた時代の西が丘など想像もできないだろう。
彼ら、彼女らの目には、サッカーというスポーツはどういうように映っているのであろうか?
■12歳の選手が見せた「衝撃プレー」
女子の決勝戦は、INAC神戸テゾーロ対三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースという対戦だった。WEリーグの首位争いをしているクラブの下部組織同士の対戦ということもあって、かなり多くのサポーターが詰めかけていた(観客数は男子決勝の1196人に対して、女子決勝は841人)。
試合は、ほぼ互角ながら守備力の差があって、浦和がやや優勢に進めていたが、21分にスローインからのこぼれ球をI神戸の青木唯奈がミドルシュートで決めて神戸がリードして折り返した。
すると、浦和は後半開始から交代のカードを切ってきた。
左サイドバックとして登場したのは小林花音。メンバー表を見ると、2013年1月生まれの、なんと12歳の選手だった。
年齢を見てびっくりしていたが、攻撃力アップのために投入されたのがうなずけるように攻撃参加がうまい選手だった。
攻撃参加といっても無闇に上がっていくのではなく、タイミングの見極めが良いから非常にスムーズな動きで効果的な位置でパスを受けられるし、裏を取られることも少ない。いわゆるオーバーラップとアンダーラップ(インナーラップ)を使い分けて、うまいポジション取りができている。
Jリーグが開幕した頃、「サイドバックの攻撃参加」といったら、タッチライン沿いにドリブルで上がって行ってクロスを入れるだけだった。
■イギータのプレーは「当たり前」?
今のように、サイドバックがインサイドMFとしてプレーしてみたり、いわゆる「レーン」を意識しながら、アウトサイドの選手と被らないような位置を取ったりするようになったのは、せいぜい10数年前からのことだ。
バイエルン・ミュンヘンでフィリップ・ラームがサイドバックとインサイドMF、インサイドハーフなど複数ポジションをこなしているのを見てビックリしたのがちょうど10年ほど前。Jリーグでは、アンジェ・ポステコグルー監督の横浜F・マリノスでサイドバックの攻撃参加に目を見張ったものだが、それもわずか7年前のことだ。
だが、今のU-15世代の選手たちにとっては、初めてサッカーを見たり、プレーしたりしたときにはそういうサッカーが普通に行われていたわけである。
GKがペナルティーエリアから出て、パス回しに加わるなどというプレーも、革新的なものだった。レネ・イギータ(コロンビア)がワールドカップという舞台で、そんなプレーを披露して世界を驚かせたのは1990年のイタリア・ワールドカップでのことだった。
今では、15歳のGKはそんなプレーを当たり前だと思っている。
なにしろ、彼ら、彼女らは、そういったプレーを見て育ち、初めからそういうプレースタイルを指導されているのだ。そして、映像があふれかえっている21世紀の今日、彼ら、彼女らは世界トップのプレーの動画をいくらでも観ることができるわけだ。






































































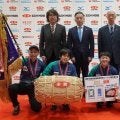



![アルカラス、難敵ポールを退け3年連続の8強進出!史上最年少の生涯グランドスラムに邁進[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012516260245513700.jpg)



