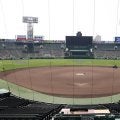3勝を挙げワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸 photo by Getty Images前編:2025年ワールドシリ…

3勝を挙げワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸 photo by Getty Images
前編:2025年ワールドシリーズ「ドジャースvsブルージェイズ」の残照
MLB史に残る激闘となったロサンゼルス・ドジャースとトロント・ブルージェイズのワールドシリーズ。その余韻はいまだ冷めることはない。あらためて振り返ると、さまざまな分水嶺があった。
前編では日本のファンにもお馴染み、縁の下の力持ち(アナリスト)としてブルージェイズを支えた加藤豪将が果たした役割と、両チームの勝敗を分けたもの、後編では比類なき活躍を見せた大谷翔平と山本由伸について、あらためて掘り下げてみたい。
【ブルージェイズを支えた加藤豪将の役割】
日本ハムで現役を終え、今季からトロント・ブルージェイズのフロント入りした加藤豪将(ごうすけ)が、ロサンゼルスのドジャー・スタジアムに姿を見せたのは8月8日のことだった。その日から始まった3連戦は、今にして思えばワールドシリーズの前哨戦だった。
加藤の役職はアナリスト。野手に関するデータを分析し、作戦立案をサポートするのが主な仕事だ。チームに帯同してフルシーズンを過ごしている。前年、ブルージェイズはア・リーグ東地区の最下位に沈んでいた。しかし今季は一転して首位を走った。加藤は「昨年はトレードデッドラインで7人の選手を放出しましたが、今年は3選手を補強しました。チーム全体が満足しています」と語る。その躍進を支えたのは、"つなぐ野球"だった。
MLBでは「フライボール革命」以降、多少三振が増えても引っ張ってフライを打つ打撃が主流となっている。だがブルージェイズは真逆のアプローチを取った。2020~21年にドジャース傘下のマイナーチームで打撃コーチを務めたデビッド・ポプキンス新打撃コーチは「ゴロも悪くない」という哲学の持ち主だ。ストライクゾーンを見極め、空振りせずにボールを強く打ち返す。たとえ地面に打っても、打球速度があればヒットになる。打球の強さを生むため、毎日、選手ごとのバットスピードを一覧にして共有。数値が落ちた選手にはすぐにウェイトルームでの調整や軽めの練習を指示して、体力回復を優先させている。
加藤も"つなぐ野球"の浸透に一役買っている。春のキャンプでは、チームがバント強化に取り組むなかで、選手をグループ分けして早朝に賞金1000ドル(約15万円)を懸けたバント競争を実施。その際、クラブハウスに貼り出された「お金をバラまくおじさん」風のジョン・シュナイダー監督の加工写真を作ったのも加藤だった。
練習運営にも関わり、バントは公式戦でも勝利を導く有効な武器となっている。2025年シーズンのブルージェイズは、本塁打数こそ30球団中11位タイだったが、チーム打率は.265でリーグ1位、得点数4位、三振数は2番目に少なかった。加藤は「バントを増やしたいわけではありません。どうすればチームを助けられるかを常に考えています」と話す。
ホームラン偏重ではない、実戦的で強力な打線を支える縁の下の力持ち――それが加藤の役割だった。

ブルージェイズの
「つなぐ野球」を支えた加藤豪将 photo by Kyodo News
【野球の面白さを世界中に再確認させてくれたシリーズ】
さて、2025年のワールドシリーズ。7試合の内容ではブルージェイズが勝っていた。数字がそれを物語っている。総得点は34対26で8点差。チームOPS(出塁率+長打率)は.745で、ドジャースの.658を大きく上回った。OPS上位8人のうち6人がブルージェイズの選手だった。1位は1.278の大谷翔平だが、2位以下はアディソン・バーガー、ウラジーミル・ゲレロJR.、アレハンドロ・カーク、ボー・ビシェット。6位にドジャースのウィル・スミスが入ったものの、7位、8位はアーニー・クレメンテとジョージ・スプリンガーだった。ドジャースは本塁打数では上回ったが、三振数も多く、チーム打率は.203とブルージェイズの.269を大きく下回った。
ドジャースはリーグ屈指の「空振りを奪う投手陣」を誇り、特に先発のブレーク・スネルはワールドシリーズまでのポストシーズン3試合で空振り率50%という圧倒的な数字を記録していた。
だが、ブルージェイズ打線はそのスネルを見事に攻略した。スネルはワールドシリーズで3試合に登板し、13イニングを投げて15安打8四球、10失点、防御率6.92と苦しんだ。大谷も2試合に先発し、8回1/3を投げて11安打3四球、7失点で防御率7.56。ブルージェイズ打線の粘りに屈した。
近年のMLBでは、「ホームランを打てないチームはポストシーズンを勝ち抜けない」と言われている。その定説は、今回もある意味で証明されたのかもしれない。第7戦では、ドジャースは9回にミゲル・ロハス、延長11回にウィル・スミスのソロホームランが飛び出し、打率で66ポイントも下回っていたドジャースが逆転優勝を果たしたからだ。
しかし誰の目にも明らかだったのは、このシリーズが「"打球の多い"ワールドシリーズ」だったということだ。走攻守のすべてで、わずか数センチを争うプレーが次々に生まれ、それが試合の緊張感を極限まで高めた。ホームランか三振か、という試合展開が主流となった現代の野球にあって、このシリーズはあらためて野球の面白さを世界中に再確認させてくれた。
第7戦、9回裏1死満塁。マウンドには山本由伸。打球は、二塁ゴロだった。もし三塁走者アイザイア・カイナー=ファレファが、もう少し大きくリードを取っていれば――。あるいはスミス捕手がホームベースを踏み損ねていれば――。決勝点が入り、ブルージェイズが1993年以来の世界一に輝いていた。
続く打者、クレメンテの左中間への大飛球も危うかった。キケ・ヘルナンデスとアンディ・パヘスが、ほんの少しでも違う角度で打球に入っていれば、捕れなかった可能性がある。
こうした「紙一重のプレー」がいくつもあり、今回のワールドシリーズの勝敗を決定づけた。ホームランか三振か、という単調な展開が支配する時代にあって、このシリーズはまるで、野球が本来持っていた呼吸や間、偶然と必然の美しさを取り戻すかのようだった。打球の音、走者のスパイクが土を蹴る音、歓声とため息----。野球というスポーツがいまだに"生きている"ことを、私たちに思い出させたのである。
つづく