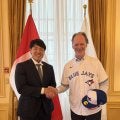サッカーは無数のディテール(詳細)であふれている。サッカージャーナリスト大住良之による、重箱の隅をつつくような超マニア…
サッカーは無数のディテール(詳細)であふれている。サッカージャーナリスト大住良之による、重箱の隅をつつくような超マニアックコラム。今回は日本サッカーの「夜明け前」。
■難しかった「プロ選手」としてのプレー
JSLで「プロ選手」が認められるのは、この2年後、1986年のことである。「オリンピック憲章」から「アマチュア」の文字が消されて12年、さまざまな競技でオリンピックのプロ選手が参加するようになっていた。ちょうどこの年、奥寺康彦さんが西ドイツのブンデスリーガでの9シーズンの活躍から帰国して古巣の古河電工(JSL)でプレーすることになった。体協の規定からようやく「アマチュア」の文字が外され、日本サッカー協会はプロ選手の登録を認め、奥寺さんと木村和司さんが「制約のないプロ活動」のできる「スペシャルライセンス・プレーヤー」として認定された。
それでも、JSLの中で公然とリーグ自体の「プロ化」が議論されるようになるのは、さらに2年後の1988年のことである。1984年9月、ロサリオのレプブリカ・ホテルのダイニングルームで私がマランゴニと向き合っていたとき、日本のサッカー界では「プロ化」などまだ想像もつかない時期だった。私はマランゴニにそうした日本の状況を説明し、プロ選手としてプレーすることは大変難しいと説明した。
「あなたの話は理解した。しかし、可能性のあるチームと話してみてくれないだろうか」
マランゴニは真摯だった。彼の穏やかな話しぶりと考え深い言葉の選び方には、高いインテリジェンスが感じられた。「日本でプレーしたい」という話が、思いつきや気まぐれではなく、さまざまなことを考えた末での言葉であったことがよく理解できた。
「わかりました。では、日本に帰ったら、トップリーグのクラブと話してみましょう」。私はそう約束した。
■「ジャパン・カップ」で来日後、英国へ
マランゴニにとって日本は未知の国ではなかった。24歳のとき、彼にとって2つ目のプロクラブであったサンロレンソ(ブエノスアイレス市)の一員として「ジャパン・カップ」のために来日し、京都、広島、東京とめぐりながらすべて「中1日」で4試合を戦った経験があった。マランゴニは全試合にほぼフル出場してチームを牽引、そのプレーが英国人エージェントの目に止まってその秋からイングランドのサンダーランドでプレーすることになる。
イングランドでも素晴らしいプレーを見せたマランゴニはファンを魅了したが、契約上の問題で1シーズン半しかプレーできず、アルゼンチンに帰国した。そしてウラカンで1年プレーした後、1982年からインデペンディエンテの不動の「5番」となったのだった。
ロサリオのホテルで彼と話した前週、私はインデペンディエンテのホームスタジアムでラシン・コルドバとの試合を見た。2-0でインデペンディエンテが勝ったのだが、その試合自体よりも、私は試合中のひとつの小さな出来事に心を奪われた。
■まさに「玄人好み」のプレーヤーだった
数少ない記者席には、私のための席はなく、「ここで見てくれ」と連れていかれたのは、VIPボックスのようないくつもの小部屋のひとつだった。現在のスタジアムの「ビジネススイート」のような部屋を想像してもらえればいいだろう。狭く、暗い部屋だったが、前面にガラスがあるわけではなく、ピッチはよく見えた。隣は、黒いロングドレスに身を包み、頭にも黒いレースをかけた上品な老婦人だった。
中盤で相手パスをカットしたマランゴニが、すばらしいステップでチャレンジにくる相手を2人かわし、ボールを持ち出して前線のリカルド・ボチーニに見事なパスを通す。ボチーニはこのクラブのファンの誰もが認めるスーパースターである。その才能は、当時すでに欧州で活躍していたマラドーナにも劣らないと言われていた。だが老女の口からもれたのは、ボチーニへの期待ではなかった。
「マランガ…」
彼女は、うめき声のような低い声でこうつぶやいたのだ。マランゴニの才能と機知に富んだプレーへの感嘆のように、私には聞こえた。そして呪術性さえ感じさせるその響きに、老若男女を問わず、この国の人がいかにサッカーを愛し、そして何よりもサッカーという競技を熟知しているか、一瞬にして理解できる思いがした。
マランゴニは、まさに玄人好みのプレーヤーだった。