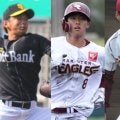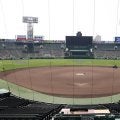それは近い将来、イングランド時代が到来することを確信させる瞬間だった。いや、それどころか、もはやイングランド時代の…
それは近い将来、イングランド時代が到来することを確信させる瞬間だった。いや、それどころか、もはやイングランド時代の幕開けを告げる瞬間だった、と言ったほうがいいのかもしれない。
インドで開催されていたU-17W杯は10月28日に決勝が行なわれ、イングランドが5-2でスペインを下し、初優勝を果たした。イングランドは、今年6月のU-20W杯優勝と合わせて、年代別代表での二冠達成である。

U-20W杯に続いてU-17W杯も制したイングランド
この試合、イングランドは立ち上がりから攻勢に出るも、10分に先制点を、31分には追加点を許す苦しい展開を強いられた。特に2失点目は、攻撃姿勢を強めたところで縦パスをインターセプトされ、カウンターに屈したものであり、優位に試合を進めていたイングランドにとっては、精神的ダメージが大きいはずのものだった。
しかし、ここからが高い攻撃力を誇るイングランドの真骨頂だった。2点のビハインドも、イングランドの強さを際立たせるための演出でしかなかった。
0-2になって意気消沈するどころか、むしろ攻撃力に火がついたイングランドは、まずは44分、右サイドを駆け上がったDFスティーブン・セッセグノンのクロスを、FWライアン・ブリュースターが頭で決め、1点を返す。
試合の潮目が変わった瞬間を振り返り、イングランドのスティーブ・クーパー監督が語る。
「(前半終了間際という)素晴らしいタイミングでのゴールだった。しかも完璧なクロスと、完璧なヘディングシュート。(まだ1点リードされていたが)ハーフタイムの雰囲気はポジティブなものだった」
後半に入ると、さらに攻勢を強める白のユニフォームが、ジワジワと赤のユニフォームを押し込んでいく。
すると58分、再び右サイドをコンビネーションで破ったセッセグノンのクロスを、フリーでゴール前へ走り込んだMFモーガン・ギブスホワイトが右足で合わせ、後半早々にして試合を振り出しに戻した。
両チームにとって、この試合が今大会7試合目。先発でピッチに立っている多くの選手は、ほとんどフルに戦い続けていた。
しかも、インドの高温多湿の気象条件に加え、良好とは言い難いピッチコンディション。足への負担も大きく、選手たちの蓄積疲労はピークに達していたに違いない。両チームともコンパクトな布陣を保つのが難しくなり、試合は時間の経過とともに、間延びしたなかにスペースが生まれ、オープンな打ち合いが繰り広げられるようになっていった。
こうなると、分があるのは、個人能力で勝るイングランドのほうだった。とりわけ、圧巻の能力を見せつけたのが、左MFのカラム・ハドソン-オドイである。
タイミングのいいフェイントや切り返しもさることながら、アクセルをブンとひと踏みするだけで相手DFを振り切れるほどの加速力を備えた背番号14は、左サイドから次々にチャンスを作り出した。決勝点となった3点目をはじめ、2-2からの3ゴールはいずれも彼のスピードと突破力が引き金となって生まれたものだ。
スペインのサンティアゴ・デニア監督が語る。
「イングランドの左ウイング(ハドソン-オドイ)は警戒していたし、そのための準備もしていた。(対面の)サイドバックだけでなく、(同サイドの)MFとふたりで対応するように指示していた」
だが、世界の頂点に立ったイングランドは、ハドソン-オドイだけを抑えればいいチームではなかった。デニア監督が続ける。
「左ウイングだけでなく、イングランドには他にもテクニックに優れた選手がいた。左利きの右ウイング(MFフィリップ・フォーデン)にしても、カットインして中に入ってくる。スペースが生まれやすい試合展開は、イングランドに合っていた」
大会MVPに選ばれたフォーデンをはじめ、イングランドはハドソン-オドイ以外にも、各ポジションに優れたタレントを擁していた。これといった穴がなく、ピッチ全体を使ってボールを動かすことができるからこそ、それぞれの個人能力を(それに依存しすぎることなく)効果的に生かすことができていた。
なかでも特筆すべきは、センターバックとボランチに、安定してボールを動かすことができ、攻撃の組み立て役を担える選手をそろえていたことだろう。
今大会やU-20W杯を見れば明らかなように、イングランドが現在、伝統的なイングランド・サッカーからの脱皮を図っていることは間違いない。すなわち、ロングボールやアーリークロスを生かし、直線的に相手ゴールへと向かうスタイルから、ボールポゼッションを高め、低い位置からでもパスをつないでビルドアップするスタイルへの転換である。
このスタイルチェンジにおいて、重要な役割を担うのが、センターバックとボランチである。彼らがスムーズにボールを動かすことができず、相手のプレスに狙われてしまえば、攻撃は必然、長いボールを蹴るしかなくなってしまう。ところが、今のイングランドの若い世代を見ていると、これはU-20代表にも共通することだが、このキーポジションに人材がそろっているのだ。
今回の決勝でも、前線からのプレスでパスコースを制限しようとするスペインに対し、テンポよくパスをつなぐだけでなく、ときには1本のロングボールで相手の背後を突き、ときには自らボールを前に持ち出し、確実に攻撃を組み立てていた。失礼ながら、かつての大味なイングランド・サッカーからは想像もできないほど、現在の若い世代は細かな自在性を備えている。
それにしても、このところの年代別代表におけるイングランドの充実ぶりには、目を見張るものがある。
図らずも今年、A代表以下、U-21、U-20、U-17と、4世代のイングランド代表を見る機会を得たが、年齢が下へいくほど、チームとして志向するサッカーが洗練されており、選手個々を見てもタレントがそろっていた。
クーパー監督は「U-20に続いて優勝できたことは、とてもスペシャルなこと」と言い、こう続ける。
「ラッキーなことに、私は監督として優勝を味わえたが、この優勝トロフィーは、FA(イングランド・サッカー協会)の全員が献身的にやってきたことの成果だ」
これまでのイングランド・サッカーというと、スピードやパワーといったフィジカル要素においては迫力があったが、裏を返せば、単調で大味な印象が強かった。少々極端に言えば、1966年に地元開催のW杯を制して以降、大まかな方向性を変えることなく、伝統を受け継いできたわけである。
しかし、さすがの”サッカーの母国”も、伝統の力だけで世界と伍していくのは難しかった。W杯では1990年イタリア大会、ユーロでは地元開催の1996年イングランド大会での、ともにベスト4を最後に、最近では不甲斐ない成績のほうが目立つ。
イングランド同様、無骨なイメージのあったドイツが、今や世界随一のポゼッションサッカーの使い手となったことも、イングランドの”ひとり負け感”を強くした一因だろう。過去にW杯優勝経験を持つ強豪国のなかでは、イングランドだけが時代の流れから取り残される格好となっていた。
だが、ここに来て、時代遅れの伝統にすがるしかなかった古豪も、ついに生まれ変わった。若手育成のためのアカデミーに力を入れ、育成年代を強化。クーパー監督が、大逆転で優勝を勝ち取った試合を振り返り、「グレイト・フットボール。自分たちがやりたいことを見せられた」と胸を張ったように。その成果は二冠という結果以上に、ピッチ上で展開された質の高いサッカーにうかがえた。
1990年代後半以降に一時代を築いたフランス、スペイン、ドイツという強豪国は、例外なく、まずは年代別代表で成果を挙げ、それをA代表につなげてきた。そうした過去の例から考えれば、間違いなくイングランド時代はやってくる。
クーパー監督は快挙達成にも、「長期的な強化計画をスタートさせて、まだ数年が経っただけ。将来にフォーカスして成長を続けていかなければならない」と、あくまでも先を見据えて謙虚に語っていたが、自信を持ってそう言えるのは、強化計画が順調に進んでいるからこそ、だろう。
さすがに来年のW杯は気が早いとしても、3年後のユーロか、あるいは5年後のW杯か。
うまくて強い――。従来のイメージを覆す、そんなイングランド代表が見られる日はそれほど遠くなさそうだ。