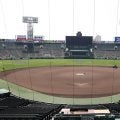リオデジャネイロ五輪のメダリストとして日本の卓球界を牽引する吉村真晴。第1回は親元で「卓球エリート」として育てられた軌跡…
リオデジャネイロ五輪のメダリストとして日本の卓球界を牽引する吉村真晴。第1回は親元で「卓球エリート」として育てられた軌跡にスポットを当てた。第2回は中学校から高校時代へ。幼少期のド派手な戦績を引っさげ、名門中学に鳴り物入り、その才能を開花させる…というわけにはいかなかった。世界に通用する吉村の戦型が作られるまでには紆余曲折があったのだ。
練習漬けだった小学生時代、吉村少年が何よりも楽しかったのが「試合」だ。「小学生なのに村の中学生とか高校生を倒せちゃうんです。それは楽しかったなあ。しかも毎試合、自分の中で発見と成長があった。20代の成長よりも、あの時の1試合ごとの発見と成長の方が大きかったですね。あの快感があったから厳しい練習も耐え抜けたんだと思います」と語る。その甲斐あって、全日本カブ(小学4年生以下)では優勝、ホープス(小学6年生以下)は2位と圧倒的な強さで卓球選手としてのキャリアをスタートさせた。
スパルタな父親との“激闘”の日々は小学6年生の時に意外にあっさりと終わる。中学からは仙台に行くことになったのだ。ここで吉村の卓球人生は大きな転換点を迎えることとなる。

身についたサボりグセ。中学校2年の空白期間
小学校を卒業した吉村が選んだのは地元茨城県東海村から離れた、名門・仙台育英学園高等学校系列の秀光中等教育学校だ。入部先はもちろん、卓球部。だが、「親から逃げたと言っても過言じゃないですね、ちょっと卓球が嫌になっていたのかもしれない」。待ち受けていたのは「平凡な日々」だった。「もちろん部内では上手かった方で。そりゃたまには顧問に怒られましたけど、親みたいに厳しく怒られることもありませんでした。悪いこともいっぱいして怒られてましたね(笑)」。気づけば身についたのはサボりグセだった。
「普通の学生生活を送ってましたね」。ようやく手に入れた友達との楽しい暮らし。それと引き換えに失ったのが練習量、そして勝利の味だった。小学生時代には面白いように勝てた試合も勝てなくなっていた。「ナショナルチームのメンバーってみんなエリートじゃないですか。カデット優勝、全中優勝、インターハイ優勝して日本一になって、代表に選ばれていくけど、僕は全然違いますね」。そう軌跡を振り返る。
確かに同じリオ五輪に出場した丹羽孝希はホープスの部で全日本優勝、全国中学校卓球大会(全中)でも団体優勝、各国のツアーオープンでも数々の優勝をかっさらい、ナショナルチームへ選出されている。一方の吉村は中学校時代、全中では最高で3回戦どまりだ。「僕、カブ優勝して、次、高3での全日本優勝ですから」。キャリアだけ見ればぽっかりと空いてしまった中学時代。吉村の卓球熱が再び着火するのは中学3年生の時のことだ。
恩師との出会い、そして迎えた飛躍
きっかけになったのが秀光中等教育学校の母体の仙台育英学園高等学校のスポーツ特待生枠の廃止だ。それに伴い当時の顧問であった橋津文彦氏が山口県・野田学園中学校・高校に赴任することが決定、吉村も山口県へと転校することになる。
恩師である橋津氏が吉村に与えた影響は大きかった。現在の「長いリーチを活かした豪快な両ハンドドライブ」という戦型も橋津氏が導き出した。「もともと僕は器用な方だったんで、何でもできるタイプだったんですよね。だから戦術の幅が広すぎちゃった。色々なサーブ出して、色々なことをしたがっちゃう。だから、試合がまとまってなくて、結局負けてしまう」。悩む吉村に橋津氏はこんなアドバイスをした。「お前はバックハンドが強い。だから動き回るんじゃなくて、バック対バックから、相手を揺さぶって点数を取れ」。基礎中の基礎であるバックハンドを固め、元来器用だった吉村に“核”を作りあげた。

「それからはひたすらバックハンドの練習です。バックハンド・バックハンド・回り込み、バックハンド・バックハンド・ストレート、カウンターされてカウンターとか、自分の点数の取り方、パターン練習を叩き込まれました」という。
橋津氏のもと、再び練習に打ち込み始めた。そしてようやく飛躍の年が訪れる。高校3年生の時だ。
写真:伊藤圭
取材・文:武田鼎(ラリーズ編集部)