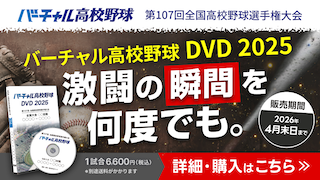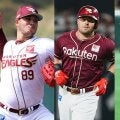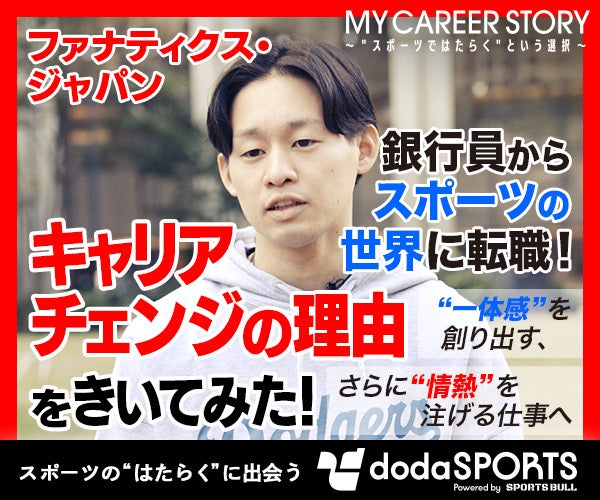サッカー日本代表が2026年ワールドカップへの出場を「世界最速」で決めた。この大会の主催者は「The Greatest…
サッカー日本代表が2026年ワールドカップへの出場を「世界最速」で決めた。この大会の主催者は「The Greatest World Cup」と、大会を自ら褒めたたえるが、その言葉は「真実」なのか。サッカージャーナリスト大住良之が「問題点」を指摘する!
■アメリカ大会に「2か国」が乗った?
カナダ代表とメキシコ代表は、グループステージの3試合をいずれも自国内で開催する(カナダは初戦をトロントで戦い、残りの2試合はバンクーバーが舞台。メキシコはメキシコシティで2試合、グアダラハラで1試合)が、大会のちょうど4分の3がアメリカで開催される以上、「3か国共同開催」というより、「アメリカ大会」にカナダとメキシコが乗った形と言える。
グループステージは6月11日(木曜日)にスタートし、最終日は6月27日(土曜日)。わずか17日間で72試合を消化する。最初の2日間は2試合ずつだが、3日目から1日4試合となり、「第3ラウンド」を迎える7月24日から27日までの4日間は毎日6試合が行われる。
■気になる「試合間隔」と広大な国土
気になるのは「試合間隔」である。これまでのワールドカップでは、グループステージの試合間隔は、「中5日ないし中4日」だった。今回も大半のチームがこの日程が保証されているが、AからLの全12グループ中、I、K、Lの3組は、2試合目と3試合目のインターバルが「中3日」しかない。
大会組織委員会は、会場を「東・中央・西」の3ゾーンに分け、グループステージではできるだけ同じゾーン内で試合ができるよう日程を組んでいるという。広大な北米大陸全体に広がる16会場は、緯度で30度(最北がバンクーバーの北緯49度16分、最南がメキシコシティの北緯19度26分)、経度で52度(最西がバンクーバーの西経123度7分、最東がボストンの西経71度4分)もの広がりがある。バンクーバーとメキシコシティ間の距離は4000キロ近くになる。時差も、東西で4時間ある。移動による負担をできるだけ減らそうという狙いだった。
それでも12グループのうち半数以上の7グループでは「ゾーンをまたぐ」形での試合を強いられる。1つのゾーンで試合ができるのは、C組(東ゾーン)、アメリカが入るD組(西ゾーン)、F組(中央ゾーン)、G組(西ゾーン)、I組(東ゾーン)だけにすぎない。
■32年前との違いは「日本代表」
1994年、32年前のアメリカ大会は、出場24チーム、6グループでグループステージが行われ、使われた会場は9都市だった。東海岸に北からボストン、ニューヨーク、ワシントンDC、そしてオーランド(マイアミ州)、中部では、デトロイト、シカゴ、そしてダラス、西海岸では、サンフランシスコとロサンゼルスだった。
私はシカゴで開幕の「ドイツ×ボリビア」を取材した後、グループステージは主として東海岸で試合を見た。ニューヨーク、ワシントンDC、ボストン、さらには「中部」のデトロイトやシカゴを飛び回った。そして大会の後半、ノックアウトステージに入ると、西海岸に移動した。決勝戦はロサンゼルスのローズボウルスタジアムだった。
会場間の移動はすべて飛行機だった。ネットで予約できる時代ではないから、予定に従って基本的に日本国内の旅行代理店で航空券を購入し、予約を入れてもらった。空港からの移動、空港からの移動は、すべてタクシーだった。公共交通機関もあったかもしれないが、基本的に朝移動して次の試合会場都市に向かい、ホテルに荷物を放り投げてスタジアムに直行、取材を終わって帰ってくると1泊し、翌朝また次の取材地に向かうという毎日だった。
だが、その大会には日本代表が出場していなかったから、開幕から決勝まで、事前に日程を決め、移動のための飛行機を予約し、そしてホテルを押さえることができた。しかし、「日本を追う」となったら、ノックアウトステージ以降は日程が決まってからすべてを手配しなければならない。
しかも、カナダのトロントでは「ラウンド32」で試合が終わるが、バンクーバーでは「ラウンド16」まで試合がある。メキシコでは、グアダラハラがグループステージで試合が終了、モンテレイは「ラウンド32」まで、メキシコシティは「ラウンド16」まで試合が続く。チームを追って、たくさんのサポーターと報道陣が北米大陸をさまようことになる。