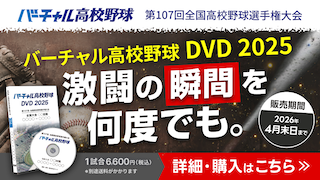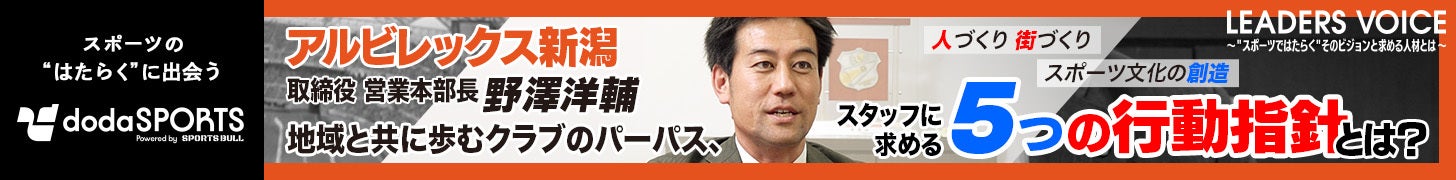■なぜ…
■なぜドラフトが必要なのか
4月3日、Bリーグ・島田慎二チェアマンのポッドキャスト番組『島田のマイク』第230回が配信。3月中旬に発表された『B.LEAGUEドラフト』制度の概要と、その導入に至った経緯や理念について語った。
2026年秋からスタートする『B.革新』の一環として実施されるドラフト制度。その導入目的について、島田チェアマンは「Bリーグが日本社会の中で未来、永く存在していくためには、皆様に応援してもらわなければいけないわけですよね。あとは(Bリーグが目指す“感動立国”や“地方創生リーグ”等も含めた)社会的大義がないといけない」と前置きし、首都圏と地方の格差是正という大きな理念を強調した。
Bリーグの強みは全国にクラブを有していることではあるが、「過度な自由競争だと、どうしても資金力のある首都圏ビッグクラブが競技的に圧倒していく未来が見えてます」と、島田チェアマンは現状の課題を指摘。何かしら手を打たなければクラブ格差が広がるばかりであるという危機感から、サラリーキャップとドラフト制度という二つの大きな施策を打ち出し、戦力の均衡化を図る。
島田チェアマンは、ドラフト制度を全てのクラブに希望を与えるための仕組みと位置づけている。ファンが地元クラブを応援したくなる環境づくりには社会貢献活動やファンサービスも大切だが、最も重要なのは「(ビッグクラブに対しても勝てる)チャンスがあるかも」と思える状況を作ることだと強調した。
「(地元でそれぞれが応援している)我がチームも将来、首都圏チームには“勝てない”じゃなくて、“勝てるかも”という制度にすることで、うまくいかないシーズンがあったとしても、来年はいけるかも、再来年はいけるかも、という希望が、その地域の活性化だったり、地域を支えていくエネルギーに相成ると信じています」
■難産を乗り越えられた背景は?
ドラフト制度はBリーグが世間から注目される機会となる一大イベントとしての側面も持つ。島田チェアマンは「始めは大物選手は少ないかもしれませんが、数年後には小中学生たちが“ドラフト1巡目でかかる”と、目標にする希望になる」と長期的な育成視点の重要性を説明した。高校・大学バスケなどのカテゴリーごとに壁があるバスケットボール界において、ドラフト制度導入により「縦割れだったのを横串刺せる」ことでBリーグファンが学生バスケに注目し、その逆も起こるという相乗効果への期待も語った。
『B.革新』による一連のレギュレーション刷新にあたり、島田チェアマンは「一番難産だったのがドラフト」と振り返った。ユース育成制度とドラフト制度の両立は世界初の試みだという。クラブが育成した選手を手元に残したい想いと、ドラフトの盛り上がりを実現させるため様々な工夫がなされており、その内の一つが優先交渉権の制度だ。クラブ所属のU18で2年以上プレーした選手には、ドラフト前にホームクラブと直接交渉する権利が与えられる。報酬条件はドラフト参加時より低くなるものの、選手とクラブの双方が合意すれば契約可能という仕組みで、育成に投資したクラブと選手の意思を尊重する策となっている。
最終的な合意に至った背景には、島田チェアマンが語った「自分のクラブで将来活躍するということに執着するんじゃなくて、日本の子どもたちをみんなで育てよう」という理念があった。各クラブが地域の枠を超えて日本バスケ界全体の発展という大きな目標に向かって協力する体制づくりが、この難題を乗り越える鍵になったという。
また、制度設計では選手の環境や条件面も重視された。島田チェアマンは「選手に不利益があったらダメなんですよ」と強調し、「環境条件と経済条件を整えて初めてこの制度は成立する」と、クラブに対して高いハードルを設定していることを明かした。トレーニング施設や練習環境、スタッフ体制まで細かく条件を定め、どのクラブに行っても高水準の環境が保証されるよう配慮されている。さらに『育成契約選手制度』として新B1のB.LEAGUE PREMIER(Bプレミア)所属選手が、新B2のB.LEAGUE ONE(Bワン)のクラブでプレー経験を積める仕組みも用意し、NBAとGリーグの関係に近い制度も構築されていることが説明された。
第1回ドラフトは2026年1月29日に東京ドームシティホールで開催予定。制度の発表を受け、番組の最後に島田チェアマンは「学生の皆さんはよく見ていただいて、ぜひチャレンジしていただきたい」と締めくくった。
【番組を聴く】B.LEAGUEドラフト概要発表!画期的な試みで”希望”を生み出す!『島田のマイク』第230回