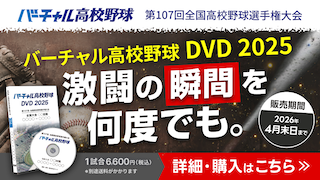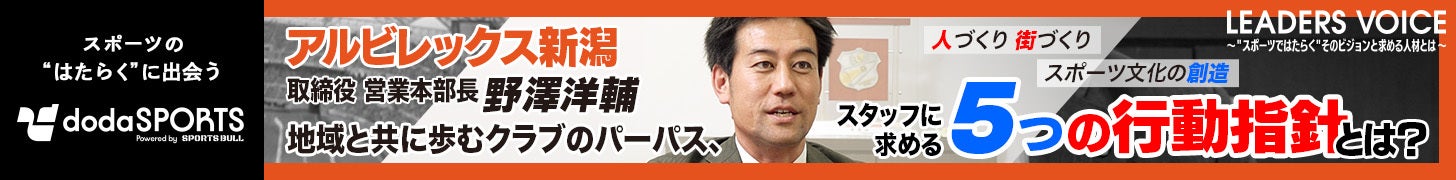鬼木達監督を迎えた鹿島アントラーズが好調だ。開幕戦こそ落としたが、その後は白星を重ねて首位に立っている。前節のヴィッセ…
鬼木達監督を迎えた鹿島アントラーズが好調だ。開幕戦こそ落としたが、その後は白星を重ねて首位に立っている。前節のヴィッセル神戸戦では、その強さの理由が垣間見えた。昨季王者との対戦で見えた「鬼木アントラーズ」の現在地をサッカージャーナリスト後藤健生が探る。
■ハイプレスの問題を解決した「天才」
2016年から日本代表を指揮したヴァイッド・ハリルホジッチ監督はハイプレスを徹底して要求したが、ハリルホジッチ時代の末期には、せっかくボールを奪いながら、それをつなぐことができず、再び奪われてピンチを招くような場面が何度もあった。
1974年の西ドイツ・ワールドカップで、FWが相手陣内からボールを奪いに行く「ボール・ハンティング」という概念を掲げて世界に衝撃を与えたオランダ代表の場合、その問題を解決したのがヨハン・クライフという天才プレーヤーの存在だった。
FWでありながら、自由にポジションを変えるクライフがいれば、奪ったボールをすぐに前線につないでチャンスを作ることができなくても、チーム全体の動きと相手の対応を見極めて常に適切な位置を取っているキャプテンを見つけてボールを預けさえすれば、後はクライフがパスを使って攻撃を組み立ててくれるし、フィニッシュの仕事にも関わってくれる。
カウンタープレスで成功を収めた神戸も、それに近い感覚だったのかもしれない。
ヴィッセル神戸には、今でも日本最高のCFである大迫勇也がいる。
ボールを奪ったら、まず大迫の位置を確かめてロングボールを蹴り込むのだ。バスの精度が多少落ちていても、大迫なら前線でボールを収めてくれるし、ヘディングで競り勝ってくれる。そして、そのボールが大迫の忠実な副官である武藤嘉紀に渡れば、さらにチャンスは広がっていく……。
では、ヨハン・クライフも大迫勇也もいないチームの場合、ハイプレスをかけてボールを奪った後、どのようにボールをつないで奪ったボールをゴールに直結させていくのか……。それこそが、各チームの課題であり、また各監督の腕の見せ所ということになる。
■90分を通して「何度もあった」場面
鹿島アントラーズが神戸を破った第7節の試合を見ていて、感心したのは就任から数か月の鬼木監督がすでに、ボールを奪った後のプランを準備しつつあったことだ。
この鹿島対神戸の試合は、悪コンディションの中での試合だった。
前日は25度を超えるような春の暖かさだったのに、3月29日の関東地方は季節外れの寒さと風雨に見舞われた。
公式記録によれば、気温は8.0度となっているが、カシマサッカースタジアム独特の風もあり、寒さは一層、身に染みた。公式記録では「弱風」となっているが、神戸の吉田孝行監督が試合後の記者会見で「後半は追い風だったのである程度、持てた」と語ったように、風の影響も間違いなくあった。
そして、未明から降り続いていた雨のせいで、ピッチはかなりスリッピーな状態だった。試合開始時には雨は弱くなっており、試合中に止んだが、ピッチがスリッピーだったことに変わりはない。実際、両チームの選手がピッチに足を取られて転倒する場面が90分を通して何度もあった。
■「使わざるを得ない」ロングボール
こうしたコンディションの試合では、どうしても安全第一でロングキックを使わざるを得ない。
実際、鹿島の決勝ゴールはGK早川友基からのロングボールから生まれた。CKからのつなぎに失敗した鹿島が自陣にボールを戻したところで、早川が相手守備ラインが整っていないのを見て、思い切って相手ゴール前にロングボールを蹴り込んだ。鹿島の前線には鈴木優磨とチャヴリッチが残っており、鈴木は明らかなオフサイドポジションだった。ところが、やや後方のオンサイドの位置から、レオ・セアラが飛び出してきたのだ。
神戸のGK前川黛也はそのレオ・セアラの動きを確認できていなかったのか、ペナルティーエリアを飛び出してヘディングでのクリアを試み、レオ・セアラと競り合い、ボールはゴール方向に落ちた。そして、体勢を立て直したレオ・セアラが無人のゴールにシュートを決めた。
まさに、ロングボールを巧みに使った形のゴールだった。