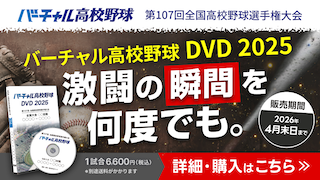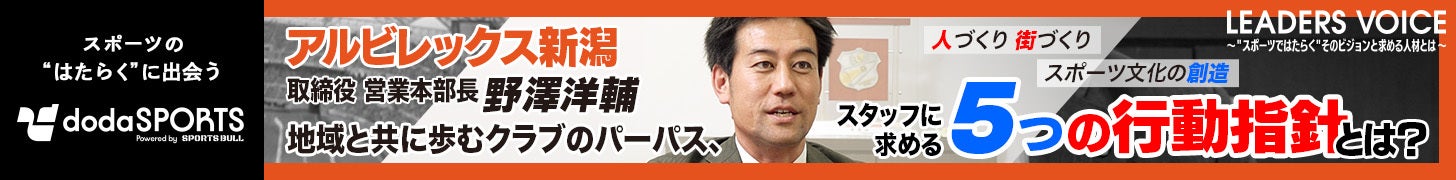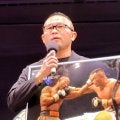蹴球放浪家・後藤健生は、サッカーを通じて文化の見分を広めている。今では一般的になっているが、かつて日本に存在しなかった…
蹴球放浪家・後藤健生は、サッカーを通じて文化の見分を広めている。今では一般的になっているが、かつて日本に存在しなかった社会のルールを、イングランドのスタジアム最寄り駅で「発見」した!
■イタリアでは「お構いなし」
さて、ロンドンに滞在した後、ツアーはイタリアに向かい、ローマ、フィレンツェ、ミラノを観光。その後、スイス経由でフランスに入り、パリ市内観光やロワール河の古城めぐりが付いていました。
ロンドンでのエスカレーターの乗り方に感心したので、僕はイタリアやフランスではどうなっているか注意して見ていました。
すると、たしかに片側に立っている場所もありましたが、このルールが都市の隅々まで浸透しているようではなさそうでした。とくに、イタリアなどはそんなことにはお構いなしのように見えました。「都市生活」という意味では、古代ローマ以来の伝統を誇るローマはロンドンやパリよりずっと歴史が長いはずでしたが、そうした習慣は根付いていないようでした(まあ、古代ローマにはエスカレーターはなかったわけですが……)。
■欧州で必要とされる「ニコッ」
その他にも、ヨーロッパには都市生活のためのルールがいくつもあります。
たとえば、入口を開けて中に入った人は、後から来る人のためにドアを押さえて開けたままにしておくという習慣がありました。後から来た人は、ドアを押す必要がないわけです。日本でも、そうする人はいますが、ヨーロッパではそうするほうが一般的です。
また、エレベーターの「かご」や列車のコンパートメントの中などで、見知らぬ人と一緒になったときに、口角を上げて「ニコッ」と笑うような表情をするのもルールの一種です(エレベーターの人が乗る箱のことを「かご」と言います。昔、本当に籠状の物に乗っていた時代の名残なのでしょう……)。
互いに「私はあなたに対して敵意を抱いてはいませんよ」ということを確認し合うわけです。異民族と陸上の国境を挟んで接しているヨーロッパではこういう非言語的コミュニケーションが必要だったのでしょう。
しかし、そういう習慣がない日本人はなかなか真似できません。僕が自然に、ニコッという表情ができるようになったのは、1980年代になって頻繁にヨーロッパに行くようになってからのことでした。
■日本流「非コミュニケーション」
エスカレーターの片側空けの習慣は、ちょうど僕がヨーロッパ旅行に行った後の1970年代後半には日本でも一般化しました。それを見て、僕は「ああ、日本もようやく文明国になったんだなぁ」と思ったものでした。しかし、その後、日本ではその習慣の規範性が強まりすぎて、それに従わない人を「非常識な人」あるいは「田舎者」と見なすようになってしまいました。規則を守りたがる日本人らしいところです。
ところが、知らない人どうしが「ニコッ」と笑顔を見せ合う習慣は、日本では今でもまったく定着していません。日本人同士の場合には、笑顔を見せるよりも、ちょこんと軽く会釈するのがマナーのようですが、会釈するのは多少とも面識のある人同士であって、見知らぬ人同士では無視し合うことも多いようです。
海外のホテルのエレベーターの「かご」の中で、外国人と一緒になると「ニコッ」と笑顔をかわすのに、(見知らぬ)日本人と一緒になると互いにそっぽを向いて、無視し合うといったことをよく経験します。
見知らぬ他人と出会う機会も多い都市生活では、知らない人とコミュニケーションを取ることも必要のように感じるのですが……。