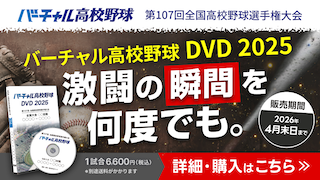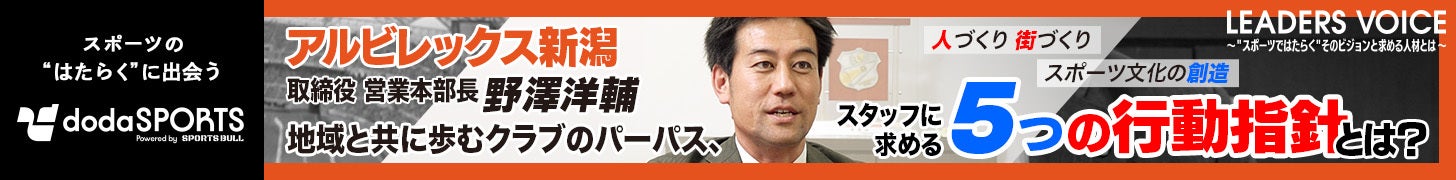福田正博 フットボール原論■サッカー日本代表が8大会連続のワールドカップ出場を勝ち取った。圧倒的な結果でW杯本大会行きを…
福田正博 フットボール原論
■サッカー日本代表が8大会連続のワールドカップ出場を勝ち取った。圧倒的な結果でW杯本大会行きを決めた背景は何か。福田正博氏が森保一監督のマネジメント力を解説。今後のチームづくりも展望した。

サッカー日本代表を8大会連続のワールドカップ出場へ導いた森保一監督
photo by Kishiku Torao
【アジアカップ敗退の経験が生きた最終予選】
サッカー日本代表のW杯アジア最終予選3月シリーズは、バーレーンに2-0で勝利、サウジアラビアには0-0の引き分け。バーレーン戦の勝利で2026年北中米W杯の出場権を決め、サウジアラビア戦はこれまで起用できなかった選手たちを試すこともできた。収穫のある2試合になったと言えるだろう。
2024年9月から始まったW杯アジア最終予選は、8試合で6勝2分け24得点2失点。過去の予選でこれほど圧倒的な結果を残したことはないが、この根底には2024年1月のアジアカップ敗退の経験があるだろう。
2022年カタールW杯でドイツとスペインを撃破し、第二次森保一監督体制がスタートした2023年はドイツを再びアウェーで撃破するなど好調だった。それが、優勝への期待が否応なく高まるなかで迎えたアジアカップでは、準々決勝で敗退。この敗北を味わったことで日本代表はもう一度引き締まり、選手たちは個々でレベルアップを遂げてきた。
森保一監督のチームマネジメントも見逃してはいけない。
まず、基本布陣を3バックへ変えたり、セットプレーでも得点できるようになったりと、今回の予選を通じてチームにさまざまな変化や成長が見てとれるようになったのは、森保監督が2期目を務めていることが大きい。
活動期間の限られる代表チームにあっては、監督はできることが限られてしまう。チームの根幹をなすところから優先順位を決めてチーム作りに取り組むと、たとえばセットプレーなどはどうしても後回しになってしまうところだ。それが現代表では森保監督1期目からの流れを受けているため、セットプレーに取り組む時間がつくれている。そこで結果が出てきたのだ。
そして、監督のチームマネジメントのなかでもっとも重要なのは、チームの方針を決め、選手たちに同じ方向を向かせることだ。
いまの日本代表はスタメンからベンチメンバーまで、海外クラブで主戦として戦う選手たちがズラリと揃う。自分が先発して当然という強い自負を持っている彼らをいっせいにピッチに送り出すことができれば楽だが、監督はメンバーを決めなければならない。起用されない選手は当然不満を抱え、それが積み重なればチームとして同じ方向を向いて戦うのが難しくなる。
森保監督は、そんなひと筋縄でいかない選手たちをまとめるのが実に巧みなのだ。
【監督のマネジメントにもっと目を向けてほしい】
その一例が長友佑都の招集であり、長谷部誠コーチの招聘だ。ベンチ入り選手数が増えたメリットを活かし、選手としての能力に加え、代表選手たちに寄り添える存在として長友佑都を招集してきた。そして選手との距離感が近く、海外で長く活躍した実績を持つ長谷部がいることによって、試合に出られなくて不満を抱える選手の気持ちが軽くなった側面がある。
森保監督自身も、スタッフを信頼しながら厳しくすべき点では自らが前に出る。予選中にある選手がピッチ上でふさわしくない振る舞いをした時、森保監督はそこを許すとチームがまとまりを欠くと判断し、「中心選手であっても代表チームを去って構わない」という強い覚悟を持って選手と対峙した。普段は温厚で誠実な人柄で、つねに私利私欲なく「日本代表のため」「日本サッカーのため」を考えている監督だからこそ、厳しさを前面に打ち出した時に選手へ思いの真意が伝わるのだ。
森保監督に対しては、バーレーン戦後に批判も出た。先発した守田英正が故障を再発させ、三笘薫もコンディションを崩したからだ。W杯出場権をほぼ手中にしていたなかで無理して使う必要はなかったという意見だが、これは結果論にすぎない。
スポーツは決められる時に決めなければ、その後に勝ち点を手にできる保証はない。なにより守田にしろ、三笘にしろ、日本代表に自覚と責任を持って臨んでいることを、軽んじていないだろうか。
彼らの気持ちをもっとも尊重しているのは、森保監督だ。予選を通じて中心選手として日本代表を牽引してきた彼らをリスペクトしているからこそ、選手の「出られる」という判断を尊重したのだ。逆にW杯出場が決まる大一番にスタメンから外されたら、選手たちは監督の気遣いを理解はしつつも、出られなかったことへ不満を抱えるだろう。トップ選手というのは、そのくらい自身の存在価値に大きな自負を持っているものである。
監督の仕事というのは、采配面に目が向きがちだ。しかし、限られた時間しかない代表活動のなかで、選手たちの気持ちをコントロールしながら継続的にチームをつくりあげていくことのほうが圧倒的に難しい。このマネジメントこそ監督たちが重きを置くものであり、多くの人たちにもっと理解してほしいと思う。そして、そうした目線でこれからの日本代表の活動を見ると、新たなサッカーの魅力に触れられるはずだ。
【競争を名目に主力を休ませるか】
森保監督は、バーレーン戦後のインタビューのなかで「競争」という言葉を発した。これはW杯出場を決めた選手たちに、緊張感と刺激を持たせる狙いがあったのだろう。ただし、勘違いしてはいけないのは、これはすべての選手が横並びの状態で競争するわけではないという点だ。
サッカーにおいてチーム内にヒエラルキーがあるのは当然で、それがなければチームの根幹も崩れてしまう。まして、予選を通じて選手個々が手にした役割を、W杯本番に向けて「競争だから」と取り上げたら、選手たちにそっぽを向かれる。先ほども述べたように、彼らには大きな自負心があるからだ。
ただ、日本代表の中心メンバーは所属クラブで主力として戦いながら、代表活動があるたびに長距離移動し、代表戦を戦った後は再び長い時間をかけて所属クラブに戻る。選手本人が自覚しないまま蓄積された疲労はある。それを抜いてフレッシュな状態に戻ってもらうために、彼らを休ませて新たな選手を試すことがあるかもしれない。
また、移籍への備えもある。ヨーロッパのシーズンは5月で終わり、夏の終わりに新シーズンが開幕する。このタイミングで移籍する選手は、新たな所属クラブでポジションをつかんでもらうことが、W杯に向けた日本代表の戦力アップにつながる。ここで出場機会がないままW杯を迎えるのは不安要素になるため、競争を名目に招集せず、自チームでの活動に専念させるケースも想定される。
そうしたなかで最初の競争の場になるのが、6月にあるW杯アジア最終予選のラスト2試合だ。対戦相手となるオーストラリア、インドネシアともに残りのW杯出場枠を狙って高い強度で臨んでくる。これはW杯本番を見据えた強化を考えれば、日本代表にとってメリットが大きい。
この2試合でも初招集の選手を使うというよりは、予選を通じて出番に恵まれなかった選手を起用していくと思う。サウジアラビア戦と同じように、チームの根幹であるキャプテン遠藤航やGK鈴木彩艶などを起用しながら、前田大然や菅原由勢、高井幸大、旗手怜央、古橋亨梧などにさらなる出場機会を与えていくだろう。
また、3月シリーズは招集外ながらも、予選で招集経験のある選手たちにも出番を与えたいところだ。
【超強豪との対戦を】
もうひとつ大事なことがある。日本代表がコテンパンにやられるような強豪国との強化試合を組んでもらいたい。アジアカップでの失敗をバネにしてチームが大きくジャンプしたように、日本代表がもうひと回り大きくなるためには自分たちを見つめるキッカケになる試合が必要だろう。
ヨーロッパ勢は欧州予選の兼ね合いで試合を組むのが難しく、南米のブラジルやアルゼンチンとのマッチメイクには大きな金額が必要になるが、目標に掲げるW杯優勝に近づくためには惜しみなく投資してもらいたいと思う。
10年前なら鼻で笑われたような「W杯優勝」も、いまならまんざらでもないまで日本サッカーは成長してきた。ただ、実現するためには越えなければいけないハードルはまだまだたくさんある。ここからW杯本番までの1年2カ月で一つひとつクリアしながら、過去最高成績が残せるようなチームへ進化するのを楽しみにしている。