サウジアラビア戦を0-0で終えたサッカー日本代表。その内容、データは昨年10月に引き分けたオーストラリア戦と酷似してい…
サウジアラビア戦を0-0で終えたサッカー日本代表。その内容、データは昨年10月に引き分けたオーストラリア戦と酷似していた。一定レベルの相手に引いて守られると手詰まりになる問題は、解決されていない。
【収穫が少なかったサウジアラビア戦】
すでにW杯出場を決めている日本にとって、ゴールレスドローに終わったホームでのサウジアラビア戦は、本番を見据えたうえでは収穫の少ない試合となった。

前田大然はサウジアラビア戦で3つのチャンスを逃し痛恨。しかし、日本の攻撃は早くから行き詰まっていた
photo by Nakashima Daisuke
強いて収穫を挙げるとすれば、右ウイングバック(WB)に純粋なアタッカーではなく、本職が右サイドバック(SB)の菅原由勢を配置しながら、今予選で採用している3-4-2-1が久しぶりにその特徴を発揮したという点だろう。
それを象徴するのが、日本のボール支配率だ。前半立ち上がりの5分間で81.4%を記録すると、その後も日本がボールを握り続け、前半15分間は83.1%、前半終了時でも76.6%を記録し、結局、1試合におけるボール支配率は77.6%という圧倒的な数字になった(AFC公式記録)。
加えて、どのエリアでプレーする時間が長かったのかを示すアクションエリアのスタッツでも、前節のバーレーン戦(日本のボール支配率は60.7%)では日本のアタッキングサードでのアクションエリアは18.6%だったのに対し、今回は31.9%をマーク。
つまり、この試合では多くの時間で日本が敵陣でボールを握り、攻撃を続けていたことがデータ上でも証明されており、日本が5バックになって自陣で守るシーンが限られていた点も含めて、布陣の機能性は上々だったと総括できる。
ただし、日本が3-4-2-1を攻撃的に運用できた主な要因は、相手の日本対策を覆すための対策を日本が遂行したからではなかった。それがサウジアラビアの戦い方に起因していたのは、試合を見れば一目瞭然だ。
「日本で試合をする場合、オープンな試合にはできない。(日本は)非常にいいチームなので注意をしなければならないが、守備という点では計画どおりにできたと思う」
試合後の記者会見でそう振り返ったのは、昨年11月からサウジアラビア代表監督として自身2度目の指揮を執るフランス人のエルヴェ・ルナール監督だ。
この試合のサウジアラビアは、前半23分に可能性の低いヘディングシュートを1本記録したのみ。無理してボールを保持しようとせず、徹底的に自陣で守り、リスクを排除した戦い方を最初から最後まで貫いた。W杯出場に黄色信号が灯っているサウジアラビアの現状を考えれば、プランどおりのゴールレスドローで勝ち点1を手にしたルナール監督が「結果に満足している」と胸を張ったのも頷ける。
思い出されるのは、昨年10月15日にホームで行なわれたオーストラリア戦だ。相手が勝ち点1を目指していたというバックグラウンドをはじめ、布陣、展開、構図など、ほとんどの要素が今回と似通っていた。そういう意味では、今回のサウジアラビア戦はその試合の再現だったと言っていい。
【昨年10月のオーストラリア戦と酷似】
その試合のオーストラリア同様、今回のサウジアラビアの布陣も3-4-2-1だったが、実質的には両WBに本職がSBの2番と13番を配置する5-4-1。ほとんどの時間帯で自陣に引いて守ったという点でも同じだった。
しかも、オーストラリアは試合序盤に前からプレスを仕掛けるシーンがあったのに対し、この日のサウジアラビアは前からボールを奪おうとする素振りもなく、自陣でボールを奪ったらロングキックで逃げ、ミドルゾーンで奪っても単独のドリブルで前進するのみ。3バックの両脇を突いた効果的なカウンター攻撃を見せることもなく、ミドルゾーンと自陣深くのエリアでコンパクトな5-4-1の陣形を維持して守るだけだった。
こうなると、当然ながら日本は容易に前進し、敵陣でボールを保持することができる。しかし、オーストラリア戦と同じように、一定のレベルの相手に引いて守られるとなかなかゴールチャンスを作れないという展開が、この試合でも再現された。
そのなかで、開始直後はボランチの田中碧と左シャドーの鎌田大地が頻繁にポジションを変えて、相手の5-4のブロック間を出入りしたことが奏功し、2度チャンスを作った。ひとつ目は9分。高井幸大のくさびのパスをライン間で田中が受けて反転し、素早く縦パス。DFラインの背後を狙った前田大然がエリア内で決定機を迎えたが、惜しくもシュートはポストを叩いた。
もうひとつは10分。左サイドで鎌田がスルーパスを配球し、中村敬斗が左から絶好のタイミングでクロスを入れたが、ニアに入った前田がシュートできず。前田は前半19分に得意の単独プレスからボールを奪ってGKと1対1になるシーンを作ったが、そのシーンでは自らボールコントロールを乱してしまい、好機を逸している。ゴールレスの引き金となったという点で、3つのチャンスを逃したことは痛恨だったと言える。
ただ、問題は前半10分のシーンをきっかけに、サウジアラビアの3バックが守備対応を修正し、それを機に日本の崩しが影を潜めてしまったことだろう。
特に3バック右に位置した5番が、鎌田がDFラインの前に入ってきた場合は前に出てタイトにマークし、前田のマークを中央の4番に任せるようになると、サウジアラビアの5-4のブロックはより強固になり、日本の攻撃は早い段階から行き詰まることになった。
【同じ過ちを繰り返した】
試合の構図が酷似していたので、スタッツもオーストラリア戦に近い。まず、オーストラリア戦でシュート12本だった日本は、この試合でも12本。相手はともに1本と、シュート数ではまったく同じ数字だ(日本の枠内シュートはオーストラリア戦が3本でサウジアラビア戦が2本)。前述したアクションエリアの31.9%というスタッツも、オーストラリア戦の31.1%とほぼ同じだった。
サウジアラビアがより守備的だったことも影響し、日本のパス本数はオーストラリア戦の598本からこの試合では715本に増加し、パス成功率も83.9%から90.1%にアップ。敵陣でのパス成功率も、オーストラリア戦の73.8%から今回は84.5%に上がっている。
一方、敵陣での縦パス本数はオーストラリア戦が4本(前半4本)で、今回は5本(前半4本)。左右からのクロス本数はオーストラリア戦の18本(前半8本)に対し、今回のサウジアラビア戦は13本(前半5本)だった。そのうち成功したクロスはオーストラリア戦が2本で、今回は1本と、いずれも似た記録になっている。
では、オーストラリア戦とほとんど同じ内容で終えた今回の試合を、どのように受け止めるべきか。今後の成長を求めるなら、やはり同じ過ちを繰り返したと反省すべきだろう。
もちろん、日本に工夫が見られなかったわけではない。たとえば後半の日本は、相手の5-4のブロックの「4」の両脇のスペースを活用すべく、特に左センターバック(CB)の伊藤洋輝が前に出て最終ラインが2枚(高井、板倉滉)になるシーンが増加。相手の1トップに対して日本がふたりで対応するという論理的な立ち位置をとった。
しかし、前に出た伊藤のポジショニングが左ハーフレーン内だったため、攻撃面で大きな変化を生み出せなかった。伊藤がパスを受けるとすぐに9番(後半61分からは19番)が接近し、伊藤が左大外の中村にパスしても、その時は中村が2番(後半は12番)に寄せられた状態でマッチアップ。結局、相手のマークのズレとギャップを作れなかった。
もし伊藤があまり前に出ず、横に動いて左大外レーンでパスを受けてからボールを持ち運べば、9番(または19番)の移動距離が長くなり、中央にスペースを作れたかもしれない。中村と縦関係で数的優位を作って2番(または12番)を剥がす可能性も生まれる。
あるいは、伊藤が大外でボールを受けた時に中村が左ハーフレーンに移動。2番(または12番)がついてくるなら、中村が空けたポジションにシャドーの鎌田が移動し、3人がローテーションする形で相手のマークにズレを生じさせることも可能になる。相手を動かせばズレやギャップが生まれやすく、そこに突破口が見出せるかもしれない。
【森保一監督の対応は?】
いずれにしても、日本はオーストラリア戦で得た教訓や課題をこの試合に活かせなかったことに変わりはない。
「監督として、次の手を打てるようにプランB、プランCなど、力をつけていかなければいけない」と試合後に語った森保一監督は、「今日の試合であれば、どうやって勝っていくか。システム変更なのか、人を代えるのか、相手のどこを突いていくのかということを選択肢として持っていきたい」ともコメントしている。
果たして、6月の2試合では3度同じ過ちを繰り返さないような準備を整えられるのか。同じような試合展開になる可能性は高くないが、W杯本番の戦いを考えると、4バック採用を含めた今後の采配は要注目だ。






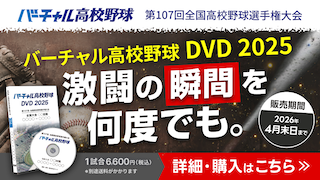











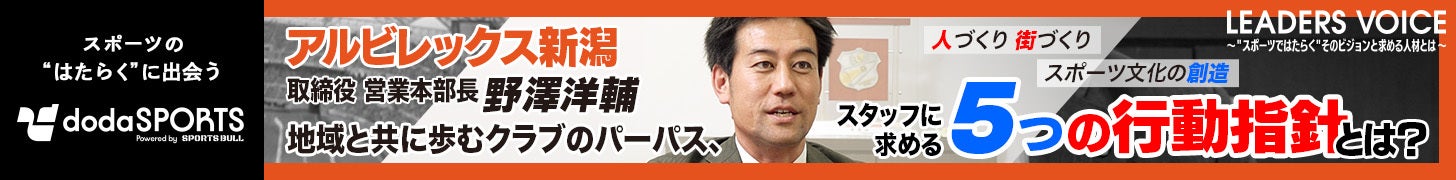






















































![サバレンカ、予選勝者の粘りに苦しむもストレートで3回戦進出「集中を切らさず戦い抜けた」[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012117260605067000.jpg)





