サッカーU-20日本代表は、U20アジアカップで戦い、年代別ワールドカップへの出場権を手にした。だが、表面上の結果だけ…
サッカーU-20日本代表は、U20アジアカップで戦い、年代別ワールドカップへの出場権を手にした。だが、表面上の結果だけではなく、この大会ではさまざまな「変化」があった。現地に飛んだサッカージャーナリスト後藤健生が、サッカー日本代表とアジア、そして世界の「距離」の変化について指摘する。
■2大会連続で「準決勝敗退」の日本
中国で開催されていたU-20アジアカップ。決勝戦では、準決勝で日本を破ったオーストラリアがサウジアラビアにPK戦の末に勝利して初優勝を飾った。
オーストラリアはグループAに属していたため、準々決勝、準決勝ともに対戦相手(イラク、日本)より休養日が多い好条件だったし、全6試合のうち5試合を同じ宝安体育場でプレーするというアドバンテージも持っていた。
ただ、そうした点を割り引いたとしても、グループリーグから準決勝までの5試合すべてで90分までで勝利した。“完全優勝”と言ってもいいだろう。
2トップにはムサ・トゥーレとルカ・ヨヴァノヴィッチという点を取れるFWが固定され、MFの4人が複雑にポジションチェンジしながら相手に的を絞らせず、さらに超攻撃的な右サイドバック、ダニエル・ベニーが攻め上がるなど攻撃は多彩。5試合で16得点を決めている。
優勝も期待されていた日本だったが、U-20ワールドカップ出場権獲得という最低限のノルマこそ達成したものの、準決勝でオーストラリアに完敗を喫して2大会連続で準決勝敗退で終わった。
オーストラリア戦では準々決勝から先発8人を変更したことが大きく影響したが、準々決勝のイラン戦で延長まで戦い、中2日しか休養日がなかったのだから仕方のない選択だった。
■この数字で「出場権」はむしろ幸運
しかし、それは自ら招いた状況だった。
グループリーグ第2戦でシリアと引き分けてしまったため、準々決勝までターンオーバーを使えなくなってしまったのだ。本来なら、グループリーグ3戦目で主力を休ませておくべきだった。
オーストラリア戦を除けば、日本はすべてのゲームでボール保持率で対戦相手を上回り、自分たちでボールを動かして試合をコントロールする時間が長かった。従って、シリア戦は勝っておくべき試合だったし、イラン戦も90分までに決着をつけるべきだった。
だが、どの試合でもせっかく数多くのチャンスを作りながら、それをゴールという結果に結びつけることができなかった。
結局、日本は5試合を戦って1勝3分1敗、得点6・失点5という成績だった。この数字で無事にワールドカップ出場権を獲得できたのだから、むしろ幸運だったと言わざるを得ない。
日本の選手たちは間違いなく、一番うまかった。
ボールを扱う技術もそうだが、パスを受ける瞬間にしっかりと体の向きを変えたり、次にプレーしやすい場所にゴールを置くことによって、対戦相手は日本選手にプレッシャーをかけられなくなってしまい、結果として日本のボール保持が長くなった。
アジアの強豪と目される韓国やイランに対しても、日本はしっかりとボールを握って落ち着いて攻撃の形を作ることができた。
その優位を生かして攻撃の形を作れなかったのは、チームとしての戦術が確立できていなかったからだ。
■試合を経験するたびに「課題が修正」
日本のFW陣には、ターゲットになるような大型の選手は身長186cmの道脇豊だけだった。
かつて大型FWだった船越優蔵監督は、高岡伶颯(165cm)や神田奏真(178cm)、井上愛簾(177cm)といった身長の低いテクニシャンタイプを並べ、186cmという高さと強さを兼ね備えた徳田誉(鹿島)は招集されなかった。
従って、サイドから単純にクロスを上げるような攻撃は有効ではない。
とすれば、中央でパスを回してフリーの選手を作る形や3列目の選手が飛び出していくような形。さらに、サイドで攻撃を組み立ててから大きく逆サイドに振るなど、攻撃パターンを作ってコンビネーションの精度を上げておく必要があったはずだ。
だが、今大会ではそうした準備が十分だったようには見えなかった。
それでも、試合を重ねるごとに選手間の相互理解が深まっていった。中盤では大関友翔がパス回しの中心となって、やや守備的な小倉幸成とバランスを取り、そこにトップ下やサイドに入った佐藤龍之介が絡んでボールがよく回るようになった。
シリアと引き分けた後、1つ試合を経験するたびに課題が修正していくだけの、選手たちの応用力には目を見張るものがあった。
だが、フィニッシュ段階でのパターン作りまでは手が回らず、最後まで効率的に得点することはできなかった。イラン戦では開始早々に失点し、前半のうちに追いついて敗戦を避けることはできたが、得点は小倉のミドルシュートという個人能力に頼ったものだった。






































































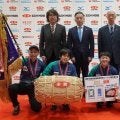



![アルカラス、難敵ポールを退け3年連続の8強進出!史上最年少の生涯グランドスラムに邁進[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012516260245513700.jpg)



