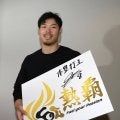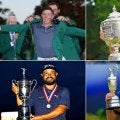熱狂度の高いアウェー戦を4-0で勝利すれば、普通ならば万々歳だ。無条件に大喜びしたくなる快勝である。しかしこの試合は例…
熱狂度の高いアウェー戦を4-0で勝利すれば、普通ならば万々歳だ。無条件に大喜びしたくなる快勝である。しかしこの試合は例外だった。
2026年W杯アジア3次予選、インドネシア戦。世の中に数ある4-0のなかでも、悪いほうから数えて何番目かに入るような、まるで褒められない内容の一戦だった。
インドネシアのシン・テヨン監督は試合後の会見で「最初の1点を我々が取っていたら結果は変わっていたかもしれない」と述べている。半分は同意したくなる分析である。「変わっていた」は引き分けか、日本の敗戦を指すが、それは言いすぎとしても、日本が苦戦を強いられたことは確かだろう。
一方、森保一監督は会見でインドネシアの女性記者の質問に「インドネシアはW杯本大会を戦う力はある」と答えているが、その見立ては間違いだ。リップサービスなのだろうが、そこまでの力はない。4-0は妥当なスコアである。しかし立ち上がりの9分、CB板倉滉がバウンド処理を誤り、その結果、相手FWラグナー・オラットマングーンがGK鈴木彩艶と1対1になったシーンで先制点を決めていれば、日本は逆転が精一杯で4点差にはならなかったのではないか。
町田浩樹、守田英正を経由して鎌田大地が左から折り返したボールを小川航基がプッシュした(記録はオウンゴール)先制点が決まった前半35分までは、日本は危なっかしいサッカー、もっと言えば悪いサッカーを展開していた。
それ以降、インドネシアは馬脚を現すように次第にボロを出し始める。試合の流れは日本に移行した。その5分後に、三笘薫のアウトサイドパスを南野拓実がきれいに合わせた2点目が決まると、試合は決まったも同然となった。

インドネシアを4-0で破った日本代表のイレブンphoto by Fujita Masato
なぜ、それまで格下のインドネシアに苦戦したか。アウェーのハンディや、試合開始とともにスコールのような強い雨が降り出したことも、日本の調子を狂わせた原因かもしれない。だが、それは芯を食った分析ではない。試合序盤の苦戦の原因を考えるうえで、アウェーや雨より何倍も重要な問題は、サッカーゲームの進め方にある。ベンチワークだ。
【引いて構える相手の「背後を突く」?】
布陣は両軍とも似ている。3-4-2-1(日本)対5-2-3(インドネシア)。3トップが開き気味に構えるインドネシアのほうが、5バックになりにくさという点では上だが、戦力の関係で5バックになる時間は日本より多かった。一方の日本は、3バックを維持する時間のほうが5バックに転じる時間より長かった。攻めている時間が断然、長かったからだ。
当然、ボール支配率で勝ったのは日本。ゲームをコントロールしてパスをつないだ。一方、インドネシアはそれを奪ってはカウンターを仕掛けた。先述の9分のシーンに加え、14分、15分にも逆襲から際どいチャンスを作っている。実力的に大きな差があるにもかかわらず、なぜこうした事態に陥ったか。
森保式3-4-2-1は、ズバリ言えば、カウンターを食らいやすいサッカーなのだ。5バックになりやすい3バック=守備的サッカーであるのに、ボール支配率が高い。この矛盾を見逃してはならない。
ボールを保持する場所はどこなのか。
森保監督は、前戦のオーストラリア戦後の会見に続き、この試合後の会見でも「素早く背後を突くサッカー」を口にしている。やろうとするサッカーについて、特に攻撃に関しては、これまで曖昧な言葉を繰り返してきた。策がないのではないかと怪しんだものだが、ここに来て頻繁に登場するのがこの言葉だ。
しかし、オーストラリア戦がそうだったように、相手は引いて構えている。裏を突くスペースは限られている。もし森保監督がインドネシアの監督なら、日本対策としてバッチリハマる戦い方だが、日本がインドネシアと対戦するときは空振りに終わる。この作戦を主導しているのはいったい誰なのか。
問題はここからだ。「素早く」と言っても、相手は引いて構えているので、日本の攻撃は必然的に遅攻になる。それでも素早くを意識すると、攻撃のルートは真ん中寄りになる。言い換えればサイド攻撃を重視しないサッカーだ。するとどうなるか。ボールを奪われる位置が中央寄りになる。カウンターを食らいやすいサッカーそのものとなる。
【カウンターを得意とする相手の餌食になる】
中央を"迫り上がる"ようにボールをつなぐサッカー、である。相手が四方(360度)から寄ってくるので、キープの難易度は高い。180度のサイドと比べれば一目瞭然だ。この中央迫り上がり型サッカー。加茂ジャパン、ジーコジャパン、第2期岡田ジャパンの途中まで、日本の専売特許だった古典的と言うべきサッカーである。
当時、主として使われていた布陣は4-2-2-2。中盤に好選手が溢れていた中盤王国と呼ばれた時代のサッカーである。名波浩コーチらはその渦中にいた選手として知られるが、また20年前のサッカーに戻ってしまったかのような錯覚に陥る。
中央を迫り上がるようにつないでいく日本は、詰まると初めてサイドに展開する。三笘にボールが渡る経緯を見ればわかりやすい。サイドバック(SB)がいないので、当然といえば当然である。それでも左はまだマシなほうだった。堂安律がウイングバックとして構える右サイドに至っては、途中交代で菅原由勢が入るまで(後半17分)、活用すらされていない。
難易度の高い真ん中攻撃が増えれば、真ん中で攻守は切り替わる。すると真ん中の選手は瞬間、逆モーションになりやすい。サイドで奪われるより何倍も危険な行為を、森保ジャパンは頓着なく繰り返した。悪いサッカーの典型だ。
「素早く背後を突くサッカー」は、言ってみれば速攻だ。3-4-2-1はそれに相応しい布陣として認知されているので、やりたいサッカーに適した布陣と言える。だが、相手は弱者だ。相手には適さない。逆に相手に歓迎されることになる。
日本の「素早く背後を突くサッカー」がハマる相手、つまり日本をボール支配率で確実に上回る強者は、世界に何チームあるだろうか。逆にいまの日本のサッカーを歓迎するチームのほうが断然多い。強者と対戦する前に、カウンターを得意とする弱者の餌食になる。インドネシアに前半35分まで善戦を許す姿に、その危険性は端的に表われている。
この強度の強いプレッシングの時代において、難易度が高い真ん中攻撃の危うさに気づかぬ日本ベンチ。時計の針を20年戻したかのような、初歩的な過ちだと言っていい。ピッチ上にそうした症状が出現しても、特に気にする様子も、反省の弁もない。サッカー偏差値が低いと言われても仕方がないだろう。