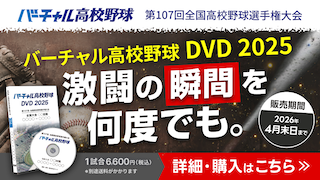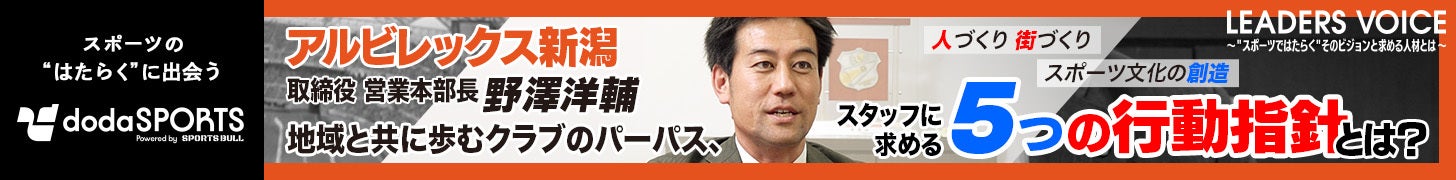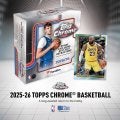広尾晃のBaseball Diversityインターリーグ(NPBでは交流戦)は、異なるリーグのチームが対戦する試合のこ…
広尾晃のBaseball Diversity
インターリーグ(NPBでは交流戦)は、異なるリーグのチームが対戦する試合のことを言う。練習試合やオープン戦などの非公式戦でも、異なるリーグのチームが対戦することがあるが、インターリーグの場合、同一リーグのチームと対戦する「公式戦」と同等であり、その勝敗はリーグ戦の順位に反映される。また、選手成績も公式記録に加えられる。
日米プロ野球が2リーグ制になった経緯
インターリーグの紹介の前に、MLBで2リーグができた経緯について簡単に説明しよう。
19世紀後半にアメリカ東海岸で生まれた野球は、強豪チームが集まって「リーグ」を結成、対戦成績で競うリーグ戦を始めた。その中で最も有力なリーグが1870年代に「メジャーリーグ」を名乗って、他のリーグと差別化した。こうしてできた最初のメジャーリーグがナショナル・リーグだ。以後、その他のリーグ=マイナーリーグのいくつかが、メジャーリーグを名乗ったが、長続きしなかった。1901年にアメリカン・リーグができ、この年から「2リーグ制」となった。1903年には両リーグの優勝チームが雌雄を決する「ワールドシリーズ」が始まった。
日本のプロ野球(職業野球)は、1936年に始まったが、戦後の1949年までは1リーグ制だった。しかし、1950年からMLBに倣ってセントラル、パシフィックの「2リーグ制」になって現在に至っている。

アメリカでは、野球だけでなくアメリカンフットボール(NFL)や、バスケットボール(NBA)なども2リーグ(カンファレンス)制となっている。
ヨーロッパのサッカーなどは、2リーグではない。2リーグはアメリカン・スポーツ独特のスタイルだと言えよう。
なお、韓国プロ野球(KBO)は一時期2リーグだったが現在は1リーグ、台湾プロ野球(CPBL)は当初から1リーグだ。
2リーグ制のメリットとデメリット
「2リーグ制」のメリットとして、ペナントレースが並行して2つ行われることで、野球ファンの関心が高まることがある。一方のリーグが首位チーム独走のワンサイドの様相になっても、もう一方のリーグが接戦であれば、野球ファンの興味をつなぎとめることができるからだ。
また二つのリーグがあることで、リーグ対抗の「オールスター戦」や、ポストシーズン(ワールドシリーズ、日本シリーズなど)が充実する。
一方で、2リーグ制のデメリットとしては、同時期に同じ国でプレーしているにもかかわらず「全く対戦しないチーム、選手」が必然的に発生することがある。
MLB史上最高の選手と言われるベーブ・ルースは、22年のキャリアの内21年をアメリカン・リーグでプレーしたが、同じ時期に373勝を挙げた大投手、ピート・アレキサンダーはナショナル・リーグでプレーしたため、1926年のワールドシリーズで対戦しただけだった。
NPB史上最多の400勝を挙げた金田正一はセ・リーグでしかプレーしていないため、同時代に活躍しNPB史上最多の3085安打を打った張本勲とは公式戦でもポストシーズンでも一度も対戦がなかった。
MLBでもNPBでも、両リーグは設立した経緯が違い、リーグの運営方針も異なっていたため、対抗意識があった。「指名打者=DH」の導入に際しても、MLBではアメリカン・リーグだけが、NPBでパシフィック・リーグだけが導入。NPBでは開幕戦の日程も別個に決めるなど、日米ともに互いの対抗意識が極めて強かった。
それもあって、MLBもNPBもこの形で長く興行を行ってきた。

インターリーグ、交流戦はなぜ始まったか?
MLBでは1994年からサラリーキャップ制度やFA権の拡大を巡って選手会がストライキを行い、野球人気が下落した。
これに危機感を抱いたMLBでは1997年からインターリーグを実施するようになった。
リーグ側は半信半疑で実施したが、ファンが「新しい対戦カード」ができたことを歓迎し、観客動員は前年の6016万5727人から6323万4442人へと増加した。
NPBでは1960年代から読売ジャイアンツが圧倒的な人気となり、巨人戦のテレビ中継は高視聴率を稼いだ。このためセ・リーグ各球団は巨人との対戦試合での「放映権収入」をベースとするビジネスモデルができていた。
巨人戦がないパ・リーグは多くの球団が赤字で、親会社の補填によって球団を維持していた。
1980年でいえばセ・リーグの観客動員は1032万2000人、パ・リーグは579万7500人と、観客動員の面でも大きな格差ができていた。
パ・リーグはMLBに倣って「インターリーグの実施を」とたびたび働きかけていたが、セ・リーグ側は「巨人戦の試合数が減る」ために頑なに拒んでいた。
しかし、2004年の球界再編騒動が起こると、新たなセ・パ両リーグの体制を構築する際に「交流戦」を実施することが決定された。
その背景には、プロ野球の地上波での放送が激減し「巨人戦の放映権」を基本とするビジネスモデルが崩れつつあったこと、さらにはセ・パ両リーグで地域密着型のマーケティングが盛んになり、パ・リーグの観客動員も増加したことがある。
2004年までNPBの観客動員数は実数ではなく「球団発表」であり、500人しか入っていなくても球団の裁量で2000人と発表するなど、数字は正確ではなかった。このために、交流戦導入前後の観客動員の変化はわからない。
しかし2005年に両リーグで1920万2488人だった観客動員は、2023年には2579万2294人と34.3%増加している。少なくとも「交流戦」は、NPB興行を行う上でマイナスではなかったと言えるだろう。

焦点となった「指名打者」
MLB、NPBともにインターリーグ・交流戦を行う上での留意点は「指名打者」だった。指名打者制のないナショナル・リーグ、セントラル・リーグと、指名打者制があるアメリカン・リーグ、パシフィック・リーグの対戦では、原則として指名打者制があるリーグのチームの主催試合でのみ、指名打者制が導入された。
NPB、MLBともに両リーグの実力は「互角」だと思われていたが、どちらも「指名打者制のあるリーグ」の方が勝ち越している。
NPBは昨年までセ1122勝73分パ1253勝、でパが勝ち越し。パの勝率は.528。MLBは2022年までア3636勝ナ3330勝でアが勝ち越し。アの勝率は.522だった。
なぜ指名打者制のあるリーグの方が強いのか、については議論が分かれているが、指名打者という「9人目の打者」を育成しているリーグの方が、打線の層が厚くなるから、とか、指名打者があることで先発投手は代打を送られて交代することがなくなるので、より長く投げる実力を蓄えるから、などの説がある。
インターリーグ、交流戦で広がった愉しみ
MLBは2023年からナショナル・リーグも指名打者制を導入、MLBではこれを「ユニバーサルDH制」としている。DHか投手でしか出場していない大谷翔平が、今季、ナショナル・リーグのロサンゼルス・ドジャースに移籍できたのはこの「ユニバーサルDH」ができたからだ。
またインターリーグは前年まで1チーム20試合だったが、2023年からは46試合になり、最低でも全球団と2試合対戦することとなった。
NPBは当初、6球団と6試合総当たりの36試合だったがこれが2007年に4試合総当たりの24試合になり、2015年からは3試合総当たりの18試合になっている。
インターリーグ、交流戦が導入されたことで、野球ファンは多彩な対戦カードの試合を観戦することができるようになった。
この制度がなければ、MLBでいえばヤンキースのスラッガー、アーロン・ジャッジと、ドジャースの大エース、クレイトン・カーショウとの対戦はあり得なかった(ジャッジは通算6打数1安打ながらその1本が本塁打)。NPBでいえば、ヤクルトの村上宗隆とロッテの佐々木朗希の対戦もあり得なかった(村上は通算2打数1安打1本塁打)。
MLBで27年、NPBでも19年が経過して、インターリーグ、交流戦はプロ野球のペナントレースにすっかり定着したと言ってよいだろう。