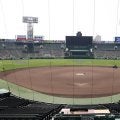サッカーは無数のディテール(詳細)であふれている。サッカージャーナリスト大住良之による、重箱の隅をつつくような「超マニ…
サッカーは無数のディテール(詳細)であふれている。サッカージャーナリスト大住良之による、重箱の隅をつつくような「超マニアックコラム」。今回は、「地球の裏側で…」。
■世界で最も風変わりなスタジアム
翌5月29日、私は『ボンボネーラ』と呼ばれるボカ・ジュニアーズのスタジアムの記者席にいた。おそらく、世界で最も風変わりなスタジアムだろう。収容は6万人。三方を三層式で急傾斜の巨大な観客席が囲むが、東側のタッチライン沿いのスタンドだけは、タッチラインに合わせて幅が100メートル以上あるのに、奥行きは10メートル足らずという平べったい5階建てのビルで、それが記者席を含む「メインスタンド」なのである。各階の道路側には階段と通路があり、席は5列ほどだった。私の席は3階だったが、タッチラインに手が届くかと思うほど近かった。
驚いたのは、記者席に「案内人」がいたことだった。入場口でチケットを示し、記者証を見せると、制服を着てきちんと帽子をかぶった案内人が先に立ち、3階の席まで案内してくれる。そして、白い手袋でさっと座席をぬぐい、「どうぞ」と言ってくれる。まるで劇場のようだ。「ありがとう」と言って座ると、彼はまだそこに立っている。チップが必要だったのだ!
■スタンドから流れ落ちる「幅70メートル」の大滝
ポーランドは前大会(1974年大会)3位のチームで、そのときの中心選手だったMFカジミエシ・デイナやFWグジェゴシ・ラトなどが健在。さらに新進気鋭のスブグニェフ・ボニェク(当時21歳)も右サイドバックとしてプレーしていた。前半31分にラトがスピードを生かして先制したが、アルゼンチンは前半のうちにダニエル・ベルトーニのPKで追いつき、後半には落ち着いて試合を支配して、レオポルド・ルーケとベルトーニが決めて3-1で逆転勝ちした。初めて南米の地で見る南米代表のプレーは、その技術の高さ、音も立てずにボールをコントロールする、「シルク」のようなタッチに感銘を受けた。
だが、この日最も驚いたのは、選手入場のときだった。ピッチへの選手入場口はバックスタンドの中央にあったのだが、そこから選手たちが姿を表すと、両ゴール裏のスタンドからいっせいに「紙吹雪」が投げられたのだ。いや、「紙吹雪」というより、「滝」だった。新聞紙を10センチ角ほどに引きちぎった束を、ゴール裏のサポーター全員が両手につかみ、いっせいに投げるのだ。それは、まるで落差30メートル、幅70メートルの壮大な瀑布だった。結果として、両ゴール前は芝生が隠れ、真っ白になった。選手たちはそんなことお構いなしにプレーを始めた。
「郷に入っては郷に従え」という言葉がある。冬季ということもあったのか、「ラ・ボンボネーラ」のピッチはボコボコだった。翌年のワールドカップに向け、リバープレート・クラブのスタジアムは改装中だった。そのため、この年の国際試合シリーズはすべて「ラ・ボンボネーラ」で開催された。だが紙吹雪にもピッチにも、ポーランドの選手が動揺した様子はなかった。「南米でのサッカー」を体験することがこの遠征の目的だったのだから、異様な光景でもそれを受け入れ、自分のプレーに集中するところに、欧州のサッカーの強さを見た気がした。
■「食べにくい」ハンバーガー
だが、日本から来た25歳の駆け出し記者は、あらゆることに驚きっぱなしだった。そして、あらゆることに「地球の裏側」を感じた。
この試合の前日、ブエノスアイレスに到着した日の午後いっぱいを休む間もなくあちこち歩き回った私は、午後8時過ぎにホテルに戻り、ようやく荷物をほどいた。そして空腹を覚えたので、「夕食をとらなければ」と、2階のティールームに行った。この日だけは、この町で最高級のシェラトン・ホテルに部屋をとってあった。日本から予約できるのは、ここひとつだったからだ。
ティールームのカウンターに座り、メニューを見ると、「ハンバーガー」があった。出てきたのは、なんとも食べにくい代物だった。日本で食べるハンバーガーのパテには、さまざまな「混ぜ物」が入っていて、かみやすくなっている。ところがこのハンバーガーは、おそらく肉が90%以上なのだろう。さすが「ビーフ大国」である。しかし、食べにくさは尋常ではなかった。
コーラで流し込むようにそのハンバーガーを食べ終え、22階の部屋に戻ると、部屋の電話をとって東京への国際電話を依頼した。東京の編集部に無事到着したことを知らせなければならない。「少し待ってください」という交換手の答えに、受話器を置いて待つことにした。しかし、待てども待てども電話は鳴らない。私は大きなベッドに倒れ伏し、いつの間にか熟睡してしまった。突然、電話のベルがけたたましく鳴る。ようやく電話がつながったという。時計を見ると12時を過ぎている。依頼してから3時間以上たっていた。
この頃、アルゼンチンと日本間の国際電話は、アメリカ経由で行われていた。まずアメリカにつなぎ、そこから日本につないでもらうのだ。そのアメリカとの回線数が少なく、空くまで順番を待たなければならない。それに3時間もかかったのだ。私は、南米大陸から中米・メキシコを経て、アメリカのロサンゼルスまで電線がつながっている図を想像した。そして、そこからは太平洋を海底ケーブルで横断するのだ。
太平洋横断ケーブルが開通したのは1964年。日本からグアム島、ウェーク島、ミッドウェー島を経由し、ハワイまで海底ケーブルをつないだのは、日本のKDD(現在のKDDI=auの前身)だった。アメリカ本土からハワイまではすでに海底ケーブルでつながっていたので、日本とアメリカがつながったことになった。
「地球の裏側から2万キロをつなぐんだ。3時間なら御の字かな」
もうろうとした頭でようやく電話連絡を終わり、そんなことを考える間もなく、私は再びベッドに倒れ伏して爆睡してしまった。