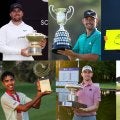私が語る「日本サッカー、あの事件の真相」第20回ドイツと南アフリカ――2度のW杯で体感した真逆の試練~玉田圭司(3) 2…
私が語る「日本サッカー、あの事件の真相」第20回
ドイツと南アフリカ――2度のW杯で体感した真逆の試練~玉田圭司(3)
2010年南アフリカW杯。現地入りした日本代表が本番を目前にして取りかかったのは、アジア最終予選までのシステムや戦術を一掃して大幅にメンバーを入れ替えるという、大きな"オペ"だった。
中盤の底にアンカーを置く、4-5-1にシステムを変更。最終予選では主力だった中村俊輔、内田篤人、楢崎正剛らが先発から外れ、キャプテンも中澤佑二から長谷部誠に代わった。
そして1トップには、玉田圭司ではなく、岡崎慎司を試したのち、本番では本田圭佑が配置された。出場機会を失った玉田は、このシステムのどこに自分が当てはまるのか、考えを巡らせた。
「レギュラーチームのシステムが4-5-1になったんですけど、サブ組はトップ下を置く4-2-3-1で、僕はそのトップ下だった。だから、(レギュラー組の)4-5-1でプレーする場合、(自分は)どこでできるか考えたんですけど、答えが見つからなくて......。
もとは1トップでしたけど、そこに入ったのは体が強くて、体を張れる本田。僕がそこに入ると、また役割が変わってきてしまうので、ハマらないだろうなと思いました。途中から出るとしても、トップ下でいくのか、サイドから攻撃的にいくぐらいしかなかったので、自分の居場所(を見つける)というのは、すごく難しかったです」
新たなシステムのなかで、自らのポジションを見つけられずにいた玉田。気持ち的にはややささくれ立った状態にあったが、本番を迎えて、もはや「ああだこうだ」と言っていらない状況となった。
土壇場で採用したシステムによって、日本は初戦のカメルーン戦に勝利。チームとしての方向性が確定した。
「初戦に勝ったことで、(チームとして)『このシステムでいくしかない』というのが決まりました。そこで、自分が『(それよりも)こうしていこう』という立場でもなかったので、僕もそのやり方についていくしかなかった。
歯がゆい部分はありましたけど、チームが結果を出したなかで不貞腐れるわけにもいかない。気持ち的には苦しかったですけど、試合に出るためにやるべきことをやる、ということに集中していました」
続くオランダ戦では1点リードを許すなか、後半32分から途中出場。臆することなく、自分のプレーに徹したが、ゴールは遠かった。
「試合は(ヴェスレイ・)スナイデルの一発にやられて、成す術がないというか......。あのサッカーは守りきる力はあるけど、その上をいかれると挽回するのが非常に難しい。個人としても何もできなかった。
そこで結果を出すことができなかったのは(自らの)力不足ですが、やっぱり頭から試合に出られない、というのがすごく悔しかったです」
出場機会を失った悔しさを抱えていたのは、玉田だけでない。中村俊や内田ら、サブ組に落ちた面々は皆、同じ思いを抱えていた。
その思いを多少なりとも解消できたのは、日々の練習の時だ。紅白戦ではレギュラーチームを圧倒し、尖った気持ちが少しは和らいだ。
「紅白戦は楽しかったですし、(レギュラーチーム相手に)勝てたことで『自分らもまだイケるな』と思っていました」
守備的なサッカーを実践し、チーム内でさまざまな思いが交錯するなかにあっても、日本は3戦目のデンマーク戦を勝利して、グループリーグを2位で通過。ラウンド16ではパラグアイと対戦した。
試合はどちらも消極的な戦いに終始し、時間だけが過ぎていった。玉田は延長後半の開始から出場。岡田武史監督から「点をとってこい」と送り出された。
「試合は凡戦でしたね。どちらも点がとれないだろうな、という流れのままPK戦までいってしまった。結果的に点をとれていないので、何とも言えないですけど、僕ひとりで何とかというよりも、ベンチにいたメンバーたちのアイデアを生かして戦ったほうがいいかなと思っていました。
PKはスタメンで出ていたメンバーが蹴る、というのが決まっていたけど、僕も蹴りたかったです」
パラグアイは最初から"PK戦に持ち込めば"という粘り強さを見せて戦った。そして、その思惑どおりPK戦の末に日本を下した。
玉田は、南米予選という修羅場を潜り抜けてきた経験の差が、最後のPK戦に出てしまったと思った。選手が悔し涙を流すなか、玉田も無表情のまま涙を流した。玉田がピッチで涙を流したのは、この時と、この半年後の2回だけになる。
「『終わったなぁ』と思いつつ、寂しさも感じました。(このW杯に挑んだチームは)勝つごとに一体感が生まれて、いいチームになった。(2004年の)アジアカップで優勝した時の雰囲気にすごく似ていました。試合も負けるべくして負けたわけじゃなく、PK戦なので、悔しさが余計に大きかったです」
W杯における手応えは、前回大会のドイツW杯の時よりも大きかった。
「試合に出る時間は少なかったですけど、2006年のドイツW杯の時ほど世界のすごさは感じなかった。日本と世界との距離が縮まったのか、それともオランダとは対戦したけど、ブラジルとか世界のトップクラスと対戦しなかったからなのかわからないですけど、それでも日本は世界のベスト16レベルでは十分にやれるんじゃないかなと思いました」
前評判は低かったが、日本は2002年大会以来、2度目の決勝トーナメント進出を果たした。だが、玉田個人としては、苦しい大会となった。
「自分は、ドイツW杯の時よりも(チーム内で)年齢的に上になり、チームを支えていったり、下の選手にアドバイスをしたりする立場で、なおかつ、プレーでも結果を出していかないといけないと思っていました。
でも結局、試合に出られないことが、やはり悔しかったです。食事をしていても、試合に出られない選手は悔しさがにじみ出てくる。そうじゃなきゃ、プロサッカー選手じゃない。
だからといって、大会中はどうしようもできない。それで、W杯が終わったあとは、その悔しさをすべてJリーグにぶつけました。『見てろよ!』って気持ちで戦えたのは、南アフリカW杯での悔しさがあったからです」
南アフリカW杯から戻ってきた玉田は、Jリーグで"鬼神"のような動きを見せた。最終的に再開後だけで11ゴールを挙げ、チームの勝利に貢献した。
11月20日、第31節のアウェーの湘南ベルマーレ戦は、勝てば優勝という試合だった。初のリーグ優勝を目前にして、名古屋グランパスの選手たちの動きには硬さが見られたが、後半21分、玉田がヘディングでゴールを決めた。そして、この虎の子の1点を必死に守った名古屋が悲願の栄冠を手にした。

2010年11月20日の湘南ベルマーレ戦、玉田圭司がゴールを決めて名古屋グランパスが初のリーグ優勝を飾った
アディショナルタイムにベンチに下がった玉田は、試合終了のホイッスルが鳴ると号泣した。
「優勝できた喜びと同時に、自分は『まだやれるんだ』と証明することができた。ピクシー(ドラガン・ストイコビッチ監督)の胴上げも、ほんと感無量でした。僕は、この人のためというより、この人に認められたいという気持ちでプレーしてきた。褒めてもらいたい子どもみたいな感じだったんです」
そう言うと、玉田は昔を思い出したかのように笑った。
「僕って、(チームを率いる監督に)好かれるか、嫌われるか、どっちかなんですよ。後者の場合、毛嫌いされて扱いづらいレッテルを貼られるんです。そういう感じだから、セフ(・フェルフォーセン監督)の時がそうでしたけど、いろいろと苦労しました。
今考えると、自分の考えを曲げて(監督の意向に)もう少し歩み寄っていればというのはありますけど、そうではなかったところが、僕らしいと言えば僕らしい。ですから、後悔はしていないです」
玉田はその後、2014年シーズン終了後に名古屋を退団。翌年、J2に降格したセレッソ大阪に移籍して2年間プレーした。そして2017年、J2に降格した名古屋に復帰し、チームのJ1昇格に貢献した。
2019年からはJ2のⅤ・ファーレン長崎でプレー。2021年11月に現役引退を発表した。現在は、その長崎でアンバサダー&アカデミーロールモデルコーチを任され、自身の地元である千葉では子どもたちにサッカーを教えている。
W杯が近づくたび、日本代表のW杯における過去の軌跡として、2006年W杯のブラジル戦での玉田のゴールがテレビで流れる。あれから17年という時が経過しようとしているが、あのゴールのすごさは今も色褪せることはない。
「あのゴールがあって、僕のことをわかってくれる子どもたちがたくさんいるんですよ。その当時、まだ生まれてない子どもたちから、『YouTubeで見たよ』とか言われるとうれしいですね。親御さんが子どもにそのゴールを見せて、サッカースクールに参加してくれた子もいます。あの時は、ただの1点でしたけど、のちに(自らにとって)これだけの影響力を持つゴールになるとは思わなかった」
サッカースクールでは、ドイツW杯で再認識した「楽しむ」ことを重視して、子どもたちにサッカーを教えている。同時に、自らが"見せる"ことも大事なことだと捉えている。
「以前、那須(大亮)さんのYouTubeで、僕に密着するみたいな企画をしてくれた時に、サッカースクールでボレーシュートを決めたんです。そうしたら、『玉さん、それができるの、マジでデカい。それが、一番子どもに刺さる』って、那須さんが言ってくれて。
確かに豪快なシュートとかを決めると、(子どもたちは)『この人、すごい』みたいな空気に変わる。思えば、ピクシーもそうだったんです。動けないけど、テクニックはすごいし、そこは衰えない。練習中にボレーシュートとか見せられると、『すごいな』ってなっていましたからね。
(自分も)そういうのをなくしたくないので、今もトレーニングをしています。何歳になっても、見せられる指導者、監督でいたいんです」
玉田は今、(子どもを対象にした)スクールだけでなく、プロの指導者としての道を進もうとしている。すでにA級ライセンスを得て、今後はプロクラブで監督になるために必要なS級ライセンスを取得することになる。
理想の監督像は特にないが、プロで「楽しむ」ということの難しさを知るからこそ、あえてそのポリシーを重視する。ドイツW杯の際に目に焼きつけられた、余裕を持って楽しんでプレーしている時のブラジル代表のすごさ、そのすばらしさ。たとえそこまでは至らないとしても、そこを目指すべきだと、玉田は考えているのだ。
(文中敬称略/おわり)
玉田圭司(たまだ・けいじ)
1980年4月11日生まれ。千葉県出身。習志野高校卒業後、1999年に柏レイソル入り。2002年のシーズン後半から多くの出場機会を得て、以降は主力として定着。2004年には日本代表入りを果たす。その後、2006年に名古屋グランパスに移籍し、2010年にクラブ初のリーグ制覇に貢献した。その間、日本代表でも活躍し、2006年、2010年と2度のW杯に出場。2021年に現役を引退。現在は現役最後に所属していたV・ファーレン長崎のアンバサダー兼アカデミーロールモデルコーチを務めるなど、指導者として日々奔走している。