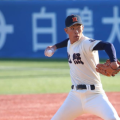1996年オリックス日本一に貢献した小川博文さんが語る拓大紅陵・小枝守監督「甘言は人を腐らす」――。拓大紅陵(千葉)で3…
1996年オリックス日本一に貢献した小川博文さんが語る拓大紅陵・小枝守監督
「甘言は人を腐らす」――。拓大紅陵(千葉)で33年間、指揮をとった故・小枝守監督の“名言”のひとつだ。今から約40年前、1984年の選抜高校野球で同校は創部初の甲子園出場を果たした。準々決勝で桑田真澄、清原和博のKKコンビがいたPL学園(大阪)に敗れたが、オリックス、横浜で活躍した小川博文さんの活躍で初出場ベスト8という快挙を成し遂げた。小川さんも“恩師”の言葉の力に魅了され、その後の人生を変えてもらった一人だった。【楢崎 豊】
冒頭の言葉は、小枝監督が生前、当時の拓大紅陵の理事長から学んだ言葉だった。錆は鉄を腐らすが、甘い言葉は人を腐らすという意味を持つ。自分にも選手にも厳しかった指揮官は、この信念を持ってチームを作りあげ、社会に出しても恥ずかしくない人材を育てた。筆者も拓大紅陵、そしてU-18日本代表監督だった指揮官を取材し、たくさんの“金言”を授かった。取材を通じて「あいつ(小川さん)はいいところで打ってくれたんだよ」と懐かしく話す表情を今でもよく覚えている。
だから、小川さんが小枝監督から受けた薫陶の中身を知りたかった。現在、勤務するオリックス球団を通じてインタビューを申し込んだ。小川さんは監督との出会いから、甲子園のこと、そしてプロ入り後のこと……鮮明に覚えていた。そして、丁寧に教えてくれた。
名門の日大三から、まだ何も揃っていなかった拓大紅陵へ小枝監督が赴任したのは1981年だった。グラウンドでは草むしりから整備を始め、選手獲得に奔走。1982年に入学してきたのが小川さんだった。
監督が力のある言葉で決意を表していたことを小川さんは忘れることはない。「監督は3年で甲子園に行くというプランを打ち上げていたんです。その核となる選手は一体、誰なのか? と思っていたら、僕を含めた新入生9人。3年後に甲子園を目指そうということになったんです」。
選手たちを自宅や、学校近くに住まわせたりして、長い時間を共有。指導に情熱を注いだ。目標達成のために1年生を厳しく鍛えた。朝から晩まで目を光らせ、世間からは「鬼の小枝」と評判だった。「でもね、ふと見せる笑顔に騙されるんですよ。グラブを買ってくれたこともありましたし、寮などでは親身になって話をしてくれたり、親みたいな存在でした」。
1984年選抜に初出場で8強入り、感想文に記された言葉が支えになった
グラウンドでは、鬼気迫る表情で選手を指導したこともあった。指揮官の言葉通り、拓大紅陵はその「3年」で甲子園出場を果たすことになる。
秋の千葉大会で八千代松蔭、習志野などの強豪を次々に撃破し、初優勝を飾った。選抜の参考になる関東大会では準々決勝で法政二(神奈川)と対戦。小川さんのサヨナラタイムリーで4強入りを決め、選抜切符を手に入れた。
甲子園1回戦の智弁学園(奈良)相手に小川さんは3ランを放つなど3安打4打点の活躍。法政二との再戦となった2回戦にも勝利し、準々決勝へ駒を進めた。PL学園には0-6で敗れるも、見事な快進撃だった。
何もなかったところから、作り上げた野球部。当事者たちには万感の思いが込み上げてきたはずだ。学校関係者から「よくやった」の声が出るのも当然だ。しかし、監督は一切、自分も選手も称えることはなかった。小川さんは当時を回想する。
「選抜が終わったあと監督が『甲子園の感想文を書け!』と言ったんです。甲子園はこんなに広くて、歓声がすごくて、一球でリズムや流れが変わってしまうとか、高校生の知識の中で精一杯書いて、私は提出したんです」
小枝監督はその感想文に、メッセージを書いて各々に返却した。小川さんの作文用紙には『一球を疎かにするものは、一球に泣く』と記されていた。後にプロ野球選手となっても、この言葉はずっと小川さんを支えたという。
変わった野球観…ダブルヘッダーの合間にも行った自主練習
「すごく印象に残っているね。一番残っているね。やっぱり、野球だけじゃなくて、何事も疎かにしてはいけないんです。もちろん学生もなんですけど、大人として、社会人として、大事なことなんちゃうかな。その言葉をずっと高校卒業後も、結びつけていましたね」
甲子園に出た後のことを生前の小枝さんに聞いたことがある。「よくやったとか甘い言葉をかけたら、夏の甲子園は絶対に出られない。選手たちを引き締めようと思った」と選抜の帰りの新幹線で部長に、一からやり直すと宣言したそうだ。そんなに早く気持ちを切り替えていたことを聞き、驚いたものだった。
小川さんの野球観も変わっていった。例えば、ダブルヘッダーの練習試合で失策をした時のこと。午前中の第1試合で犯したミスをそのままにはしなかった。昼食もとらずに、自主的にノックを受けた。監督もコーチも指示を出してはいない。打てない時も同じ。空いている時間を見つけては黙々とバットを振り、修正した。
ダブルヘッダーの場合、2試合目は控え選手を使うことも多いが、小枝監督はミスした小川さんを主力だが続けて起用した。ミスをそのままにしない姿勢を監督は評価していた。そこでしっかりと好結果を残すあたりが小川さんのプロ野球選手になった所以だろう。
「エラーをしたら、先輩や後輩、チームメートに迷惑をかけてしまう。打てなかった日とかは寮でもバットを振っていましたね。努力したと言われますが、それが当たり前だったんですよね。夜中振っていたら、それを見ていた下級生に『感動しました』と言われたこともありましたね。あの言葉で、自分に対しての責任感が生まれましたね」
チームの中心選手だった小川さんを引き締めた拓大紅陵に慢心という言葉は無縁で、夏の千葉大会を制して、春夏連続甲子園出場を決めた。小枝さんからの金言が自分を飛躍させてくれた。だからこそ、今でも忘れることはないのだ。
卒業後は本当は「教師になりたかった」小川博文さんが追った背中
監督は選抜後「やっぱり、みんなの高校野球をいい形で終わらせてあげたいんだ。いい形というのは人それぞれ考え方が違うかもしれないけど、みんなにとってプラスになるような形で終わらせてあげたいんだ」とチームを引き締めた理由を選手に話していたという。厳しくも、選手の成長をいつも願っていた。
小川さんは社会人の名門・プリンスホテルを経て、1989年にオリックスに入団。強打の内野手としてレギュラーを獲得し、95、96年のリーグ連覇に大きく貢献。1番から9番までこなし「全打順本塁打」も達成した。パンチ力だけでなく、通算169犠打、54犠飛と“黒子”にもなれる存在で、強いオリックスの象徴だった。こういうプレースタイルも恩師の言葉が起点となり、積み重ねてきた数字だった。
「自分の“戒め”にもなりましたね。今、どうしたらいいのか。お前は今、何したらええねん……とか、絶えず自分を向上させようという気持ちになれました。そこで止まってしまうのは嫌だった。もっともっと小枝さんから話を聞きたかったですね。時にはもちろん厳しいことも言われましたけど、今思えば本当によかったな、と」
高校卒業後、実は小川さんは教師を目指そうと思ったという。それは小枝監督の教育者としての姿に「自分もこうなりたい」と未来を重ね合わせていた。監督にも教師になる希望は伝えていた。だが、導かれた先は社会人の名門、そしてプロ野球の世界だった。
引退後もコーチなど野球界で活躍し、近年はオリックスのジュニアチームの監督を務めるなど野球振興に尽力している。小枝さんは小川さんの高校3年間だけを見ていたのではなく、ずっとその先も視界に捉えていたのだろう。野球の伝道師、そして自分の思いを広く伝えていける人材になれる――。そう信じて今も天国から教え子を見守っている。(楢崎豊 / Yutaka Narasaki)