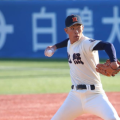サッカーは無数のディテール(詳細)であふれている。サッカージャーナリスト・大住良之による、重箱の隅をつつくような「超マ…
■日本にやってきたゼーラー
さて、西ドイツ代表から退いて1年半、サッカーからの引退を半年後に控えたゼーラーは、1972年1月、ハンブルガーSVとともに日本にやってきた。日本代表との2試合は、最初が1月9日、東京・国立競技場、そして第2戦が横浜の三ツ沢球技場。初戦は4万人がはいり、3-2でハンブルガーSVが勝利したが、第2戦はとんでもない試合となった。冬の冷たい雨に見舞われ、グラウンドも田んぼのようになってしまったのだ。
「こんな雨のなかではプレーしたくない」とばかりに、日本の主力選手は何人もこの試合を欠場した(ウォーミングアップもしなかった)。風はそう強くなかったものの終始強い雨が降る観客席では、誰もがずぶぬれになりながら傘を手放さなかったから、そう少なくは見えなかったが、発表された観客はわずか2000人だった。だがそのなかで、ゼーラーはひるみもしなかった。第1戦と同様、90分間ピッチに立ち続け、チームの先頭に立って戦い続けたのだ。
そして後半34分には右からのクロスを受けてヘディングで勝ち越し点を叩き込む。マーカーの視野から逃れるように左に動き、クロスが入れられる瞬間に右前にはいってきた駆け引きと走りのタイミング、ボールの落下点の見極め、そしてせりにくる相手を空中で制する体の使い方と、まさにヘディングシュートのお手本のようなゴールだった。
■代表チームでの新たな役割
クラブで公式戦トータル581試合492ゴール(ハンブルガーSVでは580試合490ゴールだったが、引退後の1978年4月、41歳のときにコーク・セルティックでアイルランド・リーグのシャムロック・ローバーズ戦にゲスト出場し、6-2の勝利で2得点を記録している。当時のアイルランド・リーグでは、こうしたゲスト出場がよく行われていたという)、西ドイツ代表で43ゴール。「無数」と言っていいほどのゴールを挙げたゼーラーだが、そのナンバーワンは、何と言っても1970年ワールドカップ・メキシコ大会の準々決勝、イングランド戦で見せた「奇跡のバックヘッド」だろう。
ブンデスリーガでは、1960年代半ばにバイエルン・ミュンヘンが急速に力をつけ、その若い力がそのまま西ドイツ代表の底上げをした。フランツ・ベッケンバウアーが1966年のワールドカップで西ドイツの中盤に君臨するようになり、ブンデスリーガではゲルト・ミュラーが猛烈な勢いでゴールを量産し始めていた。ブンデスリーガの初年度(1963/64シーズン)には30ゴールを記録して当然のように得点王となったゼーラーだが、1968年後半には、得点能力としてはミュラーのほうが上であることを認め、代表からの引退を決意した。
だが西ドイツ代表監督ヘルムート・シェーンは断固認めなかった。「新しい役割がある」というシェーンの言葉に、ゼーラーは再び闘志を燃やし、最前線の中央でのゲルト・ミュラーとのコンビネーションという試みに挑戦した。そして迎えたのが、1970年のワールドカップだった。シェーンは、いまでいう「トップ下」のようなポジションでゼーラーを起用したのだ。
■努力が生んだ奇跡のゴール
初戦のモロッコ戦では、思いがけなく先制点を許したが、後半にゼーラーが同点ゴールを決め、そしてミュラーが彼らしい至近距離からの押し込みで決勝点をものにした。グループを首位で突破した西ドイツは、準々決勝で4年前の決勝戦の相手、イングランドと当たる。そしてこのときも、4年前の決勝戦と同様、イングランドが赤、西ドイツが白のユニホームを着て小さなレオンのスタジアムのピッチに立った。
イングランドが攻勢をとった。モダンそのもののボールなしのランニングで西ドイツの守備を崩し、後半4分までに2-0とリードを奪ったのだ。西ドイツの反撃ののろしを上げたのはベッケンバウアーだ。後半23分、するするともち上がり、正確なシュートを決めて1点を返す。そして後半37分、「その瞬間」がくる。
猛攻をかける西ドイツ。かろうじてクリアするイングランド。そのクリアボールを、ハーフライン近くでカールハインツ・シュネリンガーが拾い、イングランドのゴールに向かってロビングを送る。ペナルティースポットあたりにいたゼーラーがゴールエリアの右角に向かって走り出る。追いすがるイングランドのアラン・ムレリー。
ゼーラーも体勢が悪い。ボールを見上げて振り返ったため、ゴールラインに背を向けていたのだ。だがその体勢からさらに右外に体を傾けながらジャンプしたゼーラーの後頭部がかろうじてボールをとらえる。するとボールはゆっくりと弧を描き、イングランド・ゴールの左に吸い込まれたのだ。ハンブルガーSVのトレーニンググラウンドの芝をはげさせるほどのヘディング練習。その積み重ねが生んだ「神業」、まさに「奇跡」のゴールだった。
試合は延長の後半3分にミュラーが決勝点を決め、西ドイツが4年前の「リベンジ」を果たす。だが、0-2からの逆転というドラマを生んだのは、最後の最後まで試合をあきらめず、相手ゴールに迫ったゼーラーの魂のこもったヘディングシュートだったことは間違いない。そしてこのゴールは、ゼーラーにとって西ドイツ代表での43ゴール目、最後の得点となった。
■名誉キャプテンにふさわしい人格
「我らがウーベ」と呼ばれ、ドイツ国民から愛された英雄。しかし彼が愛されたのは、その得点だけによるものではない。穏やかで礼儀正しく、ファンにも気持ち良く接し、すべてのサッカー選手のロールモデルとなるような人柄と、常にフェアな態度があったからこそ、彼はドイツが生んだ最高の選手のひとりに数えられ、1954年のワールドカップ優勝チームを率いたフリッツ・ワルターに次ぐ「西ドイツ代表名誉キャプテン」に選ばれたのだ。そうした彼の人格を世界に示したのが、1966年ワールドカップの決勝戦だった。
それから数十年間も話題になり続けたあのゴール、延長後半6分、バーに当たって真下に落ちたジョフ・ハーストのシュート。主審と副審が話した結果、副審が「はいっていた」とうなずき、ゴールが認められた。主審がセンタースポットを指すのを見て、西ドイツの3選手が副審のところに走り寄った。90分終了寸前に西ドイツの同点ゴールを決めたウォルフガンク・ウェーバー、ジギ・ヘルト、そしてウォルフガンク・オベラーツ。激しい口調で副審に詰め寄る3人。そこに寄ってきたのがゼーラーだった。
彼は副審には何も言わず、3人に声をかけ、なおもあきらめきれないウェーバーの肩に手を置いてポジションに戻らせたのだ。どんなに抗議しても変えられようのない判定を強い自己抑制で受け入れ、残された時間で反撃しようというゼーラーの態度は、世界の人びとの心を打った。
若いころから頭がはげ上がり、穏やかな顔をしてひとりで街を歩いていれば、現役当時でも「小太りのおじさん」ぐらいにしか見えなかったに違いないウーベ・ゼーラー。しかし間違いなく彼は20世紀の世界のサッカーを代表するサッカー選手のひとりであり、世界中のファンから敬愛される本物のスポーツパーソンだった。