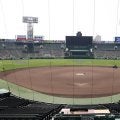「日韓W杯、20年後のレガシー」#26 松田直樹と2002年の記憶・後編 2002年日韓ワールドカップ(W杯)の開催から…
「日韓W杯、20年後のレガシー」#26 松田直樹と2002年の記憶・後編
2002年日韓ワールドカップ(W杯)の開催から、今年で20周年を迎えた。日本列島に空前のサッカーブームを巻き起こした世界最大級の祭典は、日本のスポーツ界に何を遺したのか。「THE ANSWER」では20年前の開催期間に合わせて、5月31日から6月30日までの1か月間、「日韓W杯、20年後のレガシー」と題した特集記事を連日掲載。当時の日本代表メンバーや関係者に話を聞き、自国開催のW杯が国内スポーツ界に与えた影響について多角的な視点から迫る。
数々の若き才能が輝き、世界にその存在を知らしめた日韓W杯の日本代表。そのなかの1人が、25歳とキャリアの最盛期を迎えていた松田直樹だろう。「フラットスリー」の一角を担い、世界の屈強なアタッカーと対峙。2011年、34歳の若さでこの世を去った松田だが、日韓W杯で見せた勇姿は多くのファンの脳裏に今も深く刻まれている。今回は松田がプレー以外で果たした役割と、サッカー選手として不世出のメンタリティについて振り返る。(文=小宮 良之)
◇ ◇ ◇
日本サッカー史上、長谷部誠(38歳/フランクフルト)は最も聡明で頼りになる選手と言えるかもしれない。
自著『心を整える』にあるように、飛び抜けてメンタルコントロールに優れている。常に平常心を保って、プレークオリティを一定の水準から決して下げない。どんな状況にも、冷静に適応することができる。先日、ヨーロッパリーグ決勝でも、味方のケガでいきなりピッチに立ったが、すぐに状況を把握。完璧にラインを制御し、前に入った敵を確実に潰し、チーム全体を改善させた。
長谷部の心の持ちよう、メンタルは、ピッチでのリーダーシップにも結び付いていた。最高のチームプレーヤーだ。
2011年、練習中に倒れて亡くなった松田直樹はJリーグ史上最高のディフェンダーの1人である。
松田は、長谷部とは全く異なる「生き様」によって、その異彩を放ったと言えるだろう。それは「無頼さ」とも言い換えられるのか。むき出しの激しい気性で人を引きつけた。荒々しい人間性によってチームメートを引っ張って、戦いを引き回すことができたのだ。
「練習から本気でやり合っていたら、試合で負けるはずがない」
その単純明快さに、理屈を超えた求心力があった。
チームに一体感を生んだ日韓W杯直前のワンシーン
松田は2002年の日韓W杯で、日本代表のベスト16進出を力強いディフェンスで支えたが、周りから愛されるパーソナリティこそ、唯一無二だった。やや乱暴な言動も目立った。しかしむしろ、その人間味がチームを一つにした。
トルシエジャパンで、松田はどこか他人と距離を取るところがあった中田英寿をみんなと結びつけている。大会前のキャンプ、プールサイドでチームが団らんを囲むなか、まだ冷たい水に監督から選手が落ちて笑いを誘う。一番端で関わらないようにしていた中田を、彼は大声で巻き込んだ。
「中田が跳ぶぞ! 5秒で跳ぶぞ!」
松田の掛け声によって、大勢で一斉に中田をプールへ突き落とし、大いに沸いた。W杯に向かう、何気ない一瞬だった。ただのバカ騒ぎにも見えるが、そうしたコミュニケーションは意味を持っていた。
松田は仲間同士の機微を感じ、集団を好転させる行動を少しの気取りもなくやってのけるところがあった。
もっとも、サッカーに対しては厳しい一面も持っていた。ある選手がロッカールームで、「〇〇は凄い、天才。絶対に敵わない」と相手選手について手放しで称賛していた時、怒りをぶつけたこともあった。
「これから対戦する敵の同じポジションの選手を軽々しく褒めるんじゃねぇよ。やる前から負けているんだったら、プロサッカー選手なんて、とっとと辞めちまえって」
言葉は強かったが、真理だった。それは発奮を促すもので、気に懸けていた選手だからこその叱咤だろう。彼には戦いの心得があった。
「俺は気持ちが弱いんすよ」
松田は、そう告白したことがあった。
「Jリーグに入った頃、生意気なことを言っていたけど、内心はびびっていた。ラモン・ディアスやビスコンティという世界的な選手、他にも日本代表選手ばっかりで、パス一つでもミスったらどうしようと、びくびくしていた。そんな気持ちを隠すために大口を叩いた。適当にやるなんてもんは、俺にあり得なかったし、いつも腹を括って。自分にとってサッカーはすべてで、常に真剣勝負だったからね」
ジーコと折り合わず逃したドイツW杯、松田が唯一悔やんだこと
松田は、己の中にある弱さと向き合うことができた。それを打ち負かすのが、彼のメンタルコントロールだった。必然的に生き方は苛烈になって、仲間にも激しい競争を求めた。
「だせぇか、かっこいいか」
彼はその間を認めなかった。その明確な行動規範が、彼を「松田直樹」たらしめた。戦う者にはたとえ失敗しても最大の敬意を表し、目の前の敵は叩き潰す獰猛さで挑んだ。
松田は生き方によって、求心力を放っていたと言える。論理を超えて、その生き様がチームをも引っ張った。立ち姿だけで鬼のような気を放つ選手が、人懐っこく笑ってどこまでも仲間を大事にする。そのギャップが、周りを夢中にさせた。現代風に言うなら、「勝者のメンタリティ」の持ち主だ。
一方で、強固なメンタリティがあったが故に、簡単には折り合うことができなかった。フィリップ・トルシエ後、ジーコが代表監督になった時に生じた確執も、今となっては「松田らしい」と言わざるを得ない。
「もし俺がいたら、(2006年のドイツワールドカップ、国内組の選手と折り合いがつかなかったと言われる)中田を孤立させたりはしなかった。もっとできたことがあったと思う」
松田は自分のことで弁解はしなかったが、仲間たちのことで少し悔しそうに言った。
彼は苛烈にサッカー人生を駆け抜けた。目の前に迫った厳しい戦いをくぐり抜けるたび、艶やかに強くなった。その強さに、自信を得た。
サッカー選手として不世出のメンタリティだ。(小宮 良之 / Yoshiyuki Komiya)
小宮 良之
1972年生まれ。大学卒業後にスペインのバルセロナに渡り、スポーツライターに。トリノ五輪、ドイツW杯を現地取材後、2006年から日本に拠点を移す。アスリートと心を通わすインタビューに定評があり、『導かれし者』(角川文庫)、『アンチ・ドロップアウト』(集英社)など多くの著書がある。2018年に『ラストシュート 絆を忘れない』(角川文庫)で小説家としてもデビュー。少年少女の熱い生き方を描き、重松清氏の賞賛を受けた。2020年12月には『氷上のフェニックス』(角川文庫)を上梓。